Dec 28, 2006
贈答の詩⑤ 朝吹英和句集『光の槍』への挨拶詩

『光の槍』とは、ケルト神話に登場するダーナ神族の一人である太陽神「ルー」が持つ武器「ブリューナク」に由来するとのことです。朝吹さんの「あとがき」ではこのように書かれています。
『モーツァルトの交響曲三十八番二長調。仄暗い聖堂を出た騎士の青きサーベルに煌く陽光。駿馬の如くしなやかで力強いアレグロの主題がクレッシェンドしながら夏野を駆け抜ける。対位法的展開が綾成す光と影の時空を切り開いて前進する音楽のシャープなエッジ。闇の底から麦秋の煌きへの鮮烈な転位、「光の槍」に刺し抜かれて精神の夏が輝く。』
朝吹さんの俳句は、一読して音楽を中心として美術や歴史などへの造詣の深さがうかがえます。また、おだやかな日常風景も描かれていまして、句集全体の均衡関係がとても見事だと思いました。さて、この句集にどのよな挨拶詩が似合うのでしょうか?朝吹さんが書いてくださいました、わたくしの詩集「空白期」へのご批評のテーマが「時間」でしたので、それをたぐりよせながら、書きはじめましょう。
時間の煌き
この広大な世界 ちいさなわたくし
遠いひと ここにいるわたくし
神からの比べようのない贈り物
煌く時間の彷徨
そして 光の槍
春の朝
ブラインドの傾きをくぐりぬけた
幾筋もの光が一瞬照らし出したものは
モーツァルトの弾いたチェンバロ
レ音のない未完の楽譜 遠い時間
夏の真昼
雲の峰を仰ぎみながら
熱砂を歩く駱駝のおだやかな足取りを思う
その背に揺れる永い時間
足跡を失くしたひとはふたたびそこを訪れるでしょう
秋の夕暮れ
柱に刻まれた幾筋かの傷を残して
飛びたっていった子供たちよ
残照のなかに込められたふたたびの希望
あるいは時間の鍵はみつかりましたか?
冬の夜
青葉木菟の語る物語は
はじまりもおわりもない
騎士の投げた光の槍が
音もなくどこまでも時の闇を切り開くように
(二〇〇六年・ふらんす堂刊)
Dec 22, 2006
イノセント

監督・ルキーノ・ヴィスコンティ(イタリア)=遺作。
原作・ガブリエーレ・ダヌンツィオ
この映画は「ヴィスコンティ生誕100年祭」の一環として、『完全復元&無修正版』を八月二十三日にイタリア文化会館の「ウンベルト・アニェッリ ホール」で観ました。大変に美しい画面に驚かされましたが、その折には映画感想を書く気持はあまりありませんでした。しかし、二十一日午後にコーヒーを飲みながら、何気なく観たテレビドラマで、ふいに思い出したのでした。
どうということのないドラマです。夫以外の子供を身ごもった女性が、お互いにそれを承知で結婚し、その男児を産み、さらにその後に女児も産まれ、幸せな四人家族を築いていたのですが、中学生になった息子はそれに気付くのでした。育ての父親に「僕は産まれてこなければよかったんだね。」と問いかけますが、父親はそれをきっぱりと否定します。それによって息子は本当の父親に決別するのでした。
そのシーンを観ていましたら、ふいにこの映画を思い出しました。その少年の決意に、何故か心を動かされたのです。この世に子供が産まれてくることは、どんな事情があっても祝福されるべきものであるからです。
二十世紀初めのローマ。社交界にスキャンダラスな話題を振りまくトゥリオ伯爵は、未亡人の公爵夫人テレザと関係を持ちますが、妻ジュリアーナにそれを認めさせようとします。しかし妻は作家フィリポとの不倫に走り、彼の子どもを身ごもりましたが、お互いに離婚はできません。苦しみと憎しみと嫉妬のなかで子供は産まれてきたのです。そこでジュリアーナの子供への愛しさと、トゥリオ伯爵の子供への憎しみが交錯します。
ここにはヴィスコンティ自身を投影させた、貴族階級の地獄のような悲劇を冷徹に描き、加えてキリスト教の厳しい戒律をもこめているのではないかと思われます。これがヴィスコンティの遺作となったことも意味深いことかもしれません。
クリスマスの晩、教会に行かないトゥリオは、家族の留守に、乳母も無理矢理教会に行かせて、雪の降る戸外へ赤ん坊を晒して殺してしまうのでした。夫のもとを去る妻のジュリアーナ。トゥリオはテレザのもとへ戻るが、結局トゥリオはピストル自殺で幕を閉じるのだった。
「地上のことは地上で決着をつけたい」これが無神論者トゥリオの考え方だった。
Dec 18, 2006
若き詩人への手紙 リルケ

私事ながら、秋に詩集「空白期」を出しました。詩集を出すことにはいつでもたくさんの躊躇があります。それは何度体験しても克服することはできません。それでもあえて出すのは何故でしょう?
この詩集を出すと決めた時に、大切な友人から「詩を手放したら生きてゆけない、と言うほどの思いがあるか?」という質問(詰問?)を受けました。「はい。」とは言えなかった。しかし「いいえ。」では絶対に違う。「その質問には答えたくない。」と言いました。一旦決めてからの詩集制作過程は大変幸せな時間となりました。その後の発送の時間も淡々と過しました。そして、あらためてわたくしは「リルケ」に帰りたくなりました。
わたくしが師と思っている唯一の詩人新川和江さんに、十二月の初めにお目にかかりましたが、その折の新川さんとの会話の大半が「リルケ」だったということも、その大きな要因かもしれません。それから新川さんはすでにたくさんのお仕事をされて、詩人の育成にもお力を注いだ方であるにも関わらず、お会いする度に少女のように「よい詩を書きましょうね。」とおっしゃることへの驚きと歓びと同意とが、わたしを「リルケ」再読に連れていって下さったのかもしれません。以下はすべて引用です。大変に美しい翻訳ではないかと思います。
『日常の富を呼び出せるほどに自分が十分に詩人ではないのだと心にうちあけなさい。』
『芸術作品は無限に孤独なもので、これに達するのに批評をもってするほど迂遠な道はありません。愛だけがそれを捕えて引き止めることができ、それに対して公正でありうるのです。』
『一人の創造者の思想のなかには忘れられた幾千の愛の夜々がよみがえり、その思想を尊厳と高貴をもって満たします。』
『かつて少年の日にあなたに課せられたあの大きな愛は、失われたのだとはお思いにならないでください。あなたが今日でも生きる拠り所となさっている大きい良い願いや企てが、当時のあなたの心に熟していなかったかどうか、おっしゃることがおできでしょうか? わたしはあの愛がそんなに強く烈しくご記憶に残っているのは、それがあなたの最初の深い孤独であり、あなたが自分の人生に即してなさった、最初の内的な仕事だったためだと思います。』
これらの言葉を書き写すことで、心に残しておこうと思います。
(昭和三十九年・世界の文学36・中央公論社刊)
Dec 16, 2006
吉本隆明の読む明石海人―その2

何故こんな大変なテーマについて、無力なわたくしがあえて書くのか、自分でもわからないのですが、無力を承知で書くしかないとも思うのです。少しだけ明石海人についての簡単なメモも書いておきます。海人は一九〇一年生まれ、一九二六年頃にハンセン病を発病、一九三三年作歌を始める。一九三九年逝去。下記は歌集「白猫」に書かれた明石海人自身の言葉です。(抜粋)
『第一部「白描」は癩者としての生活感情を有りの儘に歌ったものである。けれども私の歌心はまだ何か物足りないものを感じていた。あらゆる假装をかなぐり捨てて赤裸々な自我を思いの儘に飛躍させたい、かういう気持ちから生まれたのが第二部「翳」で、概ね日本歌人誌に発表したものである。が、仔細にみれば此處にも現實の生活の翳が射してゐることは否むべくもない。この二つの行き方は所詮一に帰すべきものなのであろうが、私の未熟さはまだ其處に至ってゐない。第一部第二部共に昭和十ニ年乃至十三年の作で、中には回想に據ったものも少なくない――昭和十四年一月、長島愛生園にて。』
この歌集が出版されたのは二月、この年(一九三九年)の六月に明石海人にこの世を去りました。
さて、吉本隆明は一旦は明石海人の短歌の昇華を見たようですが、さらに別の視点から考察を続けています。たとえば短歌的声調を整えてはいるが、修辞的な統合を欠いた作品が海人の短歌に頻出することが、吉本にはどうしても気がかりだったらしいのです。下記の短歌は吉本がその例としてあげた作品の一部です。
(1)銃口の揚羽蝶(あげは)はついに眼(ま)じろがずまひる邪心しばしたじろぐ
(2)水銀柱窓にくだけて仔羊ら光を消して星の座をのぼる
(1)については、わたくし自身は、詩「韃靼海峡と蝶―安西冬衛(一八八九年~一九七五年)」の最後の一節である『すると一匹の蝶がきて静かに銃口を覆うた』をふと思い出しますが、この関連性については残念ながら、わたくしには裏付けはとれません。
そして、吉本隆明は一気に明石海人の短歌から彼の散文詩へと飛ぶ。この散文詩こそが明石海人が自己についても自己の死についても、非常によく相対化されていると吉本隆明は断言しています。海人の短歌の特徴である「過剰性」は、短歌のなかに散文的な資質が内包されていたことに起因するのかもしれませんね。
明石海人が生きた時代は、ハンセン病は絶望的な病気であり、さらに社会からの隔離、隠蔽が強いられた時代である。作歌の手法としても、過剰と思えるほどの意味づけへの欲求がありながら、それを押しとどめることを余儀なくされたという「理不尽」が明石海人の短歌の混迷を生んだのではないだろうか?ともわたくしには思えます。その理不尽の一例として。。。
そのかみの悲田施薬のおん后今も坐すかとをろがみまつる
みめぐみは言はまくかしこ日の本の癩者に生れて我が悔ゆるなし
わたくしの未熟さはわたくしが一番よくわかっていますが、それでもこれを書いておかなければ先へ進めないという思いがありますので、書いておきました。最後にこの一首を置いて、とりあえずこの項を終わることにします。
いずくにか日の照れるらし暗がりの枕にかよふ管絃のこゑ
吉本隆明の読む「明石海人」―その1
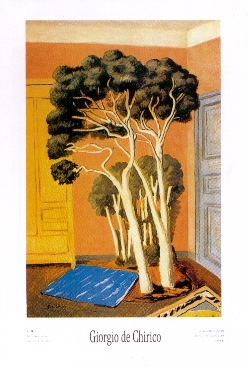
十一月十七日の日記に「ハンセン病文学全集・8・短歌(その一)」を書いて、最後に「つづく」と書きましたが、その代わりとして、これを書いておきます。これは二〇〇四年秋に書いたものですが、少し書き直しをして再録しました。
吉本隆明著「写生の物語」は、短歌と和歌に関する評論集です。このなかで吉本は歌人「明石海人」について書いています。この章はわたくしがここ数年来胸のうちで「病と言葉との関係」について揺れ続けていた疑問への解答をいただいたような気がするのです。吉本は海人の作品を「療養所文学」あるいは「ハンセン病」という括りのなかで読んだのではなく、「困難な病と言葉との均衡関係」について書いているのです。わたくしは下記の一首が明石海人の歌人としての個性をもっともよく物語っていると思いますが、どうでしょうか?
あかあかと海に落ちゆく日の光みじかき歌はうたひかねたり
まず、吉本隆明は明石海人の短歌を、ハンセン病の初期症状の段階と非常に病状が進んだ時期に書かれたものを、分けて批評しています。初期の明石海人の短歌は、病への恐怖と絶望感のなかにあっても精神の均衡は整っていましたので、作品の透明感はこの段階では保たれていると吉本は見ています。まず初期の短歌を。。。
人間の類を遂はれて今日も見る狙仙(そせん)が猿のむげなる清さ
診断を今はうたがはず春まひる癩(かたい)に堕ちし身の影をぞ踏む
しかし、吉本は海人の病状が進み、意識不明に陥るような状況が頻発する時期に書かれた短歌は、その痛切さのために短歌にあるべき音韻とリズムの乱れが見えてくると指摘しています。この時期の海人の短歌にはたしかに一首に盛り込むことが不可能と思われるものを盛り込んでしまったという「過剰性」が見られます。この特徴が海人自身の個性によるものか、彼のおかれた状況の痛切さによるものなのかを「解体」するために、吉本は海人の「叙景歌」のみを引き出してきて考察を試みるというもしています。そこから吉本は海人の歌人としての資質を探ろうとします。下記の短歌(1)(2)は病状の深刻な時期に書かれたもの。(3)は叙景歌として抜き取ったものです。
(1)しんしんと振る鐸音に我を繞りわが眷族(うから)みな遂はれて走る
(2)息つめてぢゃんけんぽんを争ひき何かは知らぬ爪もなき手と
(3)庭さきにさかりの朱(あか)をうとみたる松葉牡丹はうらがれそめぬ
そして吉本は下記のこれらの短歌に出会って、ようやくほっとする。ここには音韻とリズムが充たされたのちに、明石海人の短歌は天上に届いたと一旦は断言するのですが……。
鳴き交すこゑ聴きをれば雀らの一つ一つが別のこと言ふ
嚔(はなび)れば星も花瓣もけし飛んで午後をしづかに頭蓋のきしむ
(講談社・二〇〇〇年刊)
Dec 13, 2006
クリムト

監督=ラウル・ルイス・二〇〇五年・制作
十二月十一日午後。上野の森美術館にて「ダリ回顧展・生誕百年」を観てから、渋谷Bunkamura・ル・シネマでこの映画を観ました。ダリ(一九〇四年~一九八九年)とクリムト(一八六二年~一九一八年)の時代背景を、大雑把に区分をするならば、第一次大戦と第二次大戦 ということになるでしょうか?コーヒータイムと上野から渋谷への移動中の時間のなかで、わたくしたちは数十年の時間と場所の移動をするのだと、自覚(^^)する。・・・・・・というのはわたしだけ。同行者の桐田さんの心の推移は今だ計り難いのです。。。
一九一八年、第一次世界大戦のさなか、ウィーンの画家グスタフ・クリムトの最期のシーンから映画は始まりました。たった一人だけお見舞いに来た若い友人エゴン・シーレの存在にも気づかず、彼は夢のなかで今までの日々を彷徨っている。それが映画のストーリーとなるので、わたくしも時折迷宮を歩くこととなったのでした。これは伝記映画とは言い難く、現実と虚構との混在する世界でした。
一九世紀末、クリムトの描く作品は保守的なウィーンでの酷評、パリにおける絶賛とのはざまで翻弄されているようでした。その上クリムトはモデルとなった美女とは必ず恋に落ちるので、生まれた子供達は数十人とも言われている「女たらし」。その悪癖があのような美しく、幻想的な女性画を生み出したのだとすれば、なにをかいわんや。。。ここで、エゴン・シーレ(一八九〇年~一九一八年)のお言葉でしめていただくしかありません。
『現代芸術というものなんてありはしない。あるのは永久に続く芸術だけだ。』
Dec 10, 2006
わが悲しき娼婦たちの思い出 G・ガルシア=マルケス 木村栄一訳
手に取るなやはり野におけ蓮華草 滝瓢水
この小説は川端康成「眠れる美女」がベースになっています。お二人共「ノーベル賞作家」ですね。読んでいる途中の時期に、友人との対話のなかで俳人「滝瓢水(1684~1762)」のことが話題になったことがありましたが、その時にこの句を思い出しました。この句はたしか遊女を身請けしようとしている知人をいさめて詠われた句だったと思います。
独り身で生きてきた新聞社のフリー・コラムニストの男の九十歳の誕生日から、この物語は始まります。冒頭は『満九十歳の誕生日に、うら若い処女を狂ったように愛して、自分の誕生祝いにしようと考えた。』と書かれています。主人公の永年の友である娼家を営むローサ・カバルサスが彼のために探した十四歳の少女「デルガディーナ」に、主人公は恋に落ちる。彼は睡眠薬で眠っている「デルガディーナ」に寄り添い、一夜を過すだけでした。睡眠薬で「眠る」ことと、「眠らされる」こととは意味が大きく違います。後者の受動としての眠りは「仮死」です。ロミオの眠り、あるいは白雪姫の眠りの姿に似ています。寄り添う者が幸福な目覚めを願ってくれない限り「死からの幸福な蘇り」は訪れることはないのです。
彼のそれまでの人生でどうやら「恋」と言えるものは一回限り、それは彼が破局をさせた。「人を愛する」ということがなかったのです。その後の彼の人生は、必要な時だけ娼婦と過すという人生だった。そしてこの物語は九十一歳の誕生日で終わる。幸福な終わり方です。『これで本当の私の人生がはじまった。私は百歳を迎えたあと、いつの日かこの上ない愛に恵まれて幸せな死を迎えることになるだろう。』と・・・。その後に残される「デルガディーナ」のそれからのはるかに永い時間。。。。
この小説が何故書かれたのか?わたくしは答えを見出すことがなかなかできませんでした。訳者の解説によれば、一九八五年にマルケスが発表した小説「コレラの時代の愛」のなかで自殺した少女「アメリカ・ビクーニャ=デルガディーナ」を蘇らせる意味があったと書かれていました。この二十年間の時間に込められたマルケスの思いが、川端康成の小説「眠れる美女」の世界と交錯しながらこの小説はこのような物語となったのでしょう。
ちなみに比べてみますと、この小説を発表した時、マルケスは七十七歳、小説のモデルは九十歳。それに対して川端康成は六十一歳で「眠れる美女」を書き、モデルは六十七歳です。マルケスがこの小説を世に送ったのは二〇〇四年、日本で翻訳出版されたのは二〇〇六年となります。
(二〇〇六年・新潮社刊)
Dec 05, 2006
ミス・サハラを探して・・・チュニジア紀行 島田雅彦
この紀行書は美女を求めての旅ではないようです(^^)。冒頭から「私はユリシーズという男が嫌いだ。」とはじまるのです。そして『蓮の実喰いの国にとどまる願いを果たせなかったユリシーズの部下たちへの同情を込めていつかはジェルバ島を訪ねてみようと私は思っていた。』と書かれています。
この旅はある依頼からはじまりました。ヨーロッパの彼岸にある地中海リゾート地のチュニジアはヨーロッパ人で賑わうが、日本人はいないのだそうです。(おそらく、この本を書く以前の時点では。。)そのために島田雅彦は、この地を紹介するべく、三週間のリゾートの旅に出されるのでした。ですから、この本は砂漠と駱駝と太陽と海と、異質な時間の流れる人間の暮らしが島田によって書かれ、写真が半分を占める、一種の観光ガイドの本と言ってもいいでしょう。
旅する島田雅彦の時間の経過とともに内面の変化もあって、この心の旅路を追うことも興味深い。知らない土地に踏み込み、徐々にその土地や人間を理解しながら、戸惑いが島田特有のアイロニーに変わってゆく過程の面白さです。それぞれの土地で出会った人間や生き物、風景、出来事が時間の経過に沿って書かれています。そのなかでわたくしが興味深かったことを書いてみます。
まずは、ドゥーズの遊牧民の詩人との出会いです。遊牧民は夜のオアシスや砂漠のテントでは、夕餉の後でタンバリンをたたきながら歌います。白い服を着た詩人が喉の奥から絞り出すような高い声で。。。単調なリズムでも反復はない。朗誦は三十分に及ぶ。テキストがあるわけではない。全く日本語のわからないその詩人は、島田雅彦のつぶやいた即興の日本語の詩を、即座に音として記憶してその場で朗誦したというのです。書きしるすことをしない遊牧民詩人はこうして記憶を夜毎に朗誦するのでした。
次はカルタゴです。ここでは島田の書いたものをそっくり引用してみましょう。
『カルタゴ滅亡後、すぐにローマ人の入植が始まり、大浴場や劇場が作られ、町並みもローマ風に作り変えられた。ローマ浴場跡は今も残っているが、それが必要以上に大きく、なにゆえローマ人はかくも風呂に見栄を張ったか呆れるほどである。ローマ人は植民地には必ず大浴場を建てた。それこそリゾートの元祖というわけだ。観光を主な収入源とするチュニジアの今日と古代ローマの植民地だった昔は見事に結びついている。』
砂漠を抜けジェルバ島へ向かった時、町の賑わいやヨーロッパのツーリストの集団に出会った時には、砂漠に引き返したくなったと島田は書いています。それはかつてチベットから下界に下りてきた時の感覚に近いと。。アラビアのロレンスが「何故、砂漠を愛するのか?」という質問に「清潔だから。」と答えたそうですが、この言葉は砂漠に立ったことのある人間ならば、すぐにわかるでしょう。わたくしが八年ほど前にモンゴルの南ゴビ砂漠から持ち帰った砂が、全く変質していないことでも、これは証明されるのではないかと思います。島田雅彦はこのように書いています。
『この世の形あるものもないものも、いずれはこの砂に埋もれてゆくのだ、と呟いてみては、一人ほくそ笑むのである。それにしても砂漠の砂は、歴史の虚栄や残虐や愚行を数千年にわたって呑み込んできたにしては、美し過ぎる。』
最後に宗教に少しふれておきます。ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も砂漠から生まれました。そしてその宗教が原型に近いほど、純粋であり、人間の暮らしの根源に見合っているのではないでしょうか?「もう一度砂漠を見てから死ぬよ。」これが島田雅彦の旅の別れの言葉でした。
(一九九八年・KKベストセラーズ刊)
Dec 02, 2006
海を飛ぶ夢

監督 アレハンドロ・アメナーバル
これは実在の人物、ラモン・サンペドロの手記をもとに描かれた映画です。「尊厳死」は是か否か?それは映画を観終わってもなお、わたくしのなかでは答えは出なかった。海の事故で、頭部以外総てが不随となったラモン・サンペドロは、人生の約半分の二六年間をベッドの上で過ごしていたが、自ら命を絶つ決断をする。それは彼個人の人生だけではありえない、そこに関わる人間たちの人生にも関わる決断でもあるのだった。
まず、ラモンの世話をした老父と兄夫婦とその一人息子である。兄は弟のために海の仕事を捨てて、農業の仕事を選んだのだった。最も困難な役割を担った彼等は、それでもラモンの死を望んではいない。すべての今までの日々が無意味なものになってしまうだろう。
人権支援団体で働くジェネは、ラモンの死を合法にするため、弁護士のフリアの協力を仰ぐ。ラモンの話を聞くうちに、フリアは強く彼に惹かれていった。しかしフリアも不治の病に犯されて、やがてラモンとの死の約束をする。しかし、フリアの病の進行は「痴呆」という形であらわれて、ラモンを忘れてしまった。ジュネは夫との健康な性生活ののちに母親となる。
父親の違う二人の子持ちの未婚女性ロサは、テレビのドキュメンタリー番組のラモンを見て、彼を訪ねてくる。それは彼女の貧しさや不幸を克服するために、ラモンに寄り添う人生を選ぼうとしたように思える。何故か十月二十一日にここの日記に書いた水上勉の「筑波根物語」の女性たちをを思い出させる。しかし、死を決意したラモンには、ロサの存在は知人でしかないのだった。
そうした経過の後、法廷に車椅子で臨み、ラモンは「尊厳死」を認められる。彼はスペイン北部、ガリシアの澄んだ「海を飛ぶ夢」へ向かうのだった。わたくしは「これでよかったのだ。」とも「尊厳死はいけない。」ともいえないままです。わたくし自身がラモンだったらどうだったのか?という仮説をたてることすらできませんでした。
Nov 30, 2006
モカシン靴のシンデレラ 中沢新一 牧野千穂(絵)
「シンデレラ」の起源は旧石器時代と言われています。それがさまざまな形で世界中に拡散したものと考えられています。五百年ほど前、アメリカ大陸には先住民がおりました。そこに殖民者が入り込み、ヨーロッパ文化は先住民に伝わりました。先住民のなかの「ミクマク族」とフランス人植民者は互いの神話や民話や物語を語り合いました。そのなかの「シンデレラ=灰まみれ」が「ミクマク族」の心をとらえたのでした。
「ミクマク族」には不思議な技を持っている「灰まみれ少年」がいるのです。それは竈のそばにいて灰まみれになっている少年です。竈は死者の世界の入口なので、火のそばにいる者は死者と生者の交流の能力を持っているのです。この「灰」が最初のキーワードでした。 そして「ミクマク族」が疑問に思ったことは、「灰まみれ」の娘が「灰」を拭って、きれいに着飾って、王子の心を惹くという点でした。これは「聖なるミクマク族」には赦し難いことでしたので、ここで「ミクマク族」の「シンデレラ」が誕生したのでした。原題は「肌をこがされた少女」。英訳の原題は「見えない人」でした。
王子は「ヘラジカ」の霊に守られた偉大な狩人で、聖なる魂の少女にしか見えない「見えない人」、シンデレラのガラスの靴は父親のお古のモカシン靴(ここに密かな父親の守護を感じます。)、衣装は森の白樺の皮(わたしの独断ですが、これはヘラジカの食料ではないでしょうか?)、「幸運のお守り」とされる「ウェイオペスコール」と呼ばれるわずかな貝殻の首飾り(これは装飾ではないでしょう。)でした。
「シンデレラ」には、どの少女にも見えなかった「見えない人」が自然に見えたのでした。ここで少女は体にあった火傷の跡が消え、焼けちぢれた髪が美しい黒髪になったのでした。
この物語は、ヨーロッパにおける「女性の美しさと幸福」と言うテーマをさらに深め、純化させたということでしょう。中沢新一の翻訳とは言い難く、創作とも言い難い物語ですが、牧野千穂のやさしい絵がこの本をさらに魅力的にしたと言えるかもしれません。
(二〇〇五年・マガジンハウス刊)
Nov 27, 2006
贈答の詩④ 秋山公哉詩集「河西回廊」への挨拶詩
「西域」は秋山公哉さんの少年時代からの憧れの地、大学も「大谷探検隊」の資料に触れることのできるところとを選んだ程の長い夢であったようです。どうやらこの詩集はその旅を終えた報告の書と言えそうです。また、この詩集は以前からの詩集とは異なり、すべてご自分で手作りされたそうです。見事な作りで驚かされましたが、この「手作り」に拘ったということにも、秋山さんの深い思いがあるのかもしれません。
旅は四章に分けられて、「河西回廊」「蒙古高原」「玉門関」「天山南道」となっています。残念ながらわたくしが記憶を共有できるのは「蒙古高原」のみですが、この詩集から幻の旅をさせて頂きながら、一編の詩を書いてみました。
砂の記憶
そこには草原と空だけがあった
その境目あたりから
風が吹き 砂が舞い 光が広がる
雲は雲の形で地上に影を落す。
陽に焼けた額に知恵を満たしている
羊飼いの少女よ 馬上の少年よ
草の海の人々よ
わたくしたちは潮の海を渡ってまいりました。
幻の回廊をめぐり
牛が水を飲む一筋の河を渡り
砂に埋もれた城壁をさがしつつ
揺れる空中桜閣を追って。
そして草原から砂漠へ
生きているものはすべて砂に還り
神々は静かに風紋を渡り
わたくしたちの足跡も消えました。
永い旅の終わり
またここから始まる旅
吾亦紅の咲く野辺に立って
この花の名前の由来を再び思うのです。
(二〇〇六年・私家版)
Nov 26, 2006
私の上に降る雪は・わが子中原中也を語る 中原フク述・村上護編
中原中也の弟で五男の「中原呉郎」についてしばらく書いてきましたが、彼は「海の旅路」のなかで「故郷の中原中也」を書き、また中原家の系譜についても書いています。また四男「中原思郎」は「兄中原中也と祖先たち」と題した著書を出されているようです。これは未読ですが。
この本は、中也たちの母親である、九十五歳の中原フクの口述を村上護が文章におこしたものです。このお二人の出会いを結んだのは、どうやら呉郎のようです。村上護が「山頭火」について調べていた折に、その友人である呉郎に出会ったことがきっかけとなっているようです。
母フクの山口弁の語り口が、そのまま文体に再現されていますので、全体がやわらかく独特の世界を作りあげています。しかし、無残なことと言っては過言かもしれませんが、六人の息子達に恵まれながら、九十五歳のフクはその息子たちの死を見送ったという事実です。その息子たちに代わって、母親は我が子を語り尽くそうとしていました。過酷に見えるこの一冊は、すでに母親フクの創りあげた世界だとも言えるでしょう。死者はもう語ることはできない。生き残った者の想像力と記憶に頼ってこの一冊は成ったのです。
読み終えて、何故か腑に落ちないのです。中原家の生死の順番が狂っているからだろうか?死んだ母親を語る子供はあたりまえですが、死んだ子供を語る母親の切なさは深い。しかし反面では母親の無意識の脚色ということも感じざるをえない。これは「悪意」で言っているのではありません。母親であるわたくしの拭い難い「直感」なのです。
その一つの例をここで書いて見ましょう。
フクの夫謙助は、夫としてはエゴイストでしたが、子供の教育には厳格で潔癖でした。ことに長男中也は「神童」とまで噂されましたが、あまりの父の厳格さに抵抗して、ついに「落第生」とまでなり、父親から追放される形で家を出され、別の土地の学校に転校しますが、それは中也にとっては孤独なことではあったでしょうが「開放」でもあったはずです。その中也の成り行きから、中也以下の息子たちは冷酷とも言えるほどの極端な「放任」の姿勢をとり、ここにも謙助の「エゴイズム」が見えてきます。
その謙助の厳格な躾のなかで、庭の松の木に中也を縛って吊るしたというお話があります。当然母親のフクもそれに加担したことでしょう。夫に逆らえない妻の哀しさもあったかもしれません。これは中也から四男思郎が聞いた話だとされています。思郎が「兄中原中也と祖先たち」を書く時に、「その話はやめて欲しい。」とフクが頼んだのだそうです。しかし思郎は「それでも兄貴がぼくにそう話しておったから。」と答えたそうです。フクは口述のなかではこの事実を否定しています。これが中也独自のアイロニーであったのか、実話であるのかは知るよしもありませんが。。。
このお話からすぐに思い出したのは桐田真輔さんの詩「11月20日」でした。この詩は四章に分かれていまして、亡くなったお父上への追悼詩です。全編は桐田さんのHPで読めますので、ここでは抜粋のみとさせて頂きます。
(前略)
おとうちゃんと呼んでいた子供が
おとうさんと呼ぶようになったのはいつの頃だったか
陰で親父と呼ぶようになる前のことではあろうが
おとうちゃんは食事中についていた頬杖を
よこからとっぱらったり
泣きやまない子供を逆さにして
崖のうえからぶらさげたりもしたが
おとうさんはもうそんなことに関心はなかった
(中略)
精悍なシェパードが大好きだったおとうちゃん
鋤焼きの味付けに大量の醤油と砂糖を投入したおとうちゃん
僕は遠い昔に多摩川べりで
おとうちゃんの大きな影を見失ってから
幻の父を探し始めたのかもしれない
死にきることの難しい時代のどこかでいつか
僕はきっと父をみつける
〔 November.27.1999 〕
このわたくしの中で起きてしまった連想をおそるおそる桐田さんにお話しました。彼は「子供心に、父親は絶対にその手を離すことはない、という信頼がはっきりとあった。それさえあればさかさまな異界体験したようなもので、その印象の方が強いから、心の傷としては全く残っていない。」とおっしゃっていました。密かにほっとしました。しかし中也はどうだったのでしょうか?中也には「神童」という詩があります。
神童
わが生は、下手な植木師らに
あまりに夙く、手を入れられた悲しさよ!
由来わが血の大方は
頭にのぼり、煮え返り、滾り泡だつ。
おちつきがなく、あせり心地に、
つねに外界を索めんとする。
その行ひは愚かで、
その考へは分ち難い
かくてこのあはれなる木は、
粗硬な樹皮を、空と風とに、
心はたえず、追惜のおもひに沈み、
らんだ*にして、とぎれとぎれの仕草をもち、 (*漢字変換ならず。)
人に向かっては心弱く、諂ひがちに、かくて
われにもない、愚事のかぎりを仕出かしてしまふ。
(つみびとの歌 より)
この詩の背景には、その松の木事件を含めて、幼い日の中也を悩ませた父親の教導が大きな影を落としているように思えてならないのです。その父親から母親のフクが中也をどこまで庇うことが出来たのか?どこまで開放させることができたのかは、フクの口述には表れてこないのでした。
この本に関しましては、この問題だけに焦点を当てて、書いてみました。偏った感想ですが、中原中也と桐田真輔さんの少年期のちょっとした共通項と、視点の差異が書けたことでよしとしたいと思います。さらにこの本は二十代はじめの桐田さんが入手したであろうと思われる古書をお借りいたしました。これも何かのご縁でしょうか。
(一九七三年・講談社刊)
Nov 22, 2006
海の旅路 中也・山頭火のこと他 中原呉郎
十一月九日に『中原呉郎遺稿集ー山椒・三十二号』について書きましたが、それは「山椒」同人によって編纂されたものです。この「海の旅路」は新たに単行本として出版された遺稿集です。「三代の歌」「フク女覚書」「ヨハネ伝八章注釈補遺」は重複して掲載されていますが、それを含めて十四編のエッセーと小説が掲載されています。これらの著作も「山椒・三十二号」同様に、同人誌あるいは医学関係の雑誌などに掲載されたものを、呉郎の亡くなった後で遺稿として集められたものと思われますが、出典があきらかではありません。
表題となったエッセー「海の旅路」は昭和三十六年(一九六一年)八月から、翌年十二月までの間に「日本郵船」の船医として訪れた海外の土地について書かれています。訪れた土地は約十五箇所です。日本を恋しいとは思わなかったが、反面ではどこも同じことだという感慨があったようです。この旅の後で呉郎は「日本の普通の医者になろう。」という結論に至ったようです。
中原家は代々の医家であったのですが、長男の中也は家業を嫌い、文学の世界にいく。五男の呉郎は医師とはなったが、やはり中也同様に留まり続けることのない人間だったようです。略歴でもわかるように、軍医、船医、開業医、ハンセン病療養所の医師、無医村の医師など、変遷が多いようでした。それは友人「山頭火」が与えた影響も大きいものと思われます。
「紫陽花」は、シーボルトの日本人妻とその混血の娘、孫娘の三代の歴史小説になっています。娘は医師となりました。また「蘭学のころ」は日本の蘭学のはじまりと、それを受け継いだ人々の系譜がしっかりと記述されています。この二篇が医師「中原呉郎」の思想の原点であり、中原家の源流とも言えるのかもしれません。
また「故郷の中原中也」では、中原家を出た後の兄中也が五男呉郎へ与えた精神的な影響の大きさを物語っています。その後の生き方も、本来持っていたお互いの性格も異なりますが、評論家たちにはない弟の視線で「中也」を語る点には大いに注目してもよいでしょう。
(一九七六年・昭和出版刊)
Nov 18, 2006
ハンセン病文学全集・8・短歌(その一)
この文学全集は完結すれば全十巻となります。この短歌編は八回目の配本です。小説三巻、詩二巻、児童文学一巻、記録&随筆一巻がすでに刊行されています。その後、俳句&川柳一巻、評論&評伝一巻で完結となるはずです。作品は約八十年前から現在までに書かれたものです。これらの作品は全国のハンセン病療養所から集められたものですが、小さな出版社にとって、それは十年を越える歳月の作業だったようです。
ここでまず短歌の巻を取り上げます。・・・・・・と言っても、今後、詩の二巻、俳句&川柳の一巻について書く気持はありますが、あまりにも膨大な分量ですので、お約束はできません。さて、この六五六ページ、二段組の重たい歌集について、どこから書いてゆきましょうか?まずはこの全集の編集者の、二〇〇四年十一月のメモをご紹介します。
『長島愛生園では、双見美智子さんという八十過ぎの素敵なおばあさんが「神谷文庫」を守っている。宇佐美治さんは、ハンセン病資料の収集と保存に命を懸けている。多磨全生園ではハンセン病資料館などが出来るはるか以前から、山下道輔さんが「ハンセン病図書館」を運営し資料の保存してきた。
多くの「学者」が「新資料を発見」したと称して、マスコミに登場するが、それはそうした人たちが苦労して保存してきた資料の中から「発見した」に過ぎない。それも多とするけれど、そうした発表の中で、無名性に徹して惜しげもなく資料提供した彼らに言及する「学者」は少ない。』
これは大変に重い言葉です。そしてこの全集刊行の底流として、この考え方はずっと流れ続けていたのではないかと思います。この姿勢に敬意を表したい。
わたくしは元来この世界に詳しいわけではありません。そのわたくしがあるきっかけからここに収録されている作品の約十倍の作品を読む機会に恵まれました。(詩、短歌、俳句、川柳のみですが。)それらの本を読む時、注意深くその一冊づつの書かれた時代と、療養所の場所とを頭に入れました。そうして全部を読み終える頃には、おぼろげながらも、ハンセン病の隔離と差別の歴史、療養所の生活の様子、深い雪、波の音、川の音、風雨の気配、陽ざし、花、草木、野菜、動物、そして病の実態、治療薬の発見の歴史によって、その運命を別けられた人々・・・・・・書きつくせないほどのものをわたくしはそこから学びました。
だからこそ、わたくしはそれら半端な知識や理解を、もう一度捨てるところから再出発したいと思います。誤読、深読みはしないこと。ある作品が「ハンセン病」という括りをすでに超えて「普遍性」に届いているのだとしたら、わたくしはその「普遍性」の方へ視線を向けたい。
また、別の視点から考えますと、作品としての水準はどうか?という問題もあります。これを書くことはとても怖いことですが、あえて書きます。ここにはすべての書き手の作品が収録されていることです。永い文学の歴史のなかでは、このような「文学全集」は本来ならばありえないことなのです。ですからこれは「痛い声」の全集なのだと思われます。たとえば幼い子供が腹痛を訴えると、母親も同じところが痛む、というような遠い記憶を呼び覚まされるような出会いだった作品なのです。
この二つの視点のはざまで、途方に暮れているわたくしを、救い上げて下さった歌人は「赤沢正美」でした。赤沢は昭和八年生まれ。高見順賞受賞詩人であり歌人の「塔和子」の夫です。ここに収められた歌人は一二〇〇名、そこから何人かを選ぶのは大変に困難なことですが、かつてのわたくしのメモに残った作品を見ますと、大半が「赤沢正美」であったということから、ここでは赤沢のみの作品紹介にとどめます。
台風に揉まれし茎を起こしゐる草の自立は野にひそけしよ (投影)
人が立ちて歩き始めしときよりの背後の不安われもひきずる (草に立つ風)
明日のことまで断言をしてはならぬ貧しき者に貧し木の椅子 (投影)
地の飢えは癒されゆくか風落ちて眠りの如く降る雨のあり (投影)
病む膝を抱へて妻は眠りをり胎児標本の如くせつなく (投影)
(つづく。)
(二〇〇六年八月・皓星社刊)
Nov 11, 2006
アイヌ神謡集 知里幸恵 編訳
知里幸惠(ちり ゆきえ)は、一九〇三年(明治三十六年)生まれ。一九二二年(大正十一年)心臓病で急死。その翌年に「アイヌ神謡集」が出版されました。
この本の定本は、その大正十二年の「知里幸恵編『アイヌ神謡集』・郷土研究社刊」であり、北海道立図書館北方資料研究所蔵の「知里幸恵ノート」を、編集部が閲覧して、補訂したものです。
知里幸恵は十九歳の若さで亡くなっています。彼女は登別のアイヌの豪族の血筋を引き、豊かな大自然のなかで育ち、旭川の女子職業学校で日本語、ローマ字、英語を学びました。そして母と伯母からキリスト教を学ぶことによって、父祖伝来の信仰を深め、純化したものと思われます。
十七歳の時の金田一京助との出会いが、この「アイヌ神謡」の翻訳と出版への工程をより進めたものと思われますが、「生涯の仕事に。」という決意もならず彼女は夭逝されて、ここに収められたアイヌ神謡は十三編、残念ながらすべてということにはなりませんでしたが、これが「アイヌ神謡」として世に出た初めてのものでしょう。皮肉なことですが、この本がわたくしの手に届いたということは、先住民であったアイヌへの大和の侵略によって、日本語、新しい宗教がもたらされたという過去の歴史があったということでしょう。
これはアメリカ・インディアンの口承詩にも言えることかもしれません。祖先からの知恵、自然とともに生きてゆくことは自然への感謝と信頼であること、あたりまえのようでありながら決してあたりまえではない生きることの厳しさとやさしさを、わたくしたちは「侵略」によって知ったことになるのです。
これらアイヌ神謡は、文字がなく口承ですから、言葉の音として、本文はすべてローマ字で書きおこされていて、それを知里幸恵が日本語訳したものです。こうした仕事が出来る方はめったにいなかったことでしょう。
ここで謡う神は「梟」「狐」「兎」「小狼」「海の神」「蛙」「小オキキリムイ」「沼貝」です。「オキキリムイ」とは「人祖」です。これらの「神謡」からはもっとも根源的で平和に生きる意味が問い直されてゆきます。また「神謡」は、個々の物語に固有のリフレインがひんぱんに見られます。特にわたくしが美しいと思ったのは「梟の神の自ら歌った謡」のなかにあるこのリフレインでした。しかし文字の上でのリズムしかわからないのが残念です。
銀の滴降る降るまわりに、
金の滴降る降るまわりに、
アイヌの口承文学の中で、物語性をもったものは大きく分けて「神謡」(カムイユカラ)「英雄叙事詩」「散文説話」の三つに分けることができるそうです。その「遠い声」に耳をすませていたいと思います。
(岩波文庫 一九七八年第一刷・二〇〇五年第三十七刷)
中原呉郎追悼集 中原ふさえ編纂
十一月九日に掲載しました同人誌「山椒・三十二号・中原呉郎遺稿集」の年譜は、ややあいまいな点がありましたが、この本は奥様の「中原ふさえ」が編纂したものですので、こちらが正確かと思えますので、改めて年譜のみとりあえずメモしておきます。
この本はすべて友人、知人の追悼文を収録したもので、奥様の著述はありません。最後は中原呉郎の母上が「ふさえ」に宛てた手紙も収められています。これらに関しましては、改めて書いてみたいと思います。では年譜のみを。
(一九七六年・私家版)
Nov 09, 2006
中原呉郎遺稿集 「山椒・三十二号」
 (多磨全生園の姫りんご)
(多磨全生園の姫りんご)まず、このガリ版刷りの貴重な古い一冊を持っていらしたF氏の資料提供に深く感謝いたします。しかも古い貴重な本に触れるわたくしの緊張感を思い、すべてをコピーして提供してくださったお心遣い、ありがとうございました。また中原中也と中原呉郎を繋ぐ情報を下さった関係者の方々にも心より感謝いたします。
中原呉郎は、「中原中也」を長男とする六人兄弟の五男にあたります。職業は医師。これを掲載した同人誌「山椒」は、ハンセン病国立駿河療養所において「中原呉郎」が療養所の方々に声をかけて始まったものでした。「三十二号」は昭和五十年(一九七五年)に亡くなった彼の追悼特集号となっています。彼は医師の仕事のかたわらに詩、随筆、小説などを書いていたのです。「中原呉郎」の略歴を記しておきます。
大正五年(一九一六年)山口市にて生まれる。父は医師中原謙助、母はフク。
昭和十六年(一九四一年)長崎医科大学卒業。
ここに空白がありますが、この期間にはおそらく軍医だったのでしょう。戦後には自らの生き方に彷徨いつつ、船医をしていた時期もあるようです。
昭和三十年(一九五五年)国立多磨全生園勤務
昭和三十八年(一九六三年)国立駿河療養所勤務
昭和四十年(一九六五年)茨城県稲敷郡河内村国保療養所長勤務。
河内村は「無医村」だったのです。
昭和四十九年(一九七四年)八王子市散田南多摩病院勤務
昭和五十年(一九七五年)肝硬変にて逝去
この遺稿集には「三代の歌」「ヨハネ伝第八章注釈補遺」「フク女覚書」「病院街行進曲」「墓標記」の五編が収録されています。「三代の歌」と「フク女覚書」は、中原一族と、母親「フク」について呉郎の視点から書かれています。残り三編は小説でした。
【三代の歌】では、呉郎の祖父母、父母、そして兄弟のことが書かれていますが、その系図は大変に複雑ですので詳細は省きますが、中原一族の宿命とも言える「魂の彷徨性」「狂気性」と共に「いのちの儚さ」が、わたくしを圧倒してきました。また、中也の詩にもあたって、弟の視点で見た中也の生い立ちとの関連、詩人たちへの最期の手紙や詩作品の意味合い、母「フク」が好きだった詩は「冬の長門峡」だったことなど、わたくしの今後の中也詩の読解に大きく影響してくることでしょう。
呉郎は中也の思想を「叙情性」からすべて出発したものであることを指摘しています。これは中也に限ったことではなく、わたくしはむしろ普遍的なことではないのかと思います。また中原家三代に渡る「含羞=はじらい」を中也が受け継いだとも書いています。それは「田舎馬が物に驚く」ような「なま」な感覚でむしろ「照れ」に近いもののようです。
【フク女覚書】は、その「儚いいのち」の哀しみをすべて背負って、九十歳を超えるまでしっかりと生きられた母上の生涯が見事に書かれていました。「フク」は大変向学心もあり、とても愛情深い方だったように思いますが、残念なことに狂気と夭逝から中也を救うことはできなかったようです。
【ヨハネ伝第八章注釈補遺】は、中原呉郎自身の解釈による「ヨハネ伝」で、一人の娼婦を主人公にした一編の小説の形となっています。
【病院街行進曲】【墓標記】の二篇の小説は、中原呉郎自身の自伝のようなものであり、中原呉郎の生き方の表明に似たものだと思われます。前者が「地上の医者」ならば、後者は「海上の医者」と言えるかもしれません。この二篇に共通していることは、女性を愛すること、家族を持つことを呉郎自身がどれほどに恐れたか、ということです。その根底にあるものは前記の「魂の彷徨性」のようでした。
現実の中原呉郎は結婚はしましたが、「子供を持つこと」はありませんでした。それはどうやら中原一族の「狂気」を恐れてのことだったようです。
【墓標記】の方では、船は「海上の牢獄」だと書き、孤独と閉鎖性のなかで心を病む者が多く、海に出ることは決して開放ではないことに気付かされます。ペルシャ湾の嵐の折の描写では「全員が同一条件に立ち、過去と隣人との思いから断絶されて、死の恐怖に襲われる時、西川(主人公)は不思議な心のやすらぎを感じていた。身を痛めつけることが、せめて生きるしるしのように思われた。」と書かれてありました。
以上は、「山椒」同人によってこの一冊に収められた作品のみで、それ以前の同人誌「山椒」に掲載された作品、のちに単行本となった作品、奥様の手による遺稿集などもありますので、さらに新しい発見はあると思います。最後に、これを書くにあたり、さまざまな情報を下さって、わたくしのこの一冊の読み解きを支えて下さったF氏に深く感謝致します。ありがとうございました。
昭和五十年(一九七五年)刊
Oct 28, 2006
杉田久女随筆集
杉田久女(一八九〇年「明治二十三年」~一九四六年「昭和二十一年」)は、一九〇九年、十九歳で美術教師の杉田宇内へ嫁す。一九一七年、高浜虚子主宰の句誌「ホトトギス」が女性俳人輩出のために設けた投稿欄「台所雑詠」に五句が掲載され、それが俳人としての出発点となる。
久女の虚子への尊敬と恋情、病苦、夫の久女への抑圧による俳人と主婦との間の葛藤と苦悶、虚子からの破門、などなど話題の多い俳人ではありましたが、それが「心の病」であるのか、久女本来の情熱的な性格によるものかは、解明されていません。しかし随筆を読むと、生まれた土地、父上の仕事の関係で移り住んだ土地が、すべて南国的風土だったことが、久女の性格に大きく影響しているのではないかと思われます。
常夏の碧き潮あわびそだつ
南国の五月はたのし花朱欒(ザボン)
歯茎かゆく乳首かむ子や花曇
足袋つぐやノラともならず教師妻
病める手の爪美くしや秋海棠
またこの随筆集は、久女の長女「石昌子」によって編纂されていますので、ここに全体像を見ることは、少し無理があるのではないかとも思えます。久女の随筆、俳句の執筆活動は、このような環境にありながら、かなり多いのです。
この随筆集と並べてみたい一冊があります。それは中村汀女の「をんなの四季―昭和三十一年・朝日新聞社刊」、汀女書き下ろしの随筆集です。汀女は明治三十三年(一九〇〇年)生まれ。熊本第一高女卒。昭和六十三年(一九八八年)没。久女と同じく、「ホトトギス」の「台所雑詠」から誕生した俳人の一人です。
この本のなかには、句会に出席してもいつも途中で抜け出して急いで帰宅する汀女がいる。それに不満や無念を抱きながらも、家族の夕餉を整えられたことに安堵する彼女もいる。また幼い子供が重い病にかかり、病院で手厚い治療を受けている最中、罪の意識にかられながらも、それを書かずにはいられない汀女がいる。静かな病室では鉛筆の音さえ響くのだった。
それにしても、その時代とはいえ「台所雑詠」という言葉には、やはりわたくしには抵抗がありました。久女も随筆のなかで、男性俳人からの侮蔑の言葉に対して、女性俳人の感性の柔軟性、言葉のよき器であることを書いています。と同時にやはりかなり個性の強い女性俳人だったことは確かなようです。
虚子留守の鎌倉に来て春惜む
張りとほす女の意地や藍ゆかた
虚子ぎらひかな女嫌いのひとへ帯
蝶追うて春山深く迷ひけり
花衣ぬぐやまつわる紐いろいろ
谺して山ほととぎすほしいまま
(二〇〇三年・講談社文芸文庫)
Oct 21, 2006
筑波根物語 水上勉
この藤の花は「横瀬夜雨」最期の日に幻覚として見た花です。
『ちらちらと雪が降りはじめた。常陸にはめずらしいことであった。多喜は夜雨に雪をみせてやろうと思って縁先の障子をあけた。
「きれいな藤の花だな」
と夜雨は言った。どこにそんな花が咲いているのだろう。降りしきる雪片が空に舞うばかりで・・・・・・』
これは水上勉が長い時間をかけて書いた、明治中期から大正全期に活躍した詩人「横瀬夜雨」の評伝小説です。「横瀬夜雨」は明治十一年元旦に、筑波山のふもとに近い大宝村(現・下妻市)の素封家に生まれましたが、四歳から「くる病」にかかり、生涯を不自由な身で生きることになりました。本名は「虎寿」。十八歳で詩人としてのスタートをきりましたが、彼の作品に最初に注目したのは「河井酔茗」でした。
「河井酔茗」は、新興詩壇「文庫派」の主唱者であり、彼のもとに集まった青年詩人は、伊良子清白、小島烏水、滝沢秋暁、千葉亀雄、島木赤彦、五十嵐白蓮、鮫島紫紅、窪田空穂、水野茶丹、一色醒川、清水橘村、山村暮鳥、そののち沢村胡夷、北原白秋、人見東明、長田秀雄、さらに有本芳水、三木露風、萩原朔太郎と続く。
「横瀬夜雨」は不自由な身で美しい恋の詩を書き、女性詩壇の選者にもなったことから、女性詩人からの注目を集めることになりました。「文通」という言葉が生き生きとしていた時代のこと、彼の不遇とともにある美しい詩から、まだ見ぬ詩人同士の恋はまたたくまにはじまり、女性たちは「横瀬夜雨」の看とり女を願って結婚や同棲へと進むのでしたが、どれもすぐに破局を迎えました。彼の現実はあまりにも過酷であり、彼の住む村落が暗い風土だったこともあるのでしょう。
稲架(はざ)解くや雲またほぐれかつむすび 木下夕爾
その一人「山田邦子」は信州、函館などで暮したせいか、大宝村の印象はとても重苦しかったようだ。「ここにも信州でみられる稲干しの架木(はさ)はなく、ところどころにポプラがたっているだけで、ただののっぺらぼうに見えるのだった。邦子は不安をおぼえはじめた。」とある。
大正六年六月三十一日、最後に出会った「小森多喜」と結婚し、生涯をともに過しました。多喜二十歳、夜雨四十歳でした。大正八年二月長女「糸子」、大正十一年次女「百合」をもうける。それまでの女性詩人と比べると、「多喜」だけが一切の打算のない純粋なひたむきな女性詩人だったのだろう思えます。母親のあたたかい愛情に育まれて生きてきた「横瀬夜雨」にとって、最もふさわしい女性でした。
水上勉はなぜ「横瀬夜雨」に魅せられたのでしょうか?歩くことすらできない人間が紡ぎ出す美しい詩語の根源に引き寄せられたのでしょう。それにしましても、この本を読んでわたくしが一番驚いたことは、「言葉がこんなにも生きていた。」「言葉がこんなにも人の心を動かした。」ということです。わたくしたちはこんなにも「言葉の力」を信じて、詩を書き、手紙を書いてきたのでしょうか?
(二〇〇六年・河出書房新社刊)
Oct 15, 2006
カポーティ

監督=ベネット・ミラー
脚本&製作総指揮=ダン・ファターマン
主演=フィリップ・シーモア・ホフマン
これはほとんど実話にもとずく映画だとみていいのかもしれません。「遠い声、遠い部屋」「ティファニーで朝食を」などを書いて、「早熟の天才」と言われたアメリカの小説家「カポーティ(1924~1984)」は、小説の新しい素材として、一九五九年十一月十五日、カンザス州ホルカムで起きた「クラッター家の家族四人惨殺事件」のニュースに注目する。 逮捕された犯人は若者二人であり「死刑」が決まった。
しかしカポーティはその二人を生かしておいて最後まで徹底した取材を行うために、別の弁護士をたてて裁判を引き伸ばし、二人の刑務所の面会人リストに自分の名前を入れておくように説得し、さらに自由にいつでも二人に面会できるように刑務所長まで買収するのだった。
こうして、カポーティの徹底した取材が始まり、二人の犯人と作家との対話が繰りかえされる。その間にこの三人の間には疑念とともに、深い友情に似たものも育ってゆく。しかし小説は着々と書きすすめられて、最終章の「死刑」を書く時期になっても、彼らの死刑判決は決まらなかった。現実の死刑判決がついに執行される時、カポーティは涙を流しながら立ち会った。その小説「冷血」によってカポーティの名は一気にアカデミックなものに高まる。それはカポーティの最後の名声でもあったのだが。。。
作家であれ、殺人犯であれ、幼少期に親から心に受けた傷は同質のものだった。耐え切れないほどの孤独と恐怖、あるいは貧しさなど。「冷血」は一体誰だったのか?フィリップ・シーモア・ホフマンは「天才」「ホモ」「アル中」「ヤク中」というスキャンダラスな作家「カポーティ」を見事に演じていました。彼はアカデミー賞主演男優賞を受けています。
秋晴れの日の午後、日比谷シャンテ・シネで観ましたが、死刑現場は目をつむっていて、観ていませんでした。その日は「十三日の金曜日」。
「クラッター家」は広大な小麦畑のなかに、ぽつんとある白い家でした。その風景は過日に観た映画「ローズ・イン・タイドランド」にも見た風景。日本の田園風景では絶対にありえない風景、そして孤立の風景でした。
Oct 14, 2006
「待つ」ということ 鷲田清一
アンリ・ド・ブラーケレール (Henri de Braekeleer) 「窓辺の男」
臨床哲学者鷲田清一のおだやかな論理展開は「待つ」ことの抱いているものがいかに広く、深いものであったかを改めて考えさせられました。人生のなかで「待つ」ことはたくさんありました。おそらくこれからもあるのでしょう。そしてその「待ち方」もそれぞれに異なる形となっているのでしょう。第一章の「焦れ」の最後にはすでにこの本全体の「予言」のような一節が書かれてありました。
『わたしたちがおそらくは本書の最後まで引きずることになるであろう事態、つまり、待つことの放棄が〈待つ〉の最後のかたちであるというのは、たぶんそういうことである。』
この本ではさまざまな「待つ」ということの引用が紹介されていましたが、特にこころに残ったのは石原吉郎の「海を流れる川」、フランクルの「夜と霧」、太宰治の「走れメロス」、「小次郎を待たせた武蔵」、そしてサミュエル・ベケットの「ゴドーを待ちながら」などでした。こうした例を辿りながら、著者は丹念に「待つ」の多様性あるいはその意味をみつけようとしているようでした。
一冊の本を読む過程で、必ず一度は訪れる「疲労」があります。それは一つのテーマがとりとめもなく、さまざなな方向に拡散していき、そこをわたくしが彷徨う時です。そこを抜けて、どうやら著者の方向性が一筋の光となって見えてきたとき、その「疲労」は「読書の歓び」に変わります。多分そういう道筋を辿れた本が、わたくしにとって「よき本」ということになるのでしょう。その『光』となったものはたとえばこのような一節でした。
『何らかの到来を待つといういとなみは、結局、待つ者が待つことそのことを放棄したところからしかはじまらない。待つことを放棄することがそれでも待つことにつながるのは、そこに未知の事態へのなんらかの〈開け〉があるからである。』
『〈待つ〉のその時間に発酵した何か、ついに待ちぼうけをくらうだけに終わっても、それによって待ちびとは、〈意味〉を超えた場所に出る、その可能性にふれたはずだ。』
「待つこと」とあなたはいった。
わずかな拒否でもこわれてゆくものがあるから
しずかに「はい」と応える。
冬の空に吸い込まれていった対話。
(詩集「空白期」の「残像」より抜粋。)
(二〇〇六年・角川書店・角川選書)
Oct 08, 2006
バレンタイン 柴田元幸
柴田元幸はアメリカ文学の教授であり、翻訳者でもあるのですが、この本はエッセーと掌編小説(あるいは散文詩?)との中間のような十四編の作品が収められています。わたくしには短編集や箴言集というのは「読書」に疲れた時の回復薬のようなものです。しかし、このお薬の効き目はどうだったのだろうか?「ない。」とも「ある。」とも言えない。むしろ気付かなかった心の病状がうっすらと診えてしまったような感覚でした。多分それはわたくしのかかりつけのドクターにはわからないし、わたくしが自覚するしかないことですが。
この本は「バレンタイン」に始まって「ホワイトディー」に終わるのですが、読み終わってから、ふいに「記憶の胡桃のようだな。」と思いました。さらに「バレンタイン・チョコレート」を贈った男友達から「ホワイトディ・キャンディー」がずっと届かないままで、その男友達がこの世の人ではないような予感がして、最後には、それがすべて当ってしまって、ちょっとたじろいだ気持でした。
「胡桃」を割ると、そこには小さな記憶の山河があります。遠い時間の出来事、死者、幽霊、古い家、若かった父母や兄弟など、時には傍らにいるはずの人間の不在など。。。たった一人の人間は時間を彷徨いながら、記憶を辿りながら、果てしない物語の旅をして、そして最後は「今」すら失って、途方に暮れている。帰る場所はわかっていても、そこになかなか辿り着けない「心の足」のような奇妙な生き物でした。深夜や明け方にふいに目覚めて「ああ。夢だったのね。」と思うような物語たちでした。
(二〇〇六年・新書館刊)
Oct 03, 2006
寺山修司・過激なる疾走 高取英
これは、かつては寺山修司主宰「天井桟敷」のスタッフであり、今は「月蝕歌劇団」を率い る劇作家「高取英」の書いた「寺山修司の評伝」です。高取英の著書にあたるのはこの本が初 めてですので、言っていいのかどうか迷うところですが、他者の引用文があまりにも多いので 、わたくしのような読者は苦しめられました。書かれている一文が著者自身のものなのか、寺 山修司の言葉なのか、他者(十数名いる。)の引用なのか時々確認し直しながら読みました。 引用はほとんど「反論」ではなく「証言」として用いられていますので、迷子の読者にはなら ずにすみましたし、我が「寺山修司」の夢をぶち壊すものでなかったことにも感謝します。おそらく高取英の寺山修司との距離のとり方が近すぎたのではないでしょうか?
寺山修司の作品のなかでは、母親が幾度も殺されています。しかし彼には実母と養母がいる のですが、その双方から豊かな愛を受けています。それが彼の早熟で多才な活動に、血を注い だと思われます。これは私見ですが、「愛された記憶」がいかに一個の人間を豊かに実らせる ものであるのか、ということの一つの好例だとも言えるでしょう。
ヒットラーを「ゲルマンの血の純潔という夢のための詩的行為の人」と言い、またはトロツ キスト、反革命と言われた戯曲「渇いた湖」のなかの主人公の台詞「デモに行く奴はみんな豚 だ。豚は汗かいて体こすりあうのが好きだからな。」から、前記の考えを否定しなくてはなら ないとも思いません。
寺山修司の純粋性や愛の表現が「殺人者」「テロリスト」「叙情」「過激性」「エロス」な どなどに分かれてゆく時、その分かれ道には何があったのでしょうか?荒野のような広さと多 様な世界を抱いていた人だったと改めて思います。この本の結びの言葉は寺山修司のエッセー のなかから、このように書かれています。彼は父親にはならなかった。
『私は、私自身の父になることで、せい一杯だったのである。』
読み続けるうちに次第に疲労感が訪れてきました。寺山修司の「生き急ぎ」の人生に、わた くし本来の「ノロマ性」が追いつけなくなってきたのでしょう。
「家出のすすめ」が書かれた時期は、改めて確認してみますと、わたくしが「家を出る」こ とを意識し始めた時期とほぼ同じ時期だったようです。わたくしが思春期や青春期に寺山修司 を意識しながら生きたわけではないのですが、寺山修司の後追いのようにして、社会状況を見 つめて生きてきたのだと改めて思いました。
失ひし言葉かへさむ青空のつめたき小鳥撃ち落とすごと 寺山修司
落下する白い小鳥が置いてくる秋空のすみの青い空白 昭子
(二〇〇六年・平凡社新書)
Sep 26, 2006
天才の栄光と挫折・数学者列伝 藤原正彦
ここには九人の数学者が取り上げられています。まずその数学者の生きた時代と国名を表記してみましょう。
アイザック・ニュートン(一六四二年~一七二七年)・イギリス
関孝和(一六三九年?~一七〇八年)・日本
エヴァリスト・ガロア(一八一一年~一八三二年)・フランス
ウイリアム・ロウアン・ハミルトン(一八〇五年~一八六五年)・アイルランド
ソーニャ・コワレフスカヤ(一八五〇年~一八九一年)ロシア・・・ストックホルム(スェーデン)
シュリニヴァーサ・ラマヌジャン(一八八七年~一九二〇年)・南インド・・・イギリス
アラン・チューリング(一九一二年=一九五四年)・イギリス
ヘルマン・ワイル(一八八五年~一九五五年)・ドイツ・・・アメリカ
アンドリュー・ワイルズ(一九五三年~)・イギリス
この著書は上記の数学者の短い評伝でもありますが、藤原正彦自身がこの数学者たちの足跡を訪ね、関係者に出会う旅の紀行文ともなっています。どの時代の数学者の生涯のなかにも共通して感じられることは、研究にかけた尋常ではない時間の凝縮でした。
まず、アイザック・ニュートンや関孝和の時代の数学は、天文学、暦学、哲学、宗教学、政治学、経済学、(日本で言えば陰陽学も加わります。)などの広範囲な世界を内包していたのでした。「栄光と挫折」というタイトル通りに、数学者も人間・・・嫉妬、競争の坩堝のなかで苦しみ、さらにその時代の権力者の寵愛を受けるか否かで学者の運命は大きく変わります。学者の弛みない研究生活を見る緊張感と同時に、学者と権力が手を結ぶという怖さもありました。しかし藤原正彦は、その彼等の不遇な部分に光を当てようとしているかのようでした。
時代が変われば、エヴァリスト・ガロアのように一七八九年のフランス革命後の混乱期にあって、家族ともども思想的に困難な時代を生きなくてはならないこともあり、学者としては大変不遇でした。あるいはウイリアム・ロウアン・ハミルトンのように詩人(ワーズワースとの出会いで、詩は断念。)ということもあったのでした。ガロアの短い生涯の最後の言葉はあまりにもいたましい。
『私を忘れないでくれ。祖国が私を記憶するほど、運命は自分に充分な時間を与えてくれなかったのだから。君達の友として私は死ぬ。』
たった一人女性数学者としてソーニャ・コワレフスカヤが登場する。数学と文学とを心のなかに共存させて、美貌と知性、母性、そして大変に愛された女性であったというが、反面「絶対」を求めずにはいられない女性として生涯孤独な魂を抱いていたとも。。ドフトエフスキーの「罪と罰」は、ソーニャとその姉アニュータ(作家)との出会いののちに書かれたものだそうだ。
南インドの数学者シュリニヴァーサ・ラマヌジャンは、貧しい事務員で教育も満足に受けていなかった。彼の研究を最初に認めたのはイギリス、ケンブリッジ大学のハーディーでした。ヒンドゥー教の戒律と数学との狭間で苦しみながらも、ラマヌジャンはケンブリッジにおもむき、ハーディーと共に、研究する幸福な時間もありました。三十二年の短い生涯で、彼の数学研究を助けたのも、苦しめたものも南インドの土着の宗教だったようだ。
アラン・チューリングの師、ケンブリッジ大学のハーディー教授の一九四〇年のこの言葉は、皮肉にも数学の歴史の転換期を予言してしまったようだった。この本を時代を追って読みながら、わたくしが恐れつづけたことはここから始まったと思いました。
『真の数学者による真の数学は役に立たない。科学は戦争など悪にも役立つが、純粋数学は安全である。戦争に役たたせる道は見出されていないし、今後も長い年月、見出されるとは思えない。』
しかし、チューリングをはじめとするイギリスの数学者たちは、一九三九年戦争勃発とともに、ドイツ軍の「エニグマ」という暗号文解読のために集められることになった。これをさらに発展させられたものが、コンピューター理論の元となった「コロッサス」となる。時代はここまで来てしまった。このとき彼は二五歳。
ヘルマン・ワイルは数学とは、哲学、文学や音楽と同様に精神活動の一環として考える学者だったようだ。一九三三年ヒットラーのユダヤ人追放の時代に、妻のヘラがユダヤ系だったことから、アメリカへ渡ることになった。そのアメリカからワイルは幾多のユダヤ系の学者を救出したが、その結果ドイツのゲッティンゲン大学は瓦解したとも言われている。
戦後日本の数学界はアメリカへの頭脳流出のために、学者の乏しい時代にあったが、そんな時期(一九五三年)に東大に「SSS」という研究集団が立ち上がる。その中心人物が谷山豊と志村五郎であり、二人が取り組んだ研究は一七世紀後半の「フェルマーの予想」の証明であった。
一九六三年、アンドリュー・ワイルズ十歳の時に図書館で出会った「フェルマーの予想」の「最後の問題」の証明が少年の夢となったのだった。ここですでに見えない架け橋がかかっていたのだった。谷村豊は自死するが、志村五郎は続行する。
そして一九九四年ワイルは、ケンブリッジ大学講師リチャード・ティラーの協力により、「谷村・志村予想」の証明を成し遂げた。約四十年の歳月が経過していた。
数学者藤原正彦が魅せられた数学者の紹介はここで終わる。
この本を一緒に読んでくれた亡き父よ。ありがとう。
(二〇〇二年・新潮選書)
Sep 19, 2006
犬のしっぽを撫でながら 小川洋子
(photo by KIKI.....u u u)
この六一編のエッセー集のはじめには、小説「博士の愛した数式」の書かれた動機について記されています。そのきっかけは数学者藤原正彦の「天才の栄光と挫折・数学者列伝」にあったとのことです。たしかに藤原正彦の文章は(「国家の品格」以外!)明確で魅力的です。数学の苦手だった小川洋子は数学の美しさ、ゆるぎない正しさ、果てしのなさに惹かれていったようですね。
そして、その小説に出てくる博士が愛した少年「√」の誕生日を「九月十一日」としたこと、その誕生日のお祝いの夜にバースディー・ケーキが壊れたことの理由もこのエッセー集で理解しました。それは、小川洋子の作家としての出発点が「アンネ・フランク」だったということとどこかで繋がっているのではないか?という思いが立ち上がったからでした。
また、「√」と小川洋子のご子息が共に「野球少年」であること。タイガース・ファンであることなどのほほえましい繋がりも見えます。また若い日にレース編みを学んだこと、その先生のお宅にはフェルメールの絵「レースを編む女」が飾られていたことから、この博士の美しい数式の比喩として、「レース編み」が何度か登場することにも納得できるものでした。小川洋子の素直なやわらかな(ちょっと夢見がちな・・・)感性をここに感じます。
この小説「博士の愛した数式」の「読売文学賞」と「本屋大賞」の受賞はともかくとして、その他に「日本数学会出版賞」を受賞したということは、上等なジョークのようなお話ではないだろうか?
それから面白かったのは「罵られ箱」という二ページ弱のエッセーです。ささいな他者の冷酷な言動によって、小川洋子はすぐに落ち込むらしい。そんな時にこの箱を開ける。これまでの人生のなかで受けたさまざまな非難の言葉と心静かに対面して、またその箱に収めるのだとか。その箱は詰めても詰めても満杯にならないのだとか。。。
わたくしの「罵られ箱」の中身は、小川洋子より年長故大分増えましたが、さらにこの秋くらいには増えることでしょう。いくらでも入ると言う小川洋子のこの言葉を信じてみよう(^^)。
エッセーはその他は省いてここでちょっと笑い話。。。「曲がった鼻」という短いエッセーのなかで、耳鼻咽喉科の検査に鼻から内視鏡を入れて、咽喉を調べる方法があるのですが、その時小川洋子は貧血を起してしまって、ドクターから「君の鼻は曲がっているねえ。」と言われたそうです。わたくしは同じ場面でドクターから「鼻の穴が小さいですねえ。」と言われたことを思い出してしまって、おもわずクスクスクス。。。鼻呼吸の上手い人間ほど集中力があるそうな。。。ふうむ。深く納得しました。
(二〇〇六年・集英社刊)
Sep 16, 2006
良寛 吉本隆明
吉本隆明がこの本で何を伝えたかったのかはとても明確でした。そして吉本が描きだした「良寛」はさらに明確でした。良寛の思想の根底にあったものは、曹洞宗円覚寺の国仙、道元の「正法眼蔵」、老子と荘子であることは、水上勉の「良寛」の感想文の折にすでに書きました。この本のなかでは「仏教者良寛」について、吉本と水上の対談も収録されていますが、水上は自らの境涯を重ねながら語り、吉本は「思想」「詩文」「書」を中心として追いながら、良寛の精神の筋道を語ろうとしていました。このお二人の対談はこの本のなかで光を放っていたように思いました。お二人の「良寛」を読んだことの幸福を感じます。
吉本は良寛の思想を「アジア的」と言っています。現代を生きるわたくしたちは、良きにつけ悪しきにつけ、すでに「欧米的」思想を取り込んでしまっているのです。その精神構造で読んでいきますと、吉本の解説する「アジア的」思想が、とてもなつかしく思われてくるのでした。そこに国仙が良寛を評して言った「大愚」と、良寛の天性の性格の「悲劇性」とが錯綜して、良寛の実像に近づくのはとても困難なことだったと思います。
まず極私的に「愛語」に触れてみたいと思います。これは道元の「正法眼蔵」のなかにある「菩提薩捶(吉本の本では土偏に垂と表記。)四摂法=ぼだいさったししょうぼう」には「布施」「愛語」「利行」「同事」がありますが、良寛がもっとも拘ったのは「愛語」だそうです。従って吉本もそれらのいくつかを自らにてらして考えています。素直な方ですね(^^)。さらにその一つにわたくしも拘ってみました。それは・・・・・・
『かりそめに童にものをいいつけてはいけない。』
・・・・・・と言うものです。大人がやるべきことを子供に代理をやらせてはいけないということです。また「誰それがいけない。」とか「なにがしが悪い。」という大人の勝手な判断を、まだ判断力の育たない子供に押し付けてはいけないということです。不思議なのですが、それを無意識に自分がやってきたということが嬉しかったのでした。
しかし「禁止」は言いました。それは本当の意味での「禁止」ではなく、「禁止」を破る緊張感を子供に感じてもらうためです。「禁止」を言い渡しても、子供は増水した川に行きます。車の絶えない県道を渡って、思いがけない程に遠方まで行ってしまいます。事故に遭遇します。迷子にもなります。見知らぬ人についていったり、物を受け取ったりします。高い樹に登ります。帰宅した子供の匂いや、顔色や、服や靴の綻びや汚れ具合などからその日の出来事は見えてきますが、夕暮れに無事に帰ったことに安堵しつつ、時には思いがけない通報であわてたり。。。すべてはこどもの「いのち」を守るため、母親がやるべきことは本当にそれだけしかないのです。
・・・・・・おっと。。。自分のことばかり書いてしまいましたが、この「愛語」は、托鉢の途中で子供たちと手まりで遊ぶ良寛の行為に繋がっているのではないかと思わずにはいられません。現代の児童心理学や犯罪心理学を超えてゆく思想ではないかと思います。
良寛の詩文の根底にもやはり「愛語」があったように思います。良寛の詩文はすでに近代の詩歌にまで受け継がれる要素をもっていたのではないでしょうか。この「詩文」と「書」を例にとりながら吉本は、僧として、詩人としての良寛を理解しようと展開しています。この吉本の柔軟な論理展開は美しいものでした。人間の真摯な探求はいつでも美しい。。。
【付記】
この感想を書くにあたり、「道元の「正法眼蔵」のなかにある「菩提薩捶四摂法」について教えて下さった方々にお礼を申し上げます。ありがとうございました。
(一九九二年・春秋社刊)
Sep 10, 2006
テストです。
【菩提薩捶四摂法】↑の文字、テキストで書くと「捶」が拒否されましたが、ここなら大丈夫かな?道元の「正法眼蔵」にあるものです。「布施」「愛語」「利行」「同事」の四つだそうです。それにしても正確な読み方もわかりませぬ。こまった。。。「ぼだいさったよんせっぽう」でいいのかなー?
「捶」は本当には「つちへん」ですが。さらにテスト。。
埵
この↑文字は桐田さんのマックから見ると、文字化けするそうです。あちゃー。。
Sep 07, 2006
贈答の詩③ 清水哲男詩集「黄燐と投げ縄」への挨拶詩
清水哲男さんは、この詩集以前に「夕日に赤い帆」「緑の小函」と二冊の詩集が出版されています。「赤」「青」「黄」と交通信号三部作だそうです。ふうむ。「止まれ。」「渡れ。」「注意せよ。渡れる自信ある者は渡れ。」ということになりますね。詩集をぱらぱらとめくりながら読んでいるうちに、「何か書けそうだな。」という気持が動きました。黄色の信号が点滅しているうちに、ちょっと頑張って渡ってみます。作品のなかには、この詩集のなかの言葉をお借りしていますことを明記しておきます。哲男さんからは「こういうケースは高田さんのオリジナルなのですから。」という許可を頂きました。
兄の記憶
その先の角を曲がれば
兄の背中に追いつけるだろうか
そんなあわい想いをかかえながら
黄燐の匂う道を辿る
曲がり角にさしかかって
ふっとわたくしは想う
夢のなかで
やさしく小さな歌を歌ったのは誰だったの?
数十年生きても
白く笑う癖は直らない
戻ることのできない夢が
兄の背中に今もおぶわれているわけではない・・・・・・
生きてきたことに間違いはなかった
死ぬことはきっと間違いなくできる
あの夕暮れの歩道橋で
手を振っている幻の人だけが知っていること
福生セントラルの暗闇に
今もボールを握ったまま
佇んでいる少年の兄よ
わたくしはその時
金網におでこを貼り付けていた
眼ばかり大きな少女だった
曲がり角に佇んで
電柱のかげに隠れて
空の魚や
老いた猫や
巨きな父上や
兄の背中をみつめている
そのわずかな距離の果てしなさ
まだ、その道に行けない
頑迷なわたくしの足元では
言葉の叢が
一斉に風に騒いでいるから・・・・・・
(二〇〇五年・書肆山田刊)
Sep 03, 2006
百人一首
我がごちゃごちゃ書棚には、たぶん五冊くらいの「百人一首」の解説本があるのだろうが、とりあえず参考にしているのは、吉原幸子著「百人一首・一九八二年・平凡社刊」と、白洲正子著「私の百人一首(愛蔵版)・二〇〇五年・新潮社刊」の二冊である。白洲正子の本は一九七六年新潮選書として書き下ろされ、その後文庫版となり、それを底本とした愛蔵版です。
吉原幸子の本では、かなり深入りした解釈とともに、吉原幸子自身が書いた解釈口語詩も添えられている点がユニークな試みです。そこには彼女自身の少女期の百人一首遊びへの郷愁も加担しているようでした。反面、白洲正子の本では、歌そのものの解釈には深入りせずに、歴史的状況を踏まえながら、距離をはかりつつ書かれている。白洲正子は吉原幸子とは異なる視点で「何故、百人一首がこれほどに人気があるのか?」という問いかけから出発しているようです。
とりあえずこの二冊をテキストとして、吉原幸子の後追いのつもりで、一首に対して五行の口語詩を書く試みを始めてみました。一人では寂しいので相方をお願いして二人で交互に書いて、連詩のような形にしています。道のりは遠い。完結するかどうか。いや完結させたい。それができたとしても、どうということはないのですが、わたしには楽しい遊び、百人一首の丁寧な再読という収穫もあるのです。
Aug 30, 2006
博士の愛した数式 小川洋子
映画を観た後で、原作にあたるという体験はひさしぶりなことだった。困るのは小説のなかの登場人物と映画の配役とが奇妙なかたちでダブったり、ブレたりすることだ。それによってなかなか人物像が結べないままに読み終えたという感はわずかにあります。 しかし、まず言っておきたいことは、「映画」と「原作」はまったく別物だということです。「原作」が読者のなかで一人歩きはじめるように、「映画」も同じことではないのかな?その「原作」と「映画」との「ズレ」を、わたくしはここで指摘するつもりはまったくないので、今回は「原作」についてのみ書いてゆきます。
ある事故によって、記憶が八十分しか持たないという優れた老数学博士は、記憶からこぼれることのなかった美しい数式にあてはめて、日々を生きている。博士の汚れのない人格はこの数式が見事に浮き彫りにしてゆく。その博士に関わることになった家政婦とその息子「√」、同じ敷地内に住む義理の姉(博士が唯一愛した女性。同じ事故に遭遇して、足が少しだけ不自由です。)たちは、たとえようもない美しい心の経験をすることになる。読む者にとってもそれは同じ経験を共有することになる。
『瞬く星を結んで夜空に星座を描くように、博士の書いた数字と、私の書いた数字が、淀みない一つの流れとなって巡っている様子を目で追い掛けていた。』
『私はページを撫でた。博士の書き記した数式が指先に触れるのを感じた。数式たちが連なり合い、一本の鎖となって足元に長く垂れ下がっていた。私は一段一段、鎖を降りてゆく。風景は消え去り、光は射さず、音さえ届かないが怖くなどない。博士の示した道標は、なにものにも侵されない永遠の正しさを備えていると、よく知っているから。』
『私は神様の手帳の重厚さ、創造主のレース編みの精巧さを思った。どんなに懸命に一日一日たどっていても、ほんの一瞬油断しただけで、次に進むべき手掛かりを見失ってしまう。ゴールだと歓喜した途端、更に複雑な模様が出現する。
博士だっていくつかの、レースの切れ端を手にしたに違いない。そこにはどんな美しい模様が透けて見えるのだろう。博士の記憶に今もそれが刻み込まれていますようにと、私は祈った。』
これらはすべて家政婦の「私」の独白です。十歳の息子とともに、博士との人生における偶然の出会いがもたらしたものの豊かさがここに表れていると思いました。
この小説を書くにあたり、小川洋子は数学者藤原正彦と対談をしているようです。小説のあとに藤原正彦の書いた「解説」から、それがわかりますが、小川洋子は執筆経過報告も藤原にしていたようです。しーかーしー。この数学者の「解説」が美しくないのは何故か?
(新潮文庫・平成十八年八月・十八刷)
Aug 26, 2006
おとこ坂 おんな坂 阿刀田高
この著書は十二話からなる短編集です。毎日新聞日曜版に二〇〇五年四月から二〇〇六年三月まで、五十回に渡って連載されたもののようです。新聞連載という「拘束感」なのだろうか。舞台となる土地は国内のさまざまな地方都市であり、一編づつに詩や小説、伝記などがさりげなくストーリーのなかに挿入されている。ストーリーも時折かすかな驚きをみせるものの、日常的なありふれた人間模様が描きだされている。薄味な短編小説集だ。
しかし、この十二話に共通していることは、大袈裟ではないのだが、人間社会への静かな肯定、あるいは人間(または男女間)へのさりげない信頼のようなものがあるようだ。さらにそこには「いのち」へのささやかな希望や驚き、「運命」と「人生」とのやさしい調和、というものなどが、常にストーリーという川の川底に流れているということだろう。
第七話「生まれ変わり」が、上記のわたくしの感想を集約されたもののように思える。間もなく三十歳になる女性画家が、才能の限界を見定めて、タブローからイラストへの転向を考え出す。しかし彼女の幼いときからの絵の才能を見守っていた叔父は、彼女の誕生日と同じ日に、二十三歳で死んだという大叔父はかなり才能を認められていた画家だったので、その「生まれ変わり」だと言うのだった。
「遠野物語」には柳田国男を蔭で支えて、物語の蒐集に努めた地元の佐々木鏡石がいたように、人生には大きな達成と共に、隣合わせの目立たない達成がある。その鏡石の命日が誕生日だという、作家をあきらめ占い師になった男に出会う。占い師は街角のストーリー・テラーだ。彼は彼女にこのような示唆を与える。
『人生はいろいろですよ。どんなに執念を燃やしても、できないことがある。願ったことのすぐ隣くらいのことができれば満足すべきでしょう。事実、満足できます。そこで充分に自分を燃焼させればいい。』
(二〇〇六年・毎日新聞社刊)
Aug 21, 2006
贈答の詩② 小川三郎詩集「永遠へと続く午後の直中」への挨拶詩
小川さんの詩作品はそれぞれがシュールな物語のワンシーンのようでした。あなたはその物語をみずからの歩幅で歩いてゆく。時には走る、時には落ちる。その言葉には「バネ」のようなものがあって、それは時には粗暴で、時にはやさしかった。
さてさて批評を書けないわたくしは、この詩集の美味しい言葉の素材を頂いて、別のお料理をしてみましょう。「たべてくれるな」と呟いてももう遅いです(^^)。不出来ではございますが、どうぞめしあがれ。。。
【付記】この作品掲載については、小川三郎さんの許可を頂いております。
二度とないものを
あの女の胎内の児は
どうやら翼があるらしい
たまごの殻を破るのか
暗い産道を潜りぬけるのか
その双方の合意がないままに
胎児はずっと不機嫌だった
女が散漫な日々を過している家では
百歳のおんなが死んだ
枕辺に残された人形は不死
限りあるものとそうでないものが
古い家のすみずみまで
強い糸で結ばれている
季節は狂いなく進む
男はまた一年の節々を丹念に死ぬ
そして繰り返される
彼岸花の野原のひろがり
赤鬼の昼寝
そうしてあの胎児は
時を切り裂いて生まれてきたのだった
永遠へと続く午後の直中へ
飛ぶのか
這うのか
歩くのか?
名付けてあげよう
二度とないこの時間を生きるには
愛するものから呼ばれるためには
一つの名前が必要だ
(二〇〇五年。思潮社刊)
Aug 18, 2006
西の魔女が死んだ 梨木香歩
梨木香歩(一九五九年・鹿児島生まれ)、英国に留学、児童文学者のベティ・モーガン・ボーエンに師事。この「西の魔女が死んだ」で日本児童文学者協会新人賞、新美南吉児童文学賞、小学館文学賞を受賞しているようだ。この他にも別の受賞作品を含めての作品がありますがそこは省きます。賞の価値はよくわかりませんが、注目を集めているらしいこの児童文学者「梨木香歩」に初めて触れたことになるのですが、とてもよい本、素直に「好きです。」と言えます。
「西の魔女」とは登校拒否の中学生「まい」の英国人のおばあちゃんです。日本人であるおじいちゃんと結婚して日本に来たのです。「まい」のパパは単身赴任中、ママも仕事をしている。「まい」は一人っ子です。学校に行けなくなった「まい」はおばあちゃんの家で暮らすことになりました。そのおばあちゃんの家と広大な庭、現代社会から距離を置いた自然に即した暮らしぶりは、米国バーモント州で暮らす「ターシャ・テューダー」を思い出す。
おばあちゃんは実は魔女だと言う。「まい」の心の立ち直りはその魔女修行にあるのだが、それは単に健康な規則正しい生活をして、からだを動かして働き、自立した考え方、他者を冒涜しない感性を内部に養うことだった。夜更かしだった「まい」におばあちゃんは、彼女のベッドの柱に「たまねぎ」を吊るして、おまじないを唱えるのだった。よく効いた。
「ナイ、ナイ、スウィーティ」
「まい」には幼い頃から抱えていた不安があった。それは何気ないパパの言葉に始まっていた。「死」についてパパは「最後の最後、何もない。」と言い、「まいが死んでも、生きている人たちは翌日から変わりない生活をするのか?」という問いかけにも、パパは無造作に「そうだよ。」と答える。
かつて小さかったわたくしも、どんなに「死」がこわかったことか。その上、死んだら焼かれるという事実に出合った時には「死なない大人になるか?あるいは大人になるということは、死がこわいものでないと感じることなのか?」と考えて、とりあえず大人になるまでの時間の猶予に望みを託すしかなかった。
それは、時を経てわたくしの子供の問題になった。近所の知りあいの赤ちゃんが死んだ。四歳の息子の友達の弟だったので、息子を連れて葬儀に参列して、小さな柩を見送った。その時の息子は「子供でも死ぬの?」とわたくしを見つめる。「あなたは死なない。」と小声で答えて繋いでいた手を黙って握りなおしただけだった。
おばあちゃんは「まい」に肉体の「死」を超えた「魂」の不滅を教えるのだ。それを「まい」が本当に理解したのは、おばあちゃんとの生活に別れを告げて、パパの赴任先にママと共に移り住み、新しい学校でなんとか暮している時期に、おばあちゃんが突然亡くなった時だった。
ニシノマジョ カラ ヒガシノマジョ ヘ
オバアチャン ノ タマシイ、ダッシュツ、ダイセイコウ
「まい」は「アイ ノウ」と答えた。。。
もう一編「渡りの一日」が収録されているが、それはおばあちゃんの教え通り生きている未来の「まい」の姿かもしれないが。省略。
(二〇〇一年・新潮文庫)
Aug 17, 2006
おとぎ話の忘れ物 小川洋子/文 樋上公実子/絵
この物語の舞台となるキャンディー屋さんの「スワンキャンディー〈湖の雫〉」は有名だが、もっと注目されていることはこの店の奥にある「忘れ物図書館」でした。ここには先々代の放蕩息子が世界中の「忘れ物保管所」から集めた、古びた原稿を立派な装丁でたった一冊づつの本にして置いてあるのでした。その本は今までの「おとぎ話」の外伝のような奇妙なお話になっていたのだった。パロディーと言ってもいいかもしれない。それはとりあえず四話ある。元になっているお話はどなたでもご存知でしょう。
ずきん倶楽部
少女がふとしたことから知り合った人は「ずきん倶楽部」の会長だった。訪問した家にはあらゆる種類の「ずきん」が所せましと置かれていた。その倶楽部会員の最大の催し物のずきん祭りで、会長が誇らしげに披露したものは、おおかみのお腹にいた時に赤ずきんちゃんが被っていたとされる代物だった。ずきんには鉤裂き、おおかみの胃液の匂い。うへ。。。
アリスという名前
アリスと名付けられた少女、アリスは「蟻巣」とも言える。父親はある時アリスに「蟻の巣セット」をプレゼントする。これはわたくしにも懐かしい遊びだ。「セット」などは勿論なかったが、土を入れた瓶の周りを黒い紙でくるみ、土の上にはお砂糖やキャンディーを置いて、数匹の蟻を入れて、ガーゼの蓋をする。やがて蟻は地下道を掘りはじめる。黒い紙をはずせば蟻の地下生活の断面を見ることができるのだった。
しかしアリスの蟻は、ある日覗き込んだアリスの鼻に吸い込まれてしまう。蟻はアリスのからだの中に地下道をどんどん掘り進めてしまう。蟻の不思議な国。こわ。。。
人魚宝石職人の一生
実は男の人魚がいるのだが、彼等は海面から体を出すと死んでしまうので、見た者はいないという。彼は深海の宝石職人。愛する人魚は地上の王子に恋をして、声の代わりに足をもらって地上の女性となるが、悲恋に終わり自殺する。宝石職人はいのちをかけて首飾りを砂浜において死ぬ。王子の妃はそのあまりにも美しい首飾りを見つけて首に飾るが、それは徐々に妃の首を絞めあげて。。。ううう。
愛されすぎた白鳥
深い森の入口に住む一人ぼっちの森番には、定期的に町から生活に必要なものが届けられる。その度に一つかみのキャンディーもあった。ある日一羽の美しい白鳥に出会った森番は、自分の一番の楽しみだったキャンディーを白鳥に与えた。毎日毎日。。。白鳥はキャンディの重みで湖底に沈み、一滴の雫となった。・・・・・・そしてお話は最初に戻る。ぐるぐるぐる。。。
(二〇〇六年・集英社刊)
Aug 15, 2006
贈答の詩① 足立和夫詩集『暗中』への挨拶詩
足立さんの詩集には魅力的な言葉が多々存在していました。その言葉は日常の実感から出発しながら、確かな詩語に手渡されていたと思います。そしてその詩語は読み手のわたくしに正確な重さを持って届けられました。わたくしは詩集評は書けないのですが、この詩集には、なにかを送りたかった。そんな思いからこの「挨拶詩」を書いてみました。この詩のなかには足立さんの詩集『暗中』と『空気のなかの永遠は』にある魅力的な言葉をいっぱい紛れこませてあります。
【付記】この作品掲載については、足立和夫さんの許可を頂いております。
奇妙な孤独
君のなかには時間と実感が混在していて
そのまわりを静かな闇が包んでいる
それはゆっくりと言葉になってゆく
饒舌から沈黙へ
あるいは沈黙から饒舌へ
近づくと
その闇はいつでも溶けそうなのに
そこには昔の人たちの姿が立ち並び
壁面のように君のまわりに立っているのだ
どいてくれないか その闇の番兵たち
わたくしたちは
地下の喫茶店に下りてゆき
地球の芯の真上に腰をおろして
世界を草のように食みながら
やさしい会話を交わすことができる
一五〇年の勤務者と
懐かしい暗黒の街へ出ると
闇はわたくしたちの孤独を新しくして
お酒を酌み交わすのだった
乾杯!生きることはそれに集約されるね
怜悧な星たち
夜の地上はみだらな光を散りばめている
てらてらした草は
たえまなく生えてくる
目的のない潔さ
暗中のなかに見る永遠の帰宅の仮説
わたくしたちは消えてゆきそうな素足から
現実の靴を脱ぎすてて
果てしのない独り言を
睡魔が断つのを待っている
(二〇〇六年。草原詩社発行・星雲社発売)
Aug 12, 2006
幸福論 寺山修司
この本を読むきっかけは、鷲田清一の「死なないでいる理由」に多く引用されていたことによります。寺山修司(一九三五~一九八三年・昭和十年~昭和五八年)はご存知の通り、俳人、歌人、詩人、劇作家、映画監督、エッセイストであり、劇団「天井桟敷」の主宰者であり、座付き作者兼演出家兼プロデューサーと、四八年という短い生涯を駆け抜けた方です。この本の終章ではこう書かれている。これは文庫初版年から推察すると三十代なかばで書かれたものではないだろうか。
『ところで、私は幸福である。幸福ではあるが、世界や現実を享受している訳ではない。むしろ「自己の存在を、その個別的な品性、志向、恣意に適合させ、自己の現在を享受しうる者の幸福」(ヘーゲル「歴史哲学講義」)の否定を通して、べつの快楽を創造することのなかに、新しい幸福論の時の回路を探りつづけているのだ、と言った方がよいかもしれない。』
先に終章を書いてしまったが、はじめには従来のさまざまな「幸福論」は、ほとんど書物のなかで構築されている思想であるという主張。かの有名なお言葉「書を捨てよ、町へ出よう。」に裏打ちされた寺山の現実は、読書は「人生のなんらかの理由によって閉ざされている時の代償経験」あるいは「しばらく人生から、おりているときの愉しみ」だったと。そして「走りながら読む書物はないだろうか?」という寺山らしい発想が生まれたりもする。
しかしながら、この「幸福論」も書物であり、論なのだ。という観点から「アランの幸福論などくそくらえ!」から出発して、寺山がこの書物のなかでエピソードとして取り上げているのは、通り魔的殺人者、監獄の中の人々、ラーメン屋の親父、サラリーマン、場末で性を売る女性たち、障害者、不美人、競馬場の男たちなどなどの姿であり、あるいはその時代の映画(古い女優の名前が出てきてなつかしい。。)、歌謡曲の一節などなのだった。あくまでも人間の当たり前の人生(だからこそ個々には稀有でもある。)にあたりながら寺山は書き進めている。走るように。。。あるいはマイクをつきつけるように。
また、歴史、経済、政治、性、愛、恋、家族などを通しても考察しているのだが、結論などあろうはずはない。寺山は「第二の幸福論」を書くためにこれを書いたかのようだ。しかし「第二」は書かれたのだろうか?わたくしにはわからない。最後に一番気にいった寺山修司の一節を記して終わりとします。
『白雪姫のおかあさんが、鏡を見ながら「この世で一番きれいな人は誰ですか?」と訊ねるような美しいものへのあこがれが、どのように幸福を汚してゆくかは、七人の小人でなくても知っている。』
(昭和四八年初版、平成十七年改版初版、平成十八年改版再版・角川文庫)
Aug 09, 2006
ゲド戦記 Ⅰ 影との戦い アーシュラー・K・ル=グウィン
「ゲド戦記」がアニメ化されて、すでに上映されている。これについていろいろな批判を目にするようになりましたので、気になって原作を改めて読むことにしてみました。これは子供を含めた読者を対象に書かれたファンタジーであり、「指輪物語」、「ナル二ア国物語」と共に三大ファンタジーと言われているらしい。
読みながらどうしても、映画「ハリー・ポッターと賢者の石」と重なってしまうのは、未来の魔法使いの子供たちの心の成長の初期段階を描くという点に共通点があったからかもしれません。しかしあの映画もこの本も、実はこわくてこわくて仕方がなかったと告白しておきます。何故そんなにこわいのか?それはきっとファンタジーだからでしょう。わたくしは霧のような不安に追いかけらながら読んでいるのでした。その上眠れば、またこわい夢ばかりみるというわたくしの単純さに、ほとほとあきれ果てました。時としてファンタジーとは現実よりもこわい世界なのではないだろうか?それでも読んじゃったけど(^^)。。。
舞台となるのは海に点在する「アースシー」という架空の多島界世界である。ハイタカ(後にゲド。)は少年期に伯母からわずかな魔法の力を授かり、それによって彼の住む島が他島からの襲撃から島民を守ったことから、魔法使いとしての旅と学びと冒険の物語は始まる。若さと傲慢さから、魔法使いとして禁じられている、自らの力を超えた魔法を使うことになって、心身を痛め、「影」に追われる恐怖の日々を迎えることとなる。海の旅が多いので不安はさらに深い。その課程でやがてゲドは気付く。
『影から逃げるのをやめて、逆に影を追い始めた時、相手に対するおれのそういう気構えの変化が当の相手に姿形を与えたんだと思う。もっともそれからというもの、こちらの力も奪われなくなったがな。』
人間が心にある「影」を迎えうつものは「光」。その双方を心にいだくことによって、ようやく「賢人」となれるという教訓なのであろう。たやすいことではないのだが。。。さてこれは五巻あるのだが、映画はそれをどこまで原作との折り合いをつけたのだろうか?という興味はおおいにある。この物語はアニメ映画監督ならば、制作意欲をかき立てさせられる魅力を充分にもっていると思う。さて、五巻まで読むとは宣言いたしませぬ(^^)。。。
(一九七六年第一刷・一九八七年第十六刷・清水真砂子訳・岩波書店)
Aug 01, 2006
死なないでいる理由 鷲田清一
この本を読むきっかけは、実はわたくしの詩集「砂嵐」を読んで下さった方のお薦めでした。この詩集に収録されている「冬の火事」のなかには・・・・・・
いま なにごともないように
ここにわたしが生きて在ることが
深い罪であるような冬の午後
・・・・・・という一節があります。これは父母と独り身の姉とを相次いで看取った後に書いた作品でした。ここに書かれた「在る」という言葉に注目されたU氏は、この本のなかに書かれた「ある」と「いる」についての章を読んでみるようにと薦めてくださいました。「ある」は現代語のなかでは「物」について使われる言葉であり、古語では「生きている」「存在する」「住む」「暮らす」など広い意味を持っています。わたくしはどうやらこの「在る」を古語的に使っていたようです。
この「ある」と「いる」との間にあるような現代の言葉の悲しみの距離について、筆者はひとつのエピソードを添えています。苦しんで産み出した赤子が死児だとわかった時に、医師は「ああ、死んでる。」と言った。その「看取る」や「看る」ではなく「見る」ことだけで終わった医師の言葉に、母親は激しい怒りを覚えて、医師の袖口をあらん限りの力でつかまえて「死んでるとはどういうことや。美智子さんにもそう言うんか。」と言ったそうです。
医療機関における「いのち」の尊厳の問題はこれだけではないでしょう。筆者は別の章では、映画「ジョニーは戦場へ行った」にも触れています。戦場で両手両足を失い、胴体と半分壊れてしまった頭部だけとなったジョニーを、医師団は格好の生きる医療実験材料としたのです。ジョニーに感情があることに気付いた看護婦と、唯一動くことの出来る首を動かして頭部で枕を打ってモールス信号で語るジョニーとの心の交流は、やがてジョニーの「殺してほしい」という願いになるのですが、医師団は看護婦の自殺幇助を退けて、ジョニーはたった一人の心の交流者を失い、また医療実験材料となってしまうのでした。
人が生きるということ(つまり、死なずにいるということ)の意味について、筆者は医療現場だけではなくあらゆる方向から文献やエピソードを交えながら考察しています。寺山修司の「幸福論」が多く登場することも興味深いことでした。
人が生きなくてはならないという切実な理由を見失ったかに見える現代社会においては、その「見失った」ということが切実な理由になってしまったかに見えます。それはまだたくさんの未来を抱えている若者にも、人生の大方の役割を終えた大人にも同質のものとしてあるように思えてなりません。人々は生きる意味に渇いているということでしょうか?その意味を問えば「喪失」が応えてくるように思えてなりません。
逆に「何故、人を殺してはいけないのか?」と一個人が問えば、大方の人間は怒りをあらわにすることだろう。ここでは人間の永い歴史は「戦争」という殺戮の歴史だったこと、「殺人」が「正義」だったことすらあったのだということは忘れられているのだ。「生きる理由」ということと同時に「殺してはいけない確かな理由」も問いなおさなくてはならないのでしょう。このような問いかけも答えもあまりにも寂しいものだ。この寂しさからの救済のように、鷲田清一はこう書いている。
『こぼしたミルクを拭ってもらい、便で汚れた肛門をふいてもらい、顎や脇の下、指や脚のあいだを丹念に洗ってもらった経験・・・・・・。そういう「存在の世話」を、いかなる条件も保留もつけずにしてもらった経験が、将来じぶんがどれほど他人を憎むことになろうとも、最後のぎりぎりのところでひとへの〈信頼〉を失わないでいさせてくれる。そういう人生への肯定感がなければ、ひとは苦しみが堆積するなかで、最終的に、死なないでいる理由をもちえないだろうとおもわれる。』
もう、ここだけ読めばいい、とすら思った。学者さんはあらゆる文献やエピソードにあたり、たくさんのことを語って下さいましたが、この珠玉のような文節がこぼれおちた瞬間にすべての知識は息をのんで姿をひそめたように思えてなりません。生意気を申し上げてすみませぬ。
(二〇〇二年・小学館刊)
Jul 23, 2006
遠いうた 拾遺集 石原武 (4)

これを書く前に、すこしだけ日本の「アイヌ」のことに触れておきます。これは石原氏の著書に書かれているものではありません。この著書を拝読しながら、ふっとわたくしが思い出したことなのですが、忘れがちなことですが、日本も当然のことながら単一民族ではない。大和の侵略によって狩猟民族だった「アイヌ」の人々は農耕民族になることを強いられ、アイヌ語から大和語に強制的に変えられ、かれらの神々の風習も影をひそめた時代を過ぎて、「アイヌ」の人々は「先住民族」であったことを裁判で国に認めさせたのだった。このことを忘れないでおきたい。
さて、アメリカに行きます。ここでは主にアメリカが関わったさまざまな戦争に、出兵したさまざまな兵士と、その家族にスポットがあてられています。アメリカの貧富の差の大きさ、その下層から兵士は生まれる。そこに視点をあてながら石原氏のペンは進められています。兵士として戦争に行った人々、殺し合いの代償としてなにがあったのか。負傷し、死者となり、家族は深い悲しみに落ちてゆくだけだ。世界中の母親は戦争で殺される息子を産んだのではないのだ。こうしたおびただしい犠牲者の上にアメリカという巨大な国は成り立っている。
昔からの雨 ボブ・コーマン
今日 昔からの雨が降るだろう 遠い空から
アブラハム・リンカーンが死んだ日に降った
雨のようにきっと白い雨だ
(中略)
マーティン・ルーサー・キングが死んだ日に
降った雨のようにきっと黒い雨だ
(中略)
昔からの雨はひそかな遠い空から降る
アメリカの大地へ 生き残るものたちへ
そしてきらきらアメリカを照らすだろう
アメリカは謎多き国である。
しかし石原氏は、ビリー・コリンズの詩「今日」やヘレン・クイグレスの詩「夕暮」を引用しながら、この章をこのような言葉で結んでいます。
『慎ましくも、美しいアメリカの感性を、私は信頼している。』さらに『アメリカがいかに横暴であっても、その裏側にあるこの懐かしい声のゆえに、どうしても敵になれない。』と。。。
さらに、石原氏は「宗教対立」に触れています。テロリストをテーマとしたパレスチナの映画監督アブ・アサッドの作品「すぐに天国」、ユダヤ移民として、アメリカを彷徨する詩人チャーレス・レズニコフの紹介などに続いて、ちょっとわたくしが愕然となったものは、「ファツワのサッカー」についてであった。これは、イラクでジハード(聖戦)に加わったイスラムのある若い運動選手は、国際的なルールによるサッカー競技を禁ずる「ファツワ」に洗脳されているということでした。彼が信奉するという「ファツワのサッカー」のあらましはちょっと長くなりますので、ここでは紹介できませんが、その「慈悲深い神の名において」と題されたものは十六章にも及ぶものです。これは西欧文明に対する敵意であり、異なる宗教間の埋めがたい深い溝のようでもあります。
また、イギリスのノーベル文学賞を受けた劇作家ハロルド・ピンターの受賞講演は、激しいアメリカ批判だったとも。。。「あとがき」は「石油からイネへ」と題されています。石油への欲望がいかに世界の人々の血を流したことかを、ここに付記されていらっしゃるようでした。この「あとがき」はさらにこの著書のはじまりに書かれた「村」にかえってゆくように思われます。
毎朝送られてくる情報をネットから掬い上げて、生々しい状況と文芸表現の有り様を考えることが日課となったと書かれていらっしゃる石原氏の言葉は、さらに弛まない渉猟を予感させるものでした。ここで四回に分けたわたくしの拙い感想を終わります。
(二〇〇六年・詩画工房刊)
Jul 22, 2006
遠いうた 拾遺集 石原武 (3)
さて四章では、石原氏は方向舵を変えて、渉猟はアイルランドのケルト人の哀歌にむかっていきます。これらはドルイド教からカトリックへ、さらにカトリックとプロテスタントという宗教をからめた民族紛争から生まれたようです。次にはエルサレムの永い怨嗟と報復の歴史(ここでも民族紛争)とそれらに関わる詩にふれて、さらにウクライナ、マケドニア、ルーマニア、そしてアフリカへと進んでゆきます。
その道のりは哀しい歴史とニュースと詩ばかり。。。わたくしの力では書ききれるものではありません。石原氏の弛まぬ渉猟に改めて敬意を表するのみです。作品数が多いので、これが適切かどうか迷うところですが、詩作品の断片をここに記してみましょう。翻訳はおそらく石原氏によるものでしょう。
緑を身につけて デオン・ボウシコール(ケルト)
おお アイルランドの仲間よ、
伝わってくるニュースを聞いたか。
クローバーをアイルランドの土地で育ててはばらぬ
と、法律で決めたそうだ。
聖パトリックの日ももう祝えない。
かれの色はもう消えてしまう。
緑を身につけることを禁じるなんて、
そんな法律があってたまるもんか。
(後略)
デオン・ボウシコールはケルトの血を引く貧しい農民であろうとのことです。聖パトリックは自然崇拝のドルイド教のケルト人にカトリック教を伝え、守護聖人となり、三つ葉のクローバーを精霊の象徴としたことから、「緑」が国の色となったそうです。
殉教者の遺言 ハナン・アワッド(パレスチナの女流詩人)
(前略)
おお エルサレム、あなたの傷は私の傷
私のうた。
忍耐と慰めで武装せよ。
私たちは仇と暴虐に対して
海と砂漠を火に変えた。
私たちの傷が血を流し
大地が渇き、私たちの救済が難儀なとき
私たちはどのように生きていったらいいの。
私たちは屈辱の中の平安より
死を、あるいは監獄の焼けつく鉄格子を求める。
(後略)
大虐殺 October 1966 ウォール・ショインカ(ナイジェリア)
(前略)
ペンキ塗りの船から寄せる波
それらが牧歌的な偽善を嘲る。
私はどんぐりを踏んだ。
殻のどれもが爆発して
まぎれもない頭蓋骨だ。
(中略)
樫が盛んに雨を降らして
死の算数を分からなくする。
離れていく人がズック鞄の埃を払う
秋だ、それを見つめていよう。
(後略)
ウォール・ショインカにこの石原氏の本で再会できたのは嬉しい。わたくしは彼の著書「神話・文学・アフリカ世界(一九九二年・彩流社刊・松田忠徳訳)」を大分前に必死(^^;)で読んでいたのだった。。ウォール・ショインカは反体制運動、独立運動のために、九回の逮捕、投獄、三回の亡命を経験しているノーベル賞詩人である。彼の言葉はとても美しく力強い。たとえばこのような言葉がある。
『神の命令だと言い張る連中、救済のために世界に火を放つ義務があると信じている連中、そういう死の一味と戦う義務が私にはある。かれらがイラクのごたごたした街区にいようが、ホワイトハウスの中にいようが、私は戦う。生のカードを配ってくれる人が、私は好きだ。』
さて、続きは、人種の坩堝「アメリカ」へ行きますが、ここはあんまり書きたくないなぁ(^^;)。。。
Jul 17, 2006
博士の愛した数式
監督・小泉堯史
「数学」と聞くと、アンテナが敏感になるのはおそらくわたくしの父が数学教師だった影響が大きい。久しぶりに気持のやわらかくなる映画だった。映画のなかの時間もゆるやかに進み、微笑みが自然に湧いてくるのだった。一緒に観た娘は祖父を、わたくしは父を思い出していた。父(娘の祖父)はすでにこの世にはいないのだが。。。
シングル・マザーの杏子は、一人息子と生きてゆくために、女性であるが故に最も誇ってもいい仕事「家政婦」として生きている。その新しい仕事先として、もとは高名な数学博士であったが、事故によりそれからの記憶が八十分しか持たないという状況にある博士の家だった。杏子の勤務時間は午前十一時から午後七時まで、それ故に博士と杏子の毎日の出会いは初めての繰返しとなる。
「君の靴のサイズはいくつかね?」「二十四です。」「それは潔い数字、四の階乗だ。」これが毎日午前十一時の玄関での挨拶となる。杏子の誕生日は「二月二十日=二二〇」、博士が博士号をとった時の番号は「二八四」この二つの数字は「除数」を足してゆくと、もとの数字になるという「友愛数」であり、それは「神の計らい」だと博士は喜ぶ。
やがて杏子の息子が一人で母親の帰宅を待っているという現実を知ると、博士は「子供にそんな淋しい思いをさせてはいけない。毎日ここで一緒に夕食を食べよう。」と提案する。息子と対面した博士は彼を「√」と呼ぶことにする。野球少年の「√」と大学時代まで野球をやっていたという共通性とともに、博士と「√」と杏子の三人のほほえましい生活は繰り返される。博士は「√」に数学の楽しさとともに、野球の指導まですることになる。少年の背番号は博士がわすれないように「√」とされた。
「√」とは、どんな数字でも嫌がらずに自分のなかにかくまってやる、実に寛大な記号」だと博士は少年に伝える。この映画は、やがて数学教師となった「√」の回想という形で展開されるのだが、数式とは人生のあらゆることをうつくしい姿に変えてみせる魔法の力を持っていた。いつも書斎にいた父の後姿、その書斎にこもっていた不思議な空気がなつかしい。
原作(同名)・小川洋子・新潮社刊
ローズ・イン・タイドランド

監督・テリー・ギリアム
この映画を観る前にオフィシャル・サイトをのぞいてみましたが、わたくしの想像のなかでは不幸な少女が、心のなかに作り出してゆく「ファンタジー」の世界だろうと受け取っていました。この映画も多分監督のイメージとしては、「ファンタジー」であり「現代のアリス」なのかもしれない。
しかし、わたくしの凡庸な感性では、主人公の少女「ジェライザー・ローズ」が現実で遭遇する「不幸」は度を越えているし、そこから辿ってゆく「ファンタジー」の世界も「ブラック・ファンタジー」としか表現のしようがないのだった。わたくしはひたすら「幸福な奇跡」を待ち望みつつ観ていましたが、全編を通して「救い」がない。隣席にいた見知らぬ女性は最後まで観ずに席を立ったまま戻らなかった。同行者も「あの女性、戻らなかったね。」とポツリと言った。気付いていたのだな、と思った。しかし、最後になってやっとかすかな希望を見たけれど、この「ローズ」の少女期の不幸な記憶は生涯に渡って影を落すことになるだろうと思われる。
こんな時、わたくし自身がとりたてて「賢母」であったとはとても思えないが、無意識に、もう遠くなっているはずの「母」の意識が立ち戻ってきて、子供がこんなに不幸であってはならないと「怒り」すら感じるのであった。少しだけストーリーを記しておきます。
ローズの父親は場末のバンドマン、母親とともに麻薬中毒である。その麻薬注射の手伝いを当たり前のように手馴れた様子で手伝うローズ。母親はそのために突然死する。その母親を置き去りにして、廃屋と化した父親の郷里の家に逃げる。そこでやがて父親も麻薬のために急死するが、ローズはその父親のそばでしばらくは暮している。ローズがいつも離さずに持っていたものは、首だけの人形であり、それを指先につけて「二人分の一人語り」を続けながら、ローズは「美しい大人」にも「勇気ある人間」にもなれるのだったが、不幸は限りなく続いてゆくのだった。
もう、どれくらい落ちたのかしら。 もうじき地球のまんなかあたり・・・・・・
原作・「タイドランド」・ミッチ・カリン・角川書店
Jul 14, 2006
遠いうた 拾遺集 石原武 (2)
一章と二章では、現代の文明社会から遠く隔てられた「村」という存在を再考しつつ、「記憶」や「民族」さらに「シェークスピア」にまで再考を拡大させて、三章の「アメリカ・インディアンの遠いうた」に繋ごうとされているように思われました。この三章に収録された「うた」はこれだけで一冊の単行本になるほどの作品量でした。その「うた」は呪術であり、願い、狩り、戦い、子守唄、恋、レクイエム、生活する人間のさまざまな場面に欠かせない「うた」です。
それらの「うた」にはたくさんの動物たちが登場し、月も星も太陽も、大地も水も石も草木も花もある。アメリカ・インディアンの世界感、死生感には境界がない。そしてすべての存在に「神」が宿っているのでした。
そしてなんとたくさんの部族からの「うた」をすくいあげたことでしょう。さらにシャーマン・アレクシーの短編小説「アリゾナのフィニックスから死んだ親父を連れて」も収められています。研究者石原氏の地道で壮大なお仕事に、わたくしの拙い批評や感想など到底届くものではありませんが、あえて書くのは、(1)で書いたわたくしの「たじろぎ」を書きたいからでしょう。
この「うた」の間には「間奏」と題された石原氏の一編の詩「インディアン・レッドの夜明け」が書かれています。抜粋してみましょう。
(前略)
朝風に瓶が倒れて
飲み残しのワインが床に零れた
赤い地図が広がって朝刊を染めていく
世界はきな臭く
赤い砂漠に狼煙が上がる
砂埃の瓦礫の家々まで零れたワインは届かない
鼻水垂らしたアサッドやマルムドまで
暖かな芋は届かない
私は朝食に蒸かした芋の皮を剥きバターを溶かす
マルムドよ アサッドよ ご免な
せめて丘を下りてくる山羊のご慈悲をと
わたしは清ました顔で朝のお祈りをする
(後略)
さて、私事ですが、「アメリカ・インディアン」に注目したのは、一九八九年元旦の朝日新聞に掲載されたミヒャエル・エンデのエッセー「モモからのメッセージ」でした。 この数年前に、エンデは中米奥地の発掘調査に出かけたチームの報告書を読んでいました。調査団は荷役として屈強で寡黙なインディアンのグループを雇いました。日程表をたてていましたが、彼等は予定以上に早く日程をこなすことに成功しましたが、ふいにインディアンのグループは一斉に座り込み、一歩も先へ進もうとしない。調査団からの賃金の値上げ、叱責、脅しにも応じない。そしてまた突然彼等は歩き出す時が来た。何故か?「歩みが速すぎたので、ゼーレ(魂)が自分に追いつくのを待っていた。」というのだった。
また、エンデの文化人類学者の友人からは、山頂で暮らすインディアンの村の水源は山の麓にある。毎日女性たちは往復一時間の道のりを水を運ぶというお話があった。賢明とは言いがたく、しかし「快適」という誘惑からはいつも遠い暮らしを疑いもなく続けることは、愚かとも言いがたいのではないか? わたくしはその時に、天の運行速度と魂の運行速度とは同じではないのか?という思いにかられて、その彼等の世界から「生きる」ということの根源のようなものに辿り着きたいと思うようになっていました。
さて(3)は「アイルランド」へ行きます。(つづく)
Jul 08, 2006
遠いうた 拾遺集 石原武 (1)
石原武氏は一九三〇年、山梨県甲府うまれ、詩人であり、翻訳者であり、英米文学者です。優れた骨太な詩集もたくさん出版されていらっしゃいますが、わたくしが特に注目したのは、「詩の源郷」「遠いうた・マイノリティーの詩学」などの評論集でした。マイノリティーな詩の発掘に注がれた石原氏の視点は、わたくしが知りたかった多くのことを教えてくださいました。本書はそれらをさらに推し進めて、月刊誌「柵」に六〇回、五年に渡って連載されたものを一冊にまとめたものと思われます。なんと五六〇ページを越えるものですので、本書を手にした時のわたくしはいささかたじろぎました。と同時に石原氏のあのおだやかな表情の裏にかくされた深い情熱と真摯な姿勢を見る思いでした。
青春期の入口あたりで日本の「敗戦」の有り様を見つめ、そしてまた混迷する現代をみつめながら、石原氏の詩魂(こういう言葉が息づいている。)を支えてきたものは、「遠いうた」だったのではないかと想像しています。
ちょっとお話がそれますが、シェークスピアのソネット「ⅩⅤⅠⅠⅠ」の翻訳はたくさんの翻訳家がされていますが、わたくしはこの石原氏の翻訳が一番好きでした。これは「君を夏の一日に譬えようか・二〇〇二年・さきたま出版会刊」という詩に関するエッセー集の一節として登場しています。
君を夏の一日に譬えようか
君はもっと美しくもっと優しい
心ない風が五月の蕾をふるわし
夏のいのちはあまりにも短い
"The Sonnets" No.18
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May
And summer's lease hath all too short a date:
・・・・・・というわけで、この著書はあまりにも膨大ですので、今日は入口だけです。数回に分けてメモのように連載するつもりではおりますが、途中挫折の際にはお許しを。出来うる限りこのご本の石原武氏の「熱」をわたくしの言葉として書いてみたいという思いです。
(二〇〇六年六月・詩画工房刊)
Jul 04, 2006
中原中也 悲しみからはじまる 佐々木幹郎
先月二十四日、佐々木幹郎による「中原中也」の講演と、中原中也と小林秀雄との間にいた女性「長谷川康子」のドキュメンタリー映画「眠れ蜜・脚本=佐々木幹郎・一九七六年制作」の上映が神奈川近代文学館で行われました。その折に、わたしは買わず(汗。。)桐田さんがお求めになったこの本をお借りしました。
これは中原中也の小さな評伝であるとともに、中也が昭和二年~五年頃に書いたのではないかと思われる「小年時」と題された詩の創作ノートを画像で紹介し、ノートに書かれた作品の加筆や書き直し、あるいは棒線で消した部分を佐々木幹郎が丹念にたどりながら、作品の推敲の過程を幾通りもの作品として組み立ててみるという試みがなされています。これは作品論とも言えるものでしょうか。中原中也の言葉の熱が佐々木幹郎をとらえて離さないという感じがありました。
一冊全体の印象は、詩人評伝と詩論というよりも、なんだか考古学者が断片を丹念に繋ぎながら、真実により近づこうとしているようで、ちょっと異質な面白さのある本でした。
評伝としては、すでに知られているであろう長谷川泰子や小林秀雄、富永太郎との関係、その人々が中也の作品に与えた影響などは比較的簡略に書かれていると思いました。また「ランボー」の影響についても同じことが言えるでしょう。鈴木信太郎の文語体訳の「ランボー」の「少年期」は中也の「小年時」に大きく影をおとしています。ちょっぴり皮肉を言えば多くの男性詩人が通常辿る詩法はみずからの少年時代から出発することにあるようですね(^^)。
その住む国は、増上慢の蒼空と緑の野辺、無慙にも....
ランボー「少年期」より
(二〇〇五年・みすず書房刊)
Jun 25, 2006
佐々木幹郎の語る「中原中也」
二十四日、横浜詩人会で行われる定例セミナーとして、今回は佐々木幹郎による「中原中也」の講演と、中原中也と小林秀雄との間にいた女性「長谷川康子」のドキュメンタリー映画「眠れ蜜」の上映(上映時間は約三十分。)という企画であった。場所は神奈川近代文学館。
まず映画の方ですが、この映画は一九七六年、佐々木幹郎脚本によって制作されたもので、その時長谷川康子は七十歳、映画が出来上がった時には七十二歳となっている。康子はその五十年前に「グレタ・ガルボに似た女」という募集にトップで通過した女優ではあったが、その後の活躍の足跡は見出しにくいようだ。
これはまだ二十代だった佐々木幹郎の描き出したかった「康子」だということで、そこから先はあたしの想像力で飛ばなければならない。その手掛かりとして、老いた白く細い指を絶えず拭っている康子。アランフェス協奏曲に合わせて、観客のいない舞台で踊る猫背気味の康子。その踊りはフラメンコに似ているが、これは康子の即興によるものらしい。靴は履いていない。でも素足ではなかった。頭髪は一貫してスカーフで包まれていた。そんなところかな?
長谷川康子が稀有な女性だったとは思わない。金子光晴夫人をちょっと連想したりしたけれど、康子は「創作者」ではない女性としての生涯だった。歴史上、美貌の女性は自らも周囲の人間も波乱に巻き込むという例は多々あるが、そこで括ってしまっても陳腐。「愛し方」なんてことを書き出したら、それこそとりとめがないので、あたしのなかにしまっておく。
次は講演だが、その映画を踏まえながら、中原中也、長谷川康子、小林秀雄を佐々木幹郎が語る。佐々木自身『中原中也 悲しみからはじまる・二〇〇五年九月・みすず書房刊』を出版したばかりだ。この佐々木幹郎の講演(著書もどうやら、そうらしい。未読。)の裏づけとなったものが文献よりも、今まで世に出ることのなかった写真や、手紙、証言などによるという別次元の働きかけによるものが多いようだ。
佐々木幹郎は熱い詩人である。夭逝した詩人「中原中也」をその後の詩人は誰も超えることはできないと断言する。詩人とは「努力」や「学び」ではない、ましてや「賞」や「名声」でもないと。あたりまえである。でも、あたしは「天性」という言葉は信じてるのよ。ただ神様の「天性」と「美貌」の配り方が不平等だっただけよ。ちっこいあたしには神様は「天性」も「美貌」もちっこいものしか下さらなかったのさ。ふん。
Jun 22, 2006
雨の名前 文・高橋順子 写真・佐藤秀明
これは約四五〇種の「雨の名前」が収録されていて、それに短い解説がつけられている。俳句の季語であったり、ある限定された地方だけに使われる名前だったり、季語とは無関係に成立している名前もある。湿度が高く、さらにくっきりと四季のあるこの国ならではの豊かな言葉の文化だと思う。ところどことに詩や短歌や俳句が読めるのも嬉しい。「雨の博物誌」と言いたいような本です。
そういえば著者の高橋順子には「時の雨」という詩集がある。小説家車谷長吉との遅い結婚生活を描いた詩集である。「時雨」は冬の季語。さらに「時雨」がつく「雨の名前」はこの本のなかだけでも二十種類に及ぶ。それは詩集「時の雨」の見せる高橋順子の新しい多面性に似ているようだった。
佐藤秀明の写真も素晴らしいものだ。大仰に構えずさりげない雨の風景を切り取っている。「雨」は本来写真家にとってはマイナス要素だろう。それを逆手に取ったような細やかな視線を感じさせる写真であった。一冊は四季に分けて、さらに「季知らずの雨」と五つの項目に分けられています。
今はちょうど梅雨の季節です。「男梅雨」「女梅雨」という言葉がありました。前者は「快男児」後者は「しとやかさ」に寄せた言葉だと思いますが、さてさて今はどうだろうか?
春の「山蒸(うむし)」。夏の「雨濯(うたく)」などはじめて聞く言葉だった。また夏には「雨乞い」の歌と俳句の紹介がある。これらの歌と俳句は神へ届いたと言われている。
ちはやぶる神もみまさば立ちさはぎ天の戸川の樋口あけたまへ 小野小町
夕立や田を見めぐりの神ならば 其角
秋には「通草腐らし」があって春の「卯の花腐し」と呼応する。冬にはお馴染みの新年の「御降り」、年末の「鬼洗い」などの言葉は今でも心新たな気持になる言葉ですね。
このような本は一回通読して終われない気分になります。これは小川三郎さんにお借りした本なのですが、手元に置きたくて、同じものを注文してしまいました。
(二〇〇一年・小学館刊)
Jun 20, 2006
同人
十八日は雨だった。梅雨の季節とはいえ出掛けるにはあまり嬉しい出来事ではない。この日の午後二時からは高田馬場においてはいつもながらの同人の合評会。その前に桐田さんと西新宿にある「東京オペラシティーアートギャラリー」で最終日の「武満徹Visions in Time展」を観ました。この展覧会のことは後日書くかもしれない。。。今日は「同人」というものの再考みたいなことを、ちょっとメモ。。。遅れてきた同人ですが。。。
詩人という存在そのものがほとんど市民権の持てない世界に棲んで、わずかな人間が「詩」という(お叱りを覚悟で申し上げれば・・・)閉鎖世界にいる。それをさらに細分割したものが「同人」なのだと思う。その小さな世界にいると、お互いの作風や詩論も見えてくる。それが「慣れ」にもなる。「慣れ」は「こわい」。「こわい」は「幽霊」。「幽霊」は「消える」。「消える」は「こわい」のです。
誰に向けて詩を書くのか?わたくしの答えははっきりとしている。たった一人のひとのために。次は見知らぬ読者(出来れば一編の詩も読まなかったひと。)に。三番目は詩の世界に関わっている人々に。。。だからこそ過剰な自作自注は許されない作品でありたい。同人からのわたくしの作品への理解や賞賛はなによりも嬉しいことですが、いつでもそれが「全世界」ではないのだと自戒していたい。反面、当然手厳しい批判もあるのですが、それもまた「全世界」からの批判ではないのだと。。。
Jun 16, 2006
沖で待つ 絲山秋子
この一冊は「勤労感謝の日」「沖で待つ」の二篇の小説が収録されていますが、どちらも三十代半ばを過ぎようとする、取り立ててエリートとも言えない女性の生き方が描かれています。「生きる。」ということは、誰にでもかすかな痛ましさがある。
【勤労感謝の日】
失業保険の期限が残り二ヶ月となった三十六歳の女性「鳥飼恭子」は、ご近所の方の薦めで大安吉日、勤労感謝の日に、お見合いをすることになった。相手の男性は、会社大好き人間の「野辺山清」という。しかし、会話のあまりの馬鹿馬鹿しさに恭子は途中で逃げ出してしまって、渋谷で女友達とお酒を呑み、さらに自宅近くまで帰りながら、見合いに同席した母親と顔を合わせたくないので、近所の飲み屋でまた呑んで帰るというお話である。
人間の生涯なんて、なべて真っ当ではないということなど、この歳になればわかってくる。それにしても、その生涯の中間地点にいるような三十六歳の女性における、先が見えているようで、すべてが未定のような日々を名付ける言葉を、わたくしは見つけることができなかった。。。
【沖で待つ】
ここでの女性主人公「及川」は、大手企業の総合職という現代的で正体不明な(←わたくしの感想です。)仕事に必死で取り組み、転勤命令にもすすんで応じるタイプの女性で、前作の「恭子」とは少し違うようだ。同僚の牧原太(本当に太っているのだった。。。)は、彼女が敬愛していた先輩「珠恵」と結婚するが、「及川」と「太っちゃん」は何故か深い信頼関係で結ばれていたのだった。
お互いにどちらかが先に死んだら、生き残った者が死者のパソコンのハード・ディスクを壊すという約束を取り交わしていた。それはお互いの相手の秘密は秘密のままに葬ることができるという信頼関係があったということだ。「太っちゃん」は単身赴任先の住居であるマンションの玄関を出た途端に、飛び降り自殺者の巻き添えとなって死んでしまう。彼女は即刻その約束を果たした。
その後の彼女は「珠恵」の家を訪れて、「太っちゃん」が「珠恵」に書き送ったという詩(らしきもの。)を読むことになる。それはおそらくパソコンのなかのものだったかもしれない。その詩の一節がこの小説のタイトルとなる「沖で待つ・・・」だった。
空室になったはずの「太っちゃん」の部屋にはまださまよっている彼がいて、二人は「同期」であることの親密さについて語るのだった。夫婦でも、恋人でも築くことのできない親和力によってこの二人は結ばれていたことになる。
(二〇〇六年・文藝春秋社刊)
Jun 13, 2006
不運な女 リチャード・ブローティガン(1935~84)
この著書は、一九八四年にピストル自殺した作家の遺品の中から「完成原稿」として一人娘によって発見されたもの。それは一六〇ページの日本のJMPC社製のノート(一六〇ページ)に、一ページに一行おきに書いて一四行、各ページに書かれた言葉数はおよそ一九〇字~一四〇字。使われたペンは日本パイロット社のBP-Sペン二本、とのことだ。一九九四年に仏訳版、二〇〇〇年に英語版が刊行され、二〇〇五年日本で刊行された。
この本を友人宅の書棚に見つけて手に取った時、その帯分でわたくしは読むことを決めてお借りしてきました。そこにはこう書いてありました。「旅となれば、以前は女たちが、上手に荷物を詰めてくれたものだった。」と。。。
この本を日記や備忘録のように捉えることも可能なことだが、ブローティガン自身の流れたり、滞ったりする時間のなかに浮かんだり、飛び込んだり、沈んだりする現在進行形の出来事と、遠いあるいは近い記憶、または夢想などを繋いでいった歪なチェーン・ストーリーと言ってもいいかもしれない。このノートを書く期間は、その前期も含めて尋常ではない移動(あるいは旅?)の連続でもある。
片方だけの女物の靴が道路に転がっている光景(事故ではなく。)を見つめている時の作者の心の不安定感。あるいは首吊り自殺した「不運な女」を幾度も思い出しながら、それははっきりとした形をなしてこないことへの茫漠感。忘れ去られることを食い止めようとして、ノートは何度もそこへ戻り続けるのだが、形は浮上してこない。マリー・ローランサンの詩「鎮静剤」の一行がふと浮かぶ。
死んだ女より もっと哀れなのは 忘れられた女です。
ひとりの人間が生きている時間の経過のなかで、どのようなことが起こりうるか?そこになんらかの意味があるのか?その最初の意図を変えることなくブローティガンは書き続けたのだと思う。物語の定型をこわした未完の迷路だとしか言いようがない。一六〇ページのノートの最後にわずかな空白を残して終わる。その空白をどこに託したかったのだろうか?この著書を読みながら、癒えない傷口を掌で押さえ続けているような痛ましい感覚がずっと続いていた。そこにはもうかすかな「死」の匂いがしていた。最後はこう結んである。
でも、わたしだって真実、努力はした。
彼の詩集「ロンメル進軍・一九九一年・思潮社刊」からこの一編を記しておきます。
鹿の足跡 (高橋源一郎訳)
美しく
儚げにすすり泣き
激しい愛にもだえ
そして静かに横たわる
降ったばかりの雪の上にしるされた鹿の足跡みたいに
そこは愛する人のかたわら
それでいいのだ!
(二〇〇五年・藤本和子訳・新潮社刊)
Jun 09, 2006
プラド美術館展
七日の午後の上野公園は深緑の季節に入り、噴水ものびやかに天へ向っていました。その風景のなかをゆっくりと歩いて東京都美術館の「プラド美術館展」を観てきました。スペイン絵画の黄金時代といわれた一五七〇年頃から、近代絵画の序章となる一八一〇年頃までの絵画八十一点の展示でした。「エル・グレコ」から「ゴヤ」まどと言えばいいのかな?
宮廷と教会の絵画を中心として黄金時代は築かれて、次第に人々の暮らしや風景などに拡がっていったという道のりといえるのでしょうか?同行者に「何故、スペイン絵画を観たかったの?」と尋ねられましたが、ほとんどお答えはありませぬ。わたくしは単純に宗教画に描かれる天使や幼いイエスやヨハネを観ることが好きなのです。国や描かれた時代、画家の宗教解釈などのさまざまな要素がそこに込められているように思うのです。「聖母マリア」や「十字架を背負うキリスト」「ノアの方舟」などにもそれは言えることかもしれません。今回の展覧会では「ムリーリョ・バルトロメ・エステバン」の描いた「貝殻の子供たち」が好きです。(上の画像です。)制作年は一六七〇年から一六七五年。貝殻で掬った水を幼いイエスがヨハネに飲ませているところ。そばには羊や天使たち。。。
また「ボデゴン」と言われる静物画の精密さには驚かされました。こんな絵の植物百科辞典などがあれば、などと贅沢な夢のような想像をするのは楽しい。
余談ですが、絵画展などでおもしろいのは観ている人々の会話や反応にもあります。毎日通って話題性の高い作品の前に半日くらいいて、それらをテープ(カメラはダメでも、テープなら隠して持ち込めるでせう。)にとったら楽しいエッセーが書けるのではないかと、つまんないことを考えているのでありました。こういうつまんないことを面白がるには当然一人ではつまんない。もっと知的で大馬鹿の同行者が必要です(^^)。「キリストのハンサム度数」なんちゃって。ごめんなさい。。。
Jun 05, 2006
オイスター・ボーイの憂鬱な死 ティム・バートン
ティム・バートンは一九六八年ロスアンゼルス生まれ。ディズニー・スタジオアニメーターとしてスタートし、その後「エド・ウッド」「シザーハンズ」「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」「マーズ・アタック」を発表した映画監督であり、俳優でもあるらしい。多才な方のようだ。わたしは「シザーハンズ」しか観ていないような気がしますが、これはとても深い記憶として残るファンタジー映画でした。
「シザーハンズ」の主人公は限りなく人間に近いロボットでした。しかし手が鋏で出来ていて、その手を人間のような手に取り変える寸前に、彼を作った博士は急死してしまう。それでも彼は町に出て、人々との交流や恋などもあったが、やがてまた深い森のなかの博士の家に独り戻ることになる。それから幾十年クリスマスの夜に降る雪の意味を知っているのは、彼の恋人だけだった。
さて、この本は絵本詩集のようである。絵も詩もティム・バートンのかいたものです。奇妙と言えば奇妙、残酷と言えば残酷、面白いと言えば面白い、哀しいと言えばこれまた大いに哀しい。なんとも表現しがたいのですが、思わず最後まで読み通してしまった。人間のようで人間ではない生き物ばかりが登場しますが、そこに込められたメッセージが黙ってひしめいているようでした。
たとえば表題作の「オイスター・ボーイの憂鬱な死」では、砂浜でプロポーズし、海辺で結婚式を挙げた夫婦の間に産まれた子供は多すぎる手足のついた「オイスター」だった。子供は結局父親に殺されて食べられてしまうのです。あるいはここに挙げたイラストのように「じーっと見る。」ばかりの少女が、その二つの目を休息させるために海の中と砂浜のパラソルの下に置いたとか。。。わたくしの凡々たる感性を大きくはずれているもので、自らの感覚を総動員させた次第でありました。ううむ。大騒ぎ。。。絵本詩集製作中のわたくしとしては、素通りできない本でありました。
(一九九九年・河出書房新社刊)
Jun 03, 2006
ダ・ヴィンチ・コード
監督 ロン・ハワード
過日、桐田さんと吉祥寺に買い物に行って、気まぐれに「夕方からダ・ヴィンチ・コードを観ようか?」ということになった。夕方からの上映時間まで、初夏の気持のいい井の頭公園を散歩。映画館では一階から三階までの階段を二列に並ばされて十分くらい開場時間を待ちましたが、入場制限になるほどのことではなく、ほぼ満席という状況だった。
「ダ・ヴィンチ・コード」の話題性が高いのは何故なのか?という興味はあった。テーマが「イエス・キリスト」の今までの定説を覆すということですから、これはあらゆる面で物議を醸す要素は大きかったのでしょう。過去の歴史のなかでは「宗教戦争」というものが多々あったのですからね。これは大雑把に言えば「イエス・キリスト」は妻帯者だったという新説なのです。定説を守るがために、その子孫たちは次々に歴史から抹殺され続けてきた。その生き延びた末裔とされるのがヒロインのソフィー・ヌヴーだったということ。
ソフィー・ヌヴーの両親は、そのために交通事故に偽装されて殺された。同時に殺されるはずだった彼女は助かった。その幼い彼女を「祖父」だと偽って引き取り育てたのは、ルーブル美術館長のジャック・ソニエールだったが、彼も夜の館内で殺される。ダ・ヴィンチの「ウィトルウィス的人体図」のように。彼の死体の周囲の床や壁には暗号が書かれていた。
フランス司法警察暗号解読官であるソフィー・ヌヴーと、その夜にジャック・ソニエールに会う予定だったハーヴァード大学の宗教象徴学教授ロバート・ラングストンはその殺人現場で会う。そこから二人は殺人者からの逃亡とダ・ヴィンチの絵画「最後の晩餐」や「「モナリザ」や「岩窟の聖母」にかくされた意味の解読とで急テンポに映画は展開してゆく。そのスピード感のために大事なテーマを振り落としてしまいそうな感じがあって不安ばかりがつきまとう。
一番心に残ったのは、キリストの末裔だとされているソフィー・ヌヴーの少女期の両親の事故死からはじまった、自らのルーツ探しでした。ルーツを断ち切られた人間の「果てしのなさ」みたいなものが切ない。「イエス・ キリスト」がマリアの処女受胎によって生まれようが、妻帯者の男であろうが、わたしにはどちらでもいいことだが、今生きているソフィー・ヌヴーが、おだやかにみずからの運命を積極的に生きること、超えることだけだろう。
原作は未読ですが、読むかどうかは未定です。映画と原作の落差はいつでもありえる。
Jun 02, 2006
夜の公園 川上弘美
五月末日、かなり精神的に辛い仕事をなんとかやりすごした。そんなわけで、少し軽い読み物に触れてみたくなった。そこで手にとったのがこの小説でした。読了してからまずは「これは人生の軽い前奏曲にすぎないな。」と、ふっと思った。
ここでの人間関係は三十代半ばの夫婦「リリ」と「幸夫」が軸となっている。この出発点では二人には子供はいない。「リリ」の高校時代からの友人には「春名」がいる。私立の女子高校教師「春名」の恋人は三人、一人は「幸夫」であり、「悟」「遠藤」。「大学受験のための小論文添削」の仕事を一日四時間自宅作業をする「リリ」には「暁」という年下の恋人。「悟」と「暁」は兄弟だったことが物語の途中で判明する。
この近視眼的な人間関係を見ていると、人間の生々しい出会いというものはこの地上では無限に拡がるものではないのだろうと思えてくる。こうした人間世界のなかで、「愛」や「性」や「孤独」が絡みあいながら語られてゆく。この語りはどこに向けられているのだろうか?音のない風や雨のようだった。
「春名」と「悟」の自殺未遂事件。「リリ」の妊娠。父親は「暁」だろう。この事件も嵐のように起こったわけではない。驟雨のようだ。「リリ」は「懐妊」という理由とは関係なく「幸夫」に離婚を申し入れ、独りの生活を得る。この離婚の理由も正体不明。やがて「春名」は三人の男性以外(リリも知らない)と結婚。
「リリ」の出産と「春名」の結婚式がちょうど同時期となる。遠くにいながらこの二人はいつでも共に結ばれていたかのようだった。この二人の友情だけが濃厚な心情として重く心に残るが、女性間の友情はかくあるものかと、女性のわたくしがちょっと驚く。
(二〇〇六年・中央公論社刊)
May 22, 2006
草花の咲く場所
二十一日は詩の合評会でした。久しぶりに快晴、初夏のような一日でした。そこで提出される詩はさまざま、批評の基準の置き方がわからないので、わたくしは、いつでも作者に簡素な質問をして、後はみんなのお話を聞いているだけ。時々「突っ込み」の悪戯はするけれど。。。自作自註を熱心にする書き手、読者に手渡した後では「作品は一人歩きするもの。」という姿勢でいる書き手。おそらくわたくしは後者だろうと思う。
一番判断に困る作品は高名(?)な著書や宗教書の「言葉」を引用する作品である。引用された一節は素晴らしい「言葉」ですが、それが作品を生かしているのかどうか判断に困る。作品がその言葉に依存しながら成り立っているとしたら、それは決してよいこととは思えない。
それから、ある出来事から受ける「感動」や「共鳴」をどのように詩としての言葉に変換できるか?どのように読者に届けるのか?「届かなくてもいい。」というのは詩の書き手として傲慢すぎる。わたくしは好きな詩に出会ったら、その「続きの詩」や「贈答詩」などを書きたいとも思う。
この日の作品では、わたくしが少し前に撮った写真を思い出したのでアップしてみます。これは歩道のアスファルトの隙間、ガードレールの下あたりに長い行列をなして咲いていた「スミレ」です。偶然にもお二人の作品にそれを発見しました。過ぎていった春の記念に。。。
私はガードレールの上に残され
混沌としている
と。
いつかの花が
アスファルトを破って咲いている。
(消去・小川三郎・・・より抜粋)
午後2時
足下に雑草が吹き出している
コンクリートの割れ目から
緑の槍のように
太陽は
尖った命を沸騰させようとしている
(処方箋・柿沼徹・・・より抜粋)
May 17, 2006
国家の品格 藤原正彦
この本は講演記録をもとにしているために、話し言葉に品がなくて(ご当人のお言葉です。念の為。)大幅に加筆したもののようです。ご当人のお言葉を拝借すれば、「品格なき筆者による品格ある国家論という極めて珍しい書」とのことです。たしかに。。。「品格」の有無はともかくとして、この本の文体そのものが文章と話し言葉との境界線をあいまいなものにしてしまったという感は否めないと思います。なにか、この本を早く出版しなくてはならないというような意図が背後に働いているのではないのか?という懸念がかすかにありました。とはいえ、藤原正彦の主張は明快なものですので、充分に読み取れるものではありました。
藤原正彦はさまざまな例を出し、かなり乱暴な論法を駆使して、自らの考え方(論理とは言わない。)を押し出していました。藤原いわく「論理というものだけでは、国家、民主主義、平和、戦争、自由、平等などをくみたてられるものではない。」ということのようです。
『論理とか合理を「剛」とするならば、情緒とか形は「柔」です。硬い構造と柔らかい構造を相携えて、はじめて人間の総合判断力は十全なものとなる、と思うのです。」
この「柔」の要素として、藤原は日本独自にあった「武士道」と、日本文学の永い歴史の底流をなしてきた「情緒力」や「もののあわれ」を差し出しています。一瞬「時代錯誤か?」といういぶかしい思いがありましたが、読み続けるうちに、それが決して古いものではなくて、時代を超えて相通じるものであることは納得できました。つまり藤原は日本人が真の国際人になるためには、「英語力」ではなくて「日本独自の言葉の文化や伝統」を内部に育てるべきだと言うことかな?こうしてやっとやっと「国家の品格」は浮上するのかもしれません。
『民主主義にはもちろんきちんとした論理は通っていますが、「国民が成熟した判断ができる」という大前提は永遠に満たされないこと、その本質たる自由と平等はその存在と正当性のために神を必要とすること、という致命的とも言える欠陥があります。』
この本を読みながらしきりに思い出していた一編の詩がありました。ルーパード・ブルックは若くして戦死した軍人でした。そしてこの詩はイギリス国家の戦勝祈願として使われたらしいという経緯はありますが、詩人が意図したものはそのようなものではなかったのではないかと、わたくしは思っています。
軍人(The Soldier) ルーパード・ブルック(1887~1915・イギリス)
(田中清太郎 訳)
万一ぼくが死んだなら ぼくのことはただ次のようにだけ思ってください、
どこか異国の野の片隅に
永遠にイギリスである場所が存続するということを。
そこの肥沃な土の中には もっと肥沃な土くれがかくされているはずだ。
その土くれと化した肉体はイギリスが生み 形を与え 意識をもたせたものだった。
かつてはそれに 愛するようにと花を さまうようにと小道を 与えてくれたのもイギリスだった。
それは イギリスの空気を呼吸し
川の水で洗われ 故郷の太陽によって祝福されたイギリスの肉体だったのだ。
そしてまた 次のようにも思ってください。すべての邪念を洗い流したこの心が
不滅の心のなかのこの鼓動が 同じように
イギリスから与えられた数々の思いを どこかにお返ししているのだと。
イギリスの風景と響き 昼間と同じように楽しいイギリスの夜の夢
友達から学んだ笑い そしてまたイギリスの空の下にある
平和な心の穏やかさを どこかにお返ししているのだと。
(二〇〇五年初刷―二〇〇六年八刷・新潮新書)
May 14, 2006
詩人の目―大岡信コレクション展
(駒井哲郎・岩礁にて「At Rock Seashore」・一九七〇年)
これ↑は、展示作品のなかでわたくしが一番好きな作品でした。
十三日は寒かった。さらに雨と風。心がけの悪い奴等(?)だ。
しかし約束通り三鷹駅で待ち合わせて、駅前の三鷹市美術ギャラリーへ「詩人の目―大岡信コレクション展」を観にゆきました。美術館が駅前にあるというのは市政の心根の良さを感じますね。埼玉県の草加市(だったかな?)では駅前に大きな図書館があって「いいなぁ。」と思ったこともありましたが。。。
一九五六年、大岡信は「美術評論・パウル・クレー」を書いたことから出発して、一九五九年、(この時、大岡は二十八歳。)かつて日本橋にあったという「南画廊」において、さまざまな美術家と出会うこととなり、その歳月のなかで蒐集された作品の紹介であった。作品が予想以上に多かったことに驚きましたが、一点づつ割合丁寧に観ました。
それは大岡信の詩に触発されて描かれた絵や作成された立体的な作品であったり、絵に触発されて書いた大岡信の詩で(直筆もある。)あったり、あるいは本の装丁であったり、というような作品が多かったので、詩に関わる者としてはとても楽しいものでした。大岡信の交友関係の広さにも驚かされましたが、夢みたいな詩と美術との交歓はつくづくと羨ましい。ただし抽象的な作品ばかりですのでわたくしには作品の評価は皆目わかりませぬ。好感か不快かで分ければ「不快」な作品はなかったと思います。また、俳人との「書」による連詩(連句?)の試みなどもありました。
「絵本詩集」を試みたり、「連詩」や「相聞」などを試みることに大きな興味があるわたくしとしては、この「贈答」の作品たちに心動かされることが多いのでした。またいつか新しい詩集を作ることなどを想像しながら観ていますと、さらに夢はふくらみます。予想以上に楽しかったです。
もちろん南画廊主から「これは詩人の大岡が持つべきだ。」と言われて、大岡自身が購入した高価なオディロン・ルドンの銅版画九点などもありました。これは、シャルル・ボードレールの「悪の華」の挿絵となった作品でした。
その後は荻窪に行って、「ささま書店」で古本あさり。これも見ていればきりがない。買うには書棚と経済との限度というものがある。雨だから書籍が痛むだろうし、すでに頂いた詩誌や三鷹ギャラリーで買った画集が重いしで、悩みつつ最低限に抑える。お初の下見なのだからまた行けばいいのさ。。。
May 12, 2006
目覚め
目覚めるといつも私が居て遺憾 池田澄子
この句は清水哲男さんの「増殖する俳句歳時記」の今日の挙句です。
ううむ。実感。。。
クスリでどうやら夜を眠って、ひどい低血圧の朝の目覚めの時には、ほとんど絶望的な精神状況です。それでも「よっしゃー!」と一日生きる。面白い本に出合ったり、なんとか気に入った一編の詩ができればシアワセというもの。
明日はお出掛けです。そういう日は目覚めてから、ちょっぴりシアワセ(^^)。
(たましいの話・二〇〇五年刊所収)
May 09, 2006
人形と情念 増渕宗一
「人形を愛する」ということは、ひとが老いて醜くなってゆくこと、あるいは日常のなかで、次第に汚れてゆき、あるいは撓んでゆくものからの回避ではないのか?それは時間を止めることではないのか?という思いがわたくしのなかから抜けてゆかない。
もう一つ思い浮かべることは、俳人「小西来山・1654年(承応3年)大阪産まれ。」が1708年(宝永5年)に書いた俳文「女人形記」の下記の一文です。これは一種のエゴイズムではないのか?
『(前略)ものいはず笑はぬかはりには、腹立ず悋気せず、蚤蚊の痛を覚ねば、いつまでもいつまでも居住居を崩さず。留守に待らんとの心づかひなく、酒を呑ぬは心うけれど、さもしげに物喰ぬてよし。白きものぬらねばはげる事なし。四時おなじ衣装なれども、寒暑をしらねば、此方気のはる事更になし。(中略)愛のあまりに腹の上に置時は、呼吸にしたがいてうなずくうなずく、細目してうなずく。』
(一)
『人形は、人間の愛と憎しみのための試金石である。』
さてしかし、この本はこのわたくしのそのような問いかけには応えて下さらなかったようだ。一章がこの本の表題となっているのだが、ここに頻出する「情念」という言葉はあまりにも重い。。「愛」「嫉妬」「呪い」「憎悪」「孤独」の身代わりとしての人形。あるいは「災い」を背負わされるために作られ、すぐに流される人形たちだった。。。
また人形は「ヒトカタ」あるいは「カタシロ」と言われ、「ニンギョウ」と訓まれたのは1477年の「おゆとのの上の日記」がはじめとされているらしいが、この訓まれ方の変遷はきっと人間と人形との関わりの変遷でもあるのだろう。
(二)
『存在者から神性を抽象すれば、それは彫刻の形式と結びつき、情念を抽象すればそれは人形の形式と結びつくといってもよいのである。』
ここでは「彫像」が中心となっているようだが、古代の仏像や神像、ロダン、ピカソ、盲人などの作品、高村光太郎、和辻哲郎の彫刻と人形(この想定の差異も大きいが。。。)論、さらに「こけし」「姉さま人形」など多岐に渡るために、ややとりとめない人形美学論となっている。
(三)
『人形の衣装は、(中略)もっとも純粋な偽装の祝祭である。』
『人間と衣装との結びつきは始原的なものである。』
『人形はエロス(恋愛)にかかわる場合、衣装なき裸身と結びつくことが多い。』
ここでは「衣装」のお話になるのですが、ファッションショーとモデル、スタイル画、お化け、宗教画における衣装、徒手体操、フィギア・スケート、トランポリン、サーカス、果ては裸のキューピー、動物のぬいぐるみまで及び、とりとめのなさは果てしない。筆者の頭のなかではおそらくどこかへ着地するまでのあてどなく拡散してゆく思索の道筋なのだろう。読者としてついてゆくのは大変困難なことだ。
(四)
『人は、人形に人間の中の人間を求め、ロボットに人間の機能面での代替物を求めているのである。』
ここでは、ロボット、ピノキオ、ビュグマリオン伝説、からくり人形、おさな児のおしゃぶり、などなど、さらに話題は拡散してゆく。このなかの「ビュグマリオン伝説」には、わたしなりの異見を差し出しておきたい。美しい象牙の女性像に恋をした男は、神にその像を生きた女性に変える願いをする。願いは叶えられて、像はぬくもりを持つ女性の肉体となり、その男の子供を産む。永い歴史のなかで処女性を失った女性は「穢れ」とされてきた。今の時代でも「人形愛」の世界ではこの「穢れ」は排除されているのではないかと思うが、筆者は子供の誕生を幸福な愛の結果としている。これはおおきな矛盾ではないか?
(五)
『人は、みずからの住む家をたてると同時に、神の家をたて、人形の家をたてる。』
なるほどね。ここでは神殿にまつわるお話、ドールハウスの歴史、雛壇の歴史などに触れている。「人形の家」と聞くと、わたくしは「ノラ」に反応してしまうので困った。「人形の家」は人間生活の動かぬ縮図であり、それゆえの愛らしさなのだろう。
(六)
『人形も、愛玩動物も、共に、人間の熱愛憎悪の相関者である。
愛玩動物は、人形と同様、人間の伴侶であり、人間と愛憎を共にし、また寝食を共にしている。しかし愛玩動物には、いつか死がやってくる。つまり、愛玩動物には生物学的な生死があり、死を契機に、愛玩動物は人間の同伴者たりえず、ある他のものに転落してゆく。これに対して人形は、人間の同伴者として、つねにあらたである。』
ここでこの本からの引用はおわり。はじめの章と最後の章で、どうやらこの筆者である「増渕宗一」の論点は呼応しているようであった。中間部のほとんどはここに辿り着くための「拡散」だったのだろう。
「人形論」からはずれますが、この筆者の文章には「、」が多いなぁ。それから漢字で書いてもいいような言葉を平仮名で書くというところも何度かあって、奇妙に気にかかったなぁ。
では最後に、わたくし自身の人形との関わりの歴史を考えてみよう。病弱で学校へ通うことすら苦痛であった少女期の遊びのほとんどは「人形遊び」だった。布の端切れで人形の衣服を作り、きれいなお菓子箱などを集めて、それで人形の部屋を作り、大日さまのお祭りの機会には、セルロイドで出来た家具などを買い揃え、旅行に出る大人たちへのお土産のおねだりは必ず「小さな食器」だった。
大人になったわたくしは、見惚れるほどに可愛い(マジである。)女の子を授かった。しかしこの可愛い生き人形はウンチもオシッコもする。オナラまでする。食べ物が気にいらなければ吐きだす。夜泣きが1ヶ月以上も続くなど、この愛らしい泣き人形はほとほと若かったわたくしを困らせた。しかし幼子のもつ愛らしさがこうした困難を乗り越えさせるものだったのだとしか思えない。次には、これまた美しい王子のような男の子(マジである。)を授かった。
その期間にわたくしはおそらく「無意識の子供時代」をもう一度生きたのだろう。言葉のはじまりに立会い、子供の玩具を買うことに同行したり、ままごとの相手をしたり、絵本を見たり、遊園地や海や雪山に行ったり、かくしてこの生き人形はまたたくまに育ち、わたくしの手から離れていったのである。実感として、わたくしに残った感覚は「小さきものだけが持ちえる愛らしさ」の魔法のような力だけだったと思う。
この本のテーマである「人形美学」は未開拓な分野であって、世界に類を見ないものとされている。この本の出版年が一九八二年ですから、その後も引き続きそうであるのかはわたくしには確認できません。
(一九八二年・勁草書房刊)
May 06, 2006
MY SONG BOOK 水の上衣 清水哲男
風薫る五月である。ある偶然から懐かしい詩集を出してきました。わたくしが二十代、詩人清水哲男三十代・・・・・・大昔の詩集となる。(ごめんなさ~い。)そしてそれは「革命」や「青春」という言葉にかげりが見え始めた季節ではなかったろうか?実はこの詩集のなかに「美しい五月」という詩があるのです。まず全文をご紹介します。
美しい五月
唄が火に包まれる
楽器の浅い水が揺れる
頬と帽子をかすめて飛ぶ
ナイフのような希望を捨てて
私は何処へ歩こうか
記憶の石英を剥すために
握った果実は投げすてなければ
たった一人を呼び返すためには
声の刺青を消さなければ
私はあきらめる
光の中の出会いを
私はあきらめる
かがみこむほどの愛を
私はあきらめる
そして五月を。
この詩のなかに隠されているものをわたくしはおそらく正確には把握できていないだろう。「愛」は友人に向けたものか、人間すべてに向けたものか、あるいはたった一人の女性に向けたものかで、この詩の全体の解釈は大きく変わる。全部でいいんじゃないのとも思うけれど。。。
「五月」はおそらく一九六八年(昭和四十三年)のフランスの五月革命ではないかと思うが、また青春の終末期の予感のような悲しみが降ってくる季節であるとも言える。最後の六行は、そのままそれぞれの心の歴史にも投影されてくる。ひとはこのような季節を繰り返しながら生きてきたのではないのだろうか?エリオットは「四月はいちばん無情な月」なんて言っていたけれど、ある時間の区切りに「言葉」を与えるということは、次の季節へのいざないではないだろうか?
美しい詩である。
(昭和四十五年・限定二五〇部・非売品・・・編集正津べん?)
Apr 30, 2006
良寛 水上勉
草枕夜ごとにかはるやどりにも結ぶはおなじふるさとのゆめ 良寛
『私も九歳の経験があるのでかくいうが、その「出家」とは、旅立ちであるゆえに、出発の日から、家郷を抱くのである。父母を抱きなおすのである。良寛の旅立ちもそれを教える。』これは九歳で「出家」の経験を持つ水上勉による良寛への思いである。水上勉はみずからの体験を幾度も良寛に重ねながら、敬愛を込めてこの本を書きすすめていったように思いました。
しかし残念なことですが、この一冊をわたくしが総て理解できたわけではない。良寛の生きた時代背景、宗教やそこに登場する幾多の僧侶に対する知識、「荘子」「龐」の思想、そこまでわたくしの知識は充分に届いていない。わたくしの予想通りに時間のかかる読書となった。無念さがあるがいたしかたない。無事に読み終えた自分を褒めてあげよう(^^)。。。
良寛(栄蔵)は名主の家に産まれるが、飢饉、洪水、大火災などに経済が大きく揺れた時代であり、決して恵まれた少年期ではなかったようだが、書物に接する機会だけはあったようです。宗教も幕府からの干渉と規制がきつく、あってはならぬことだが、宗教の世界は非常に厳しい人間の差別を産み出していた。さらに重ねてキリシタン禁制の時代でもあったのだ。こういう時代に家を継ぐことをせずに、遅い出家をした良寛は当然乞食のような宗教者となるしかないではないか。彼の生きる道標となったものは「国仙和尚」の直の教えと、「荘子」「龐」の教えであったようだ。しかしこの本でわたくしは「素願」という言葉も知った。境遇やさまざなな教えよりも先立つものとして、人間が本来的に持っていた願いというものがある。良寛を導いたものはここにあったのではないだろうか?
夜は寒し麻の衣はいとうすしうき世の民になにをかけまし
天も水もひとつに見ゆる海の上に浮かびて見ゆる佐渡が島山
水上勉は、さまざまな前人の残した膨大な量の良寛の評伝に対して謙虚に丁寧にあたり、かすかな反論も反論という姿勢は持たずに、素朴な疑問の形として残し、その上で水上は初めて自論を差し出して見せるのでした。
さて中間部にきて、水上の良寛への信頼が少し揺らいでいるようだった。それは良寛の出家から、さまざまな紆余曲折の末に、教団へ背を向けた乞食坊主には、激しい詩歌への思いはあるものの、良寛がかつて尊敬し、学んだ僧侶の生き方(労働をするということ。)とは離れていることへの憂慮である。 しかし、良寛は「五合庵」においては、一人の僧侶としてではなく、無垢の子供のなかに仏心を見い出し、ひたすら多くの詩歌を書き続ける。これは水上勉自身の僧侶から文人への転身と類似した心の道のりではなかったか?
良寛は詩歌に激しく関わることによって、たくさんの良き友を得る。乞食坊主の身ではあるが、これによってのびやかに生き生きとした日々はようやく訪れるようだった。水上勉はこう記している。『もともと文芸とはとはそういう自然なものであって、折にふれて詠む朝夕の感想を人に送り、あるいは送られて、また返書してゆく楽しみである。左様。たのしみでなくてはならぬ。』竹西寛子の著書「贈答のうた・講談社刊」に書かれていた言葉「うたはあのようにも詠まれてきた。人はあのようにも心を用いて生きてきた。」をふっと思い出す。
人の子の遊ぶを見ればにはたづみ流るる涙とどめかねつも
身を捨てゝ世をすくふ人も在すものを草の庵にひまもとむとは
しかし、たとえ良寛とはいえ「老い」は容赦なく訪れる。その時期に「貞心尼」の登場であった。良寛七十歳、貞心尼三十歳という出会いであった。水上勉はこの出会いをとてもうれしく大切な出来事として書いていることがとても微笑ましい。わたくしも素直にこれにうなずくばかりだった。
これぞこのほとけのみちにあそびつゝつくやつきせぬみのりなるらむ 貞心尼
つきみてよひふミよいむなやこゝのとをとをとおさめてまたはじまるを 良寛
きみにかくあひ見ることのうれしさもまださめやらぬゆめかとぞおもふ 貞心尼
ゆめの世にかくまどろみてゆめをまたかたるもゆめもそれがまにまに 良寛
たちかへりまたもとひこむたまぼこのみちのしばくさたどりたどりに 貞心尼
またもこよしばのいほりをいとハずはすすきをばなのつゆをわけわけ 良寛
しかしその出会いの翌年には大地震が起こった。
うちつけにしなばしなずてながらへてかゝるうきめを見るがわびしさ 良寛
ここで水上勉は「しめくくり」のような形で「龐」の生き方と良寛の生き方を、その仏教史の時代背景と二人の生き方の類似性を差し出して、「龐」が良寛の源流ではなかったかと書いている。水上勉が引用している入矢義高の解説にあるように『あなたの悟りを、あなた自身の言葉に定着させて言ってみてくれ』(求道と悦・龐居士――その人と禅 より。)ということに集約されてくるようだった。
その地震の三年後に良寛は逝去。貞心尼との歳月はわずかに四年間だったことになるが、はかなくもうつくしい歳月であったことだろう。
生き死にの界はなれて住む身にも避らぬ別れのあるぞかなしき 貞心尼
うらをみせおもてをみせて散るもみじ 良寛
この本を読みながら、しきりに上野の国立博物館の「書の至宝展」で観た、良寛ののびやかでやさしい、平仮名の多い屏風の書が思い出されるのだった。良寛は勿論漢詩も残しているが、ここに水上勉が取り上げた詩歌は、平明で平仮名の多いことにあらためて気付かされた。ここにも良寛の生き方が投影されているように思えてならない。
【付記】
この読書に苦戦しているわたくしの惨状(?)に手をさしのべるように、桐田真輔さんから、ご自分のもっていらっしゃる「良寛全集」からコピーした「鉢の子」に関する詩歌二十数編をいただきました。これはわたくしの読んだ水上勉の著書には取り上げられていないものでした。これによって良寛の托鉢の様子と「鉢の子」によせる愛しさが少し見えてきました。とても嬉しかった。
道のべの菫つみつゝ鉢の子をわすれてぞ来しその鉢の子を
鉢の子をわが忘るれど取る人はなし取る人はなし鉢の子あはれ
(昭和五十九年・中央公論社刊)
Apr 25, 2006
東京奇譚集 村上春樹
春雷が二日続いた。夏の雷とは違って奇妙な胸騒ぎのする気象現象だが、それは特例ではないので、わたくしも特別な意味付けは避けることにしよう。人間は、自らの生きている理由をなにものかに託したいと思うし、託されていたいとも思うものかもしれない。この五編の短編に書かれた一種の「超体験」は、一編一編がそれほどの傑作(すみませぬ。)とは言いがたく、物語の構成もいびつであり、読み手としては苦しいものもあったが、一冊を読み終わるころには、わたしなりの答えは準備されたと思う。
現実のなかでは、その自らのわずかな「超体験」の意味は他者には意味のないことではないか?わたくしにもこうした時空を超えたささやかな体験や、自らの名前を失ったという体験がないわけではない。前者の体験は幸福な記憶として残り続けることだろう。しかし後者の記憶はその要因を含めて、季節の過ぎ去るのを待つしかない。ひとが生きるということは、丹念に、よりうつくしい思い出を積み上げてゆくことのみではないのかと近頃は思うようになった。そんな時期にこの本を読んだ。
『偶然の旅人』はまさに、偶然の不思議で幸福な出会いや出来事である。それをひとが大きな出来事と思うか、思わないかによって、それぞれのひとの生きる方向性が見えるのだった。『ハナレイ・ベイ』は死者と生者との地上での再会であり、『どこであれそれが見つかりそうな場所で』は、数分後には帰宅するはずだった人間が忽然と消えるという出来事だ。二週間という時間の経過の後に、その人間は保護されるが、髯が伸びたり、痩せていたりという現実的な時間の経過はあるが、その人間の心のなかは全く空白だった。
『日々移動する腎臓のかたちをした石』は、主人公の作家の書きかけの小説ネタである。ちょっと苦しい。。。この作家は十六歳の時に、父親が言った「男が一生に出会う中で、本当に意味を持つ女は三人しかいない。それより多くもないし、少なくもない。」という言葉の縛りのなかで生きている。一人目の女性は彼の一番の親友と結婚してしまう。この物語のなかでは二番目の女性に出会うことになったが、彼女も立ち去る。続きの三番目の女性との出会いの予感もなく終わった。
『品川猿』は、ある日から、主人公の女性が自分の名前の記憶だけを失うというお話だ。その原因を手繰ってゆくと、名前の盗人は「猿」だったという展開なので、猿芝居(失礼!)とは言わないが、狸の尻尾みたいなお話だ。その名前と引き換えにその女性は、少女期に家族から本当は愛されていなかったという、一種のベールを被せておいたままにしておいた時間を、その猿から暴かれるという展開だ。
ひとが幸福に生きるということがほとんど不可能に近いことだとすれば、「奇跡」とか「偶然」とか、あるいは「記憶の喪失」というようなことが、ひとを救済することとなり得るのではないのか?ふと、そのような思いが心をよぎるのだった。。。
(二〇〇五年・新潮社刊)
Apr 24, 2006
孤独を生ききる 瀬戸内寂聴
「人間はみなそれぞれに孤独でしょう。」と言うわたしの発言に対して、「孤独についての解釈は、欧米文化と日本では異なる。」と教えていただいたことがある。「孤独」を広辞苑でひくと「みなし子と老いて子なき者」となる。さらに「鰥寡=かんか」をひくと「妻を失った男と夫を失った女」となる。これは情況としての孤独のようですね。魂の問題ではないようです。
この本は九年前に死んだ独り身の姉の書棚にあったものでした。大半の書籍は姉やわたしの友人に差し上げましたが、何故か気になって手元に残した本のなかの一冊でした。ここに書かれている「孤独」もやはり情況的な孤独であったと思いました。さらに瀬戸内寂聴の「孤独」とは仏教と重ね合わせてどのようなものであったかは、かなりあいまいである。
はたしてこの本を読んだ人々が瀬戸内寂聴が「はじめに」のなかで書いてあるように「あなたの孤独が私の孤独に溶け込み、吸収されますように。」という願いが届いたのだろうか?という疑問が残る。死んだ姉がこの本によって癒されたとは到底思えない。確信しているのだが、死んだ姉を一番理解していたのは、このわたしだからだ。
今日は病院に行った。病院は老人が多い。(あら。あたしもそうかしらん?)今日見かけた老人は、医師だけに辛い身体的症状と生活上の困難さを訴えるだけでは気がすまないらしく、待合室では周囲の人に語りかける。診察が終われば会計の受付の事務員に訴える。処方箋を持って薬局に行くと、そこでは薬剤師に訴える。その「訴え」は当然わたしの耳に届く。彼が独居老人だということもわかった。こんな時に前記の「孤独」を思い出して、実に日本的な風景だなぁと思うことがある。
(一九九二年・光文社刊)
Apr 23, 2006
Apr 19, 2006
灰色の魂 フィリップ・クローデル
フィリップ・クローデルは一九六二年フランス、ロレーヌ地方生まれ。四月十日に書いた「リンさんの小さな子」と同じく翻訳者は高橋啓だが、こちらの原作は翻訳者泣かせの作品であり、日本語にならないフランス語特有のレトリックや言い回しに満ちていたとのことです。また読み手にとっても物語全体の構成も登場人物(本の扉の裏には「主な登場人物」の紹介がある。)も複雑で、「リンさんの小さな子」と比べますと、重苦しくて難解な印象がありますが、この二つの作品の根底にあるテーマは、おそらく同質ではないかと思うのです。「リンさんの小さな子」が子供への伝言であるならば、この「灰色の魂」は大人の読者への伝言であるように思えます。
この小説は一九一四年から一九一八年の間にあった戦争の時代が背景となって、その時代に起きたさまざまな出来事を、「私」が回想するかたちで書かれています。舞台となっているフランスの小さな町は、すぐ近くまでが戦場でありながら、軍需工場で町の経済は支えられていて、かろうじて戦場とはならなかった町でした。しかし、町の病院は次第に傷病兵にあふれ、主要な道路は軍需優先と化してゆくなかで、人々はさまざまな表情を見せることになります。
検察官、判事、警官、居酒屋の家族と小さな美しい娘、小学校教師、獣皮商人、皮職人、兵士、神父、尼僧、医師、看護婦、とても語りきれない。どう語ればいいのだろう?「戦争」というものがもたらす最も根源的な不幸は、人々が「いのちの重さ」のはかり方を際限もなく狂わせてゆくことではないのだろうか?
またこのような時代の人々の混乱は、兵士であれ、殺人者であれ、普通の市民であれ、権力者であれ、同じようであり、同じではない。権力者側の人間はいつでもぬくぬくと生き残れるという落差構造が必ずあるということだとも言えるだろうか?
そしてこの物語の語り手である「私」と最もこの物語に登場する検察官の「ピエール=アンジュ・デスティナ」との共通項は、若いままの愛する伴侶を失ったことによって、生涯に渡って大きな心の暗部を抱いていたことにあるようだ。
『劇の他の場面がいかに美しくても、最後は血なまぐさい。ついには頭から土をかぶせられ、それで永遠におしまいである。・・・・・・パスカルのパンセより。』この言葉は「デスティナ」がその本に傍線を引いた部分だ。何度も読み返された本のようだ。またこの物語の語り手である「私」は、このように記述する。『人はひとつの国に暮せるように、悔恨のなかで生きられるものだということだ。』最後にこの物語が「私」の重大な罪の告白に至るまでの、永い道のりであったことに気付かされることになる。
(二〇〇四年・みすず書房刊・高橋啓訳)
Apr 17, 2006
ぐらぐらの四月だ。。。
四月に入ってから、ふいに前詩集以後の詩作品の整理をはじめた。推敲も繰り返したが、そこから先へ進んでゆけないのは何故か?読んでいる本にも集中できず、読書と作品整理の間を右往左往しているだけだ。ぐらぐらだなぁ~。これは「一人遊び」である。勝手にしやがれ。期限は今月末までとするぞ。「連詩」の試みも途切れがちながら、ずっと続けられていることは嬉しい。わたくしごとき三文詩人の相方をつとめるお方の忍耐強さに感謝せねばなるまいか(^^;)。。。この試みは相方が納得しない限り公表することはありえないが、苦しくも楽しい「二人遊び」である。
Apr 10, 2006
リンさんの小さな子 フィリップ・クローデル
この物語は美しい童話のようなお話ですが、この背景となっているテーマははっきりと見えます。そしてどっしりと重い。文中には一言も書かれていませんので、わたくしの想像する歴史的事実は書かないことにいたしましょう。
これは、フランス人作家フィリップ・クローデルの養女クレオフェ(ベトナム人)のために書かれた物語です。「クレオフェ」とはギリシャ神話に登場する栄光の女神の名前です。しかしこの物語に登場する老人リンさんと小さな子(孫娘)、友人のバルクさんの国名もその物語の場となったところも、特定されてはいません。それは、このような哀しく、美しい物語は世界中どこにでもあるということへの示唆ではないかとおもわれます。
小さな子の名前は「サン・ディヴ=おだやかな朝という意味」ですが、友人のバルクさんは「サン・デュー=神なしという意味」と呼んでいました。二人は「こんにちは」という一言だけしか言葉が通じ合えない、国の異なる、しかしながらこれほどの友情があるだろうか?という友人になるのです。
リンさんは豊かな自然に恵まれた農村で幸せに暮していたのですが、戦禍に巻き込まれて、息子夫婦は畑で殺され、そばには首のない人形がいて、ぱっちりと目を開けていた孫娘「サン・ディヴ」だけが残り、リンさんはその孫娘とともに難民船に乗り、異国の土地の収容所に入り、散歩中の公園のベンチでバルクさんと友人になるのでした。バルクさんはかつて二十歳の時に兵士として、異国の農民を虐殺した体験に苦しみ、妻に先立たれた一人ぽっちの男でした。
さて、この小さな子はあまりにもいつでもおとなしい。この静かさのために、この子が何者なのかはわたくしにはすぐにわかりました。バルクさんはこの子のために可愛いドレスをプレゼントしたりするという微笑ましい場面もありますが、この小さな子「サン・ディヴ」が一体誰だったのかということもここではお話したくはありません。
いつでも朝はある
いつでも朝日は戻ってくる
いつでも明日はある
いつかおまえも母になる
これは母親が子供に歌う子守唄です。この物語のなかでは、リンさんが何度も小さな子の耳元にささやいていた歌でした。
(二〇〇五年・みすず書房刊・高橋啓訳)
Apr 06, 2006
数学者の言葉では 藤原正彦
ともかく読後の気持のよい本であった、とまず申し上げておきたい。この著書のなかで、著者自身が引用しているポール・ヴァレリーの「数学」についての言葉が、この著書の魅力を語っているようです 。
『私は学問の中で最も美しいこの学問の賛美者であり報いられることのない愛をこれに捧げている。』
これは昭和五十六年(一九八一年)新潮社より刊行された後に、昭和五十九年(一九八四年)に刊行された文庫版ですので、多分藤原正彦が三十代に書かれたものと思われます。かつてのガキ大将だった彼のまだ若くてちょっぴり辛辣で生意気な数学者さんの楽しいエッセーでした。藤原正彦は新田次郎と藤原ていのご子息であり、幼児期には困難をきわめた引揚っ子でもあります。数学者と文学者のはざまで「言葉の美しさ」をとても大切にして生きた方だと思えます。この本についてはわたくし自身の思い入れや共感がとても多いので、極私的な感想になると思います。お許しを。。。
【学問と文化】
まず、この章を読みながらわたくしの脳裏にはずっと亡父がいました。わたくしは読書が非常に遅い。さらに読書の長い空白期間もあった。従って入手できた情報や知識が極めて限られるので、先輩、友人に教えて頂くことは多々あるのです。その時のわたくしは生意気にも教えて下さる方の知識度を量るという悪癖があります(^^;)。その基準となるものは、わたくしにわかりやすい言葉で語って下さった方は、多分それについてご自分の内部にすでに構築された相当量の知識を持っていらっしゃるということです。
この極私的基準は数学と物理の教師だった父から自然に受け取ったものであって、父から教導されたものではありません。父は生涯に渡って本当によく学ぶ人でした。学校勤務を終えて帰宅して、晩酌、夕食、入浴が済めば、寝るまでの時間はすべて書斎にいる人でした。子供心にも「あの父の書斎の扉の向こうには広大な浪漫があるのだろうか?」と思える程でした。また休日には母から頼まれた男仕事をきちんとこなすという面もありました。(それは物理の実践だったのではあるまいか?)そして娘のわたくしに「勉強しなさい。」とは一度も言わなかった。
しかし受験を控えた時期に、母は担任教師から「このままではお嬢さんの志望校合格は難しいのです。」と言われてから、わたくしを取り巻く環境は急変しました。母の要請で毎晩父の夜の課外授業が開始されてしまったのです。父の教え方に接しているうちに、わたくしの学校教師の教え方との大きな違いがよくわかったのです。その時の父の教え方は実にわかりやすく見事だったという鮮明な記憶が、このわたくしの生意気な基準を作ってしまったのです。(結果は予想を越えた上位合格でした。)
ちょっとお話が横道に逸れますが、難解な詩についても同じことが言えそうです。その詩の根底に確かな構造力と表現への道筋があるものは、たとえ難解でも作品のところどころにキーワードを置いているので、そこを辿ることは可能です。しかし読者を想定しない自慰的な難解詩はキーワードを置いていないので、ただの訳のわからないキケンな詩となってしまうように思えます。(わっ!三文詩人のわたくしがなんたる暴言を!!!)
さて、私事が優先してしまいましたが、ここでの藤原正彦の主張は明快です。米国の大学での招聘教授を経験した藤原の、日本の大学教授の研究と講義との比重のバランスの悪さへの指摘です。たとえ研究者として優れている教授であっても、学生への講義の負担を厭うことです。講義とはとりもなおさず「言葉」を媒体にしている。その「言葉」の往来が極めて貧しい。さらにそれに拍車をかけているのは日本の大学生の学ぶ意欲の希薄さです。過酷な受験戦争を勝ち抜いた安堵感が、もっとも学ぶべき貴重な大学生期間を粗末にしてしまっている学生が大半なのです。その間の親の学資負担の重さにさえ気付かない学生も多いことだろう。その上マークシート式テストに慣れてしまった学生たちは言語表現の貧しさまでを育ててしまった。ここに藤原正彦の言葉を引用しておきます。
『実は講義の上手下手は、一国の文化と深く関わっている。すなわち、アメリカやフランスには、「言葉の文化」と呼び得るものが存在するのである。自らの意志や考えを、言葉をもって理論的かつ明晰に表現することが、高度の知性として尊重される。』
また藤原正彦は、真の研究者というものは、寝食さえ忘れるほどの粘着性がなければ、研究の進展はないとも断言しています。その研究成果を明確な言葉で学生に手渡すことができないとしたら、それは貧しい文化ではないでしょうか?
『生命を燃焼しなければ真理が見えてこない。』 数学者 岡 清
【旅の思い出】
この章では、「ロスアンゼルスの一日」「ヨーロッパ・パック新婚旅行」があり、後者はみずからのユーモラスな新婚旅行記なのですが、とりあえずここはカット。。。上記との関連で「ヤング・アメリ カンズ」に注目したい。アメリカには「ハーバード」「エール」などの一流大学はたしかにあるが、そこに米国中の秀才が集まるわけではない。そこに入学するためには莫大な学資と生活費が必要でもある。それに代わって州立大学は、州内の学生に対して格別に費用を安くしているので、そこを選ぶ学生は当然多くなり、大学間の格差がそれほどないので、日本のような受験戦争はないらしい。
その代わりに米国の子供は高校生までは勉強をしない。大学からが本気で勉強する場だという考えがある。しかも支払った学資に見合うだけのものを彼等はきっちり取り返すという合理性もあるようだ。しかし、学者を目指す若者たちは日米を問わず孤独である。
【数学と文学のはざまにて】
この章では、父上の新田次郎との交流や、数学と文学との往来について触れています。「文学は有限なるもの。」「数学は無限なるもの。」であり、また「文学は言葉によって思考する。書きながら進行 するもの。」「数学は思考の結果を言葉とするもの。先に言葉はない。」もののようです。その二つの世界の往来は思いのほか道のりがある。それでも藤原正彦があえてその生き方を選んだのかは、ご両親 が作家であるという宿命のようなものもあるかもしれませんが、はっきりとした理由はおそらくない。数学は役にたたない分、科学のような悪用もされないと言い、下記のポアンカレの言葉が大学生時代の藤原正彦を導いたけれど、この著書を書く頃には「これもよかろう。」という距離ができている。
『真理の探求、これが我々の行動の目標でなければならない。これをおいて行動に値する目標はない。』 数学者 ポアンカレ
また、宮城県のダム建設現場から奈良時代のうるし紙が発見されて、それを赤外線装置にかけたところ、そこには墨で書いた「九九八十一」の文字が浮かび上がったという。万葉集などから奈良時代から 掛け算が使用されていたことはうかがい知ることはできるが、藤原正彦はこの発見を通して、さまざまな想像に心を躍らせながら書いていることが、こちらに伝わってきて大変好もしい思いになる。
例えば、中国から渡ってきた掛け算を学んだエリートたちが各地に赴任して、租税や収穫量の計算に利用する。さらにそれは庶民に広まり、暗算国日本の黎明となったこと。あるいは藤原自身が研究に行き詰まり、あてどのない旅に出た途中で、山陰の片田舎の木造校舎から聞こえてきた子供等の「九九」の旋律が早春の風景に調和して、数学の原風景に出会ったという歓び。海外において数学だけは国境を越える唯一の文化だという実感。そうしたさまざまな思いが「数学」が時間も国境も超えるものであるという歓びに繋がってゆくのだった。
【父を思う】
父親の新田次郎の小説を、藤原正彦はすべて読んでいるわけではない。肉親の文学作品を読むということは、冷静な読者にはなれないからだろう。父親の書いた小説のなかで、息子は恋愛場面がでてくると例外なく拒絶反応を起して異常なほど潔癖になり、その場面がなくとも小説は充分に成立するとさえ父親に悪態を突くのだった。その悪態ぶりは尋常ではなく、父親は編集者に相談するほどだったという。しかし息子の意見は却下される。父親に息子は「未熟者」と笑われ、それが的を得た答えだったために息子は余計にくやしがる。。。読んでいて「クスクス・・・」であった。
反面、父親は息子の書いたものにはすべて目を通した。息子もそれを願っていた。「まあ良い」「面白い」「非常に面白い」という三種類の答えから息子は推敲の程度をはかっていたようだ。不思議に思うことはここに同じ小説家である母親の藤原ていの介入がまったく見られないことだった。もしもあるならば、藤原正彦が母親について書いたものを読んでみたいと思う。
(昭和五十九年・新潮文庫)
Apr 02, 2006
桜を観た日
三月三十一日、快晴の午後は少し寒くて風も強かったけれど、多摩川の土手沿いの桜並木を訪れる。翌日から「桜祭り」なるものが始まる前の一日をそぞろ歩きしました。(昨日の日記の続編です。)
そぞろ歩きをする前には、実は必要なものがあります(^^)。
こんなところで地ビールをちょっぴり。。。この酒造屋さんでは地酒と地ビールを造っています。
きれいな川があるところには酒造屋さん、お蕎麦屋さんはつきものですね。
ここの庭には椿の花が見事に咲いていました。
桜並木の土手を降りて近くの公園にも行きました。
木立はまだ新芽をかすかにふいている程度ですが、水仙が咲いていました。
Apr 01, 2006
Mar 29, 2006
小熊秀雄童話集
小熊秀雄は一九〇一年(明治三十四年)北海道小樽に生れる。二十歳の徴兵検査の折に、母マツの私生児だったことがわかる。養鶏場番人、炭焼き手伝い、鰊漁場労働、職工、伐木人夫、呉服店員などさまざまな仕事についていたが、一九二二年文才を認められて旭川新聞社の社会部記者となり、その後文芸欄を担当し、詩、童話、美術作品などを発表する。肺結核のため一九四〇年に夭逝。
これは十八話からなる童話集です。登場するのは人間だけではなく、家畜や狼、魚や花や野菜など、さまざまな生き物に託されて、短いお話は展開されています。これらの童話の背景には、小熊自身が私生児だったこと、さまざまな過酷な職業体験、北海道という土地の特性、貧しかったことへの哀しみと、それを言葉の力でなぐさめようとする想いと、貧しき者からの鋭い社会批判があるように思われました。
これに加えて、二〇〇四年、「池袋モンパルナス 小熊秀雄と画家たちの青春」展における、野見山暁治と窪島誠一郎の対談が収められています。このお二人は「無言館」の活動によって「菊池寛賞」を共に受賞されています。「池袋モンパルナス」とは、小熊秀雄の詩のタイトルから生れた言葉でしょう。
池袋モンパルナスに夜が来た
学生、無頼漢、芸術家が街に出る
この対談のなかで、小熊秀雄の絵の特徴にふれていますが、小熊が記者時代にはカメラがなかったので、写真の代わりにスケッチをした。それが彼の絵画の出発点だったという。「記憶を記録する。」ことが小熊の絵画だったと。。。これは童話のなかにも息づいているように思えてならない。
(二〇〇六年・清流出版刊)
Mar 28, 2006
ナルニア国物語・第一章「ライオンと魔女」

原作 C・S・ルイス 監督・製作総指揮・脚本 アンドリュー・アダムソン
ルイスのこの物語は七章からなるもので、今回映画化されたものはその第一章です。時代背景は第二次大戦初期のイギリス。ロンドンの空襲を逃れて、ペベンシー家の四人兄妹(長男ピーター、長女スーザン、次男エドマンド、次女ルーシー)が親元を離れて、田舎に住むカーク教授の屋敷に疎開をすることから、この物語は始まる。
教授の屋敷は古色蒼然として広く、子供たちのかくれんぼには最適な環境であった。淋しがっている末っ子のルーシーのために、兄と姉たちはかくれんぼをすることになる。ルーシーは誰もいない部屋にある大きな洋服ダンスのなかにかくれる。ルーシーはそこから雪の降る「ナルニア国」へ訪れることになる。
「ナルニア国」の住人は、魔女以外人間の姿をした者はいないが、ルーシーとの会話はすべて可能だった。神話に登場するさまざまな神々の姿に似ていたり、ライオン、ビーバー、狐など獣の姿そのものであったりする。住居はピーター・ラビット風であったり、ネィティヴ・アメリカンのテント、あるいはモンゴルのパオを模したものであったりして、いかにも「どこでもない場所」を象徴しているかのようだった。
こんなお話を誰が信じるだろうか?しかし、四人一緒に「ナルニア国」へ行くことはすぐに実現してしまった。ナルニア国は、氷の城に住む冷酷な「白い魔女」のために長い間冬の季節ばかりが続き、ナルニア国の人々は「アスラン王」の帰還を待ち、語りつがれた「預言」に希望を託していたのだった。その予言とは。。。
二人の「アダムの息子」と二人の「イヴの娘」が
「ケア・バラベル城の四つの王座」を満たす時
白い魔女の支配は終わる・・・
四人の兄妹はその予言を託された者として人々に迎えられ、さらにライオンの「アスラン王」に面会。武器や魔法の薬などを与えられ、ナルニア国を率いることになり、魔女との命をかけた戦闘まで突入してゆくが、その戦いのなかで兄妹たちは成長してゆく。戦闘は勝利する。ナルニア国に春が来る。
「ケア・バラベル城の四つの王座」は、「英雄王・ピーター」「優しの君・スーザン」「正義王・エドマンド」「頼もしの君・ルーシー」によって満たされた。その後平和は続き、ナルニア国では十年ほどの時間が経ち、四人はともに大人になるが、ふとしたことからまた洋服タンスを抜けて屋敷の部屋に戻る。四人はもとの時間に帰ってきたのだった。現実では戦争はまだ終わらず、疎開生活も続く。この世の平和の預言者は不在のままだった。教授だけは子供たちのファンタジー体験をわかっているのだった。この教授はルイスなのかしらん?
ファンタジー映画は時代とともに、CG技術の向上によって画像の作り物臭さが排除されてきている。この進歩には目を見張るものがある。(・・・と言ってもわたしはそれほどの映画通ではないのだが。。。)ウォルト・ディズニー社の製作も費用も膨大なものであろうことは想像できる。
しかし、どうしてもわたくしの気持が晴れないのは、四人の兄妹は現実においても、ナルニア国においても、「戦争」に巻き込まれたことだった。現実においては無力な四人だが、ナルニア国においては平和を導いた勇者であったと理解すべきなのだろうか?まだ物語ははじまったばかり、C・S・ルイスのメッセージはこれで終わりではないのだろう。。。
Mar 26, 2006
Mar 25, 2006
人形展と映画鑑賞の一日
二十四日午後、銀座松屋にて、人形作家「与勇輝・あたえゆうき」の作品を観ました。中央線、青梅線、さらに山手線の事故が重なり、有楽町駅前のコーヒー・ショップで同行者を待つこと四十分。「小 熊秀雄童話集」を読みながら、快晴に恵まれた今日を喜んでいたのに・・・などとつぶやきながら。。。さて無事同行者到着。映画の上映時間を一回分遅らせることにして、まずは人形展へ。
松屋八階の展示会場までの階段は一階から、長蛇の二列。。。あっけにとられるが「今日は待つ日。」といささか寛大(?)な境地になっていましたが、人形展は待った甲斐はありました。作品は小津安二郎の映画の登場人物を中心として、さまざまな子供たちの情景、妖精たちなど、目を見張るものばかりでした。どれを観ても微笑みがこぼれる。。。
さて、地下鉄で新宿へ。東口側へ出るはずが西口側へ出てしまった。。。「まぁ。こんな日もあるさ。」「うん。そうね。」寛大。寛大(^^)。。。「新宿ピカデリー」の「ナルニア国物語」の上映時 間を確認してから、コーヒー・タイム。この映画の予備知識はわたくしは皆無であったため、簡単に同行者の解説を聞く。
映画も予想以上に楽しかった。さまざまな矛盾点もあるのだが、今は整理できない。いずれこの感想はゆっくりと書くことにする。かくして新宿の夜は更けて、今度は帰路のわたくしの乗った電車が事故のために遅れる。乗り継ぐはずだった最寄駅までの電車の最終には間に合わず、乗った電車は最寄り駅二つ前の駅でアウト。「まぁ。こんな日もある。。。」長い列の後に並んでタクシーを待つ。タクシー代は結構多額。日付はもうとっくに二十五日になっていた。でも楽しい時間だった(^^)。
Mar 23, 2006
かもめ食堂 群ようこ

読後にほのぼのと、またさわやかな気分になる本に久しぶりに出会った。たまたま映画「アメリカ・家族のいる風景」を観た折に、この本の映画化されたものの予告編を観たことがきっかけとなって、この本を読む羽目に(?)なりました。映画はまだ観ていませんが、この本は映画のために書き下ろされたもののようです。
さて、これは三十八歳、四十歳ちょっと、五十歳の三人の独身女性が、日本を出てたまたまフィンランドのヘルシンキで出会うお話です。そこで主人公サチエの経営していた「かもめ食堂」が物語の中心の場となります。物語の登場順に女性の年齢が高くなるのでした(^^)。
サチエ(三十八歳)は小柄だが武道家の父の指導のもとで育ち、武道の心得は相当なものである。料理には関心が深く、母亡き後は彼女はさらに料理の研究に熱心だった。そして自分らしい食堂経営を求めて、父に別れを告げ、宝くじで当たった大金を元に、ヘルシンキへ向う。地元では東洋人の小柄なサチエは子供のように見えたらしく、「かもめ食堂」は「こども食堂」と呼ばれていた。(小さいから、どーした?・・・・・・独り言です。)
サエキミドリ(四十歳ちょっと)は、目をつぶってたまたま地図に指先が落ちたところがヘルシンキだったという理由で、この土地を訪れる。サチエとは書店で出会って、アパートに同居して店を手伝うことになる。
シンドウマサコ(五十歳)は両親の死後に、両親の介護中にたまたまテレビで見たヘルシンキに好感を持っていたという理由で、この土地に現れ、「かもめ食堂」を訪れる。「かもめ食堂」に働くのは三人となり、店はゆっくりとおだやかに地元に根をおろしてゆく。
この三人の女性の日本における生活が、貧しかったわけでもなく、とりたてて不幸であったわけでもない。その背後にあったものは、老親問題、あるいは死など、どこにでもみられるようなものだ。その時期に、自分探し(・・・というほど大袈裟でもなく。)のために、くじを引くように「ヘルシンキ」を訪れて、偶然に三人は出会った。はっきりとした意志やら目的やらがあったのはサチコだけだったろう。これはちょっと歳をくった女性たちの素敵なメルヘンではないだろうか?
(二〇〇六年・幻冬社刊)
Mar 22, 2006
対詩 詩と生活 小池昌代&四元康祐
わたくしは詩集の感想を書くことをみずからに禁じてきました。それは拙い詩の書き手でしかないわたくしに、必ずはね返ってくるものだと思いますし、元来とても苦手でした。そのわたしくしが「書きたい。」と思ってしまったのです。さて困ったことに。。。
この対詩集について書く前に、この対詩の出発点となっているヴィスワヴァ・シンボルスカの詩「書く歓び・四元康祐訳」を紹介しておきます。この詩の存在は、シンボルスカ・ファンのわたくしとしてはとても大きな歓びでした。そのためにこの拙文を書いているのだとさえ思えます。四元康祐の翻訳の言葉もとてもうつくしいと思いました。
書く歓び ヴィスワヴァ・シンボルスカ(四元康祐訳)
書かれた鹿はなぜ書かれた森を飛び跳ねてゆくのか
その柔らかな鼻先を複写する泉の表面から
書かれた水を飲むためだろうか
なぜ頭をもたげるのだろう なにか聞こえるのか
真実から借りたしなやかな四肢に支えられて
鹿は耳をそばだてる――私の指の下で
しずけさ その一語すらが頁を震わせる
「森」という言葉から生えた
枝をかき分けて
白い頁に跳びかからんと、待ち伏せるのは
ゴロツキの文字どもだ
その文節の爪先のなんと従属なこと
鹿はもう逃げられまい
インクの一滴毎に大勢の狩人たち
細めた目で遠くを見つめ
いつでも傾いたペン先に群がる準備を整え
鹿を取り巻き ゆっくりと銃口を向ける
今起こっていることが本当だと思い込んでいるのだ
白地に黒の、別の法則がここを支配している
私が命ずる限り瞳はきらめき続けるだろう
それを永遠のかけらに砕くことも私の気持次第だ
静止した弾丸を空中に散りばめて
私が口を開かない限りなにひとつ起こらない
葉っぱ一枚が落ちるのにも たたずむ鹿の小さな蹄の下で
草の葉一枚が折れ曲がるのにも私の祝福がいる
私が総ての運命を支配する世界が
存在するということなのか
私が記号で束ねる時間が
私の意のままに存在は不朽と化すのか
書く歓び
とじこめてしまう力
いつか死ぬ一本の手の復讐
この一編の詩(ポーランド語から英訳されたもの。)を翻訳した四元康祐が小池昌代に渡し、その詩を読んだ後から小池昌代の一編目の詩「森を横切って」は始まる。この一編目では小池昌代は「ヴィスワヴァ・シンボルスカ」を超えることはできない。この詩の全体像に言葉は届いていない。ここから交わされはじめる二人の対詩は手紙のように長く、シンボルスカの詩に寄り添っているわけではないようだ。ただタイトルの示した「書く歓び」は二人のなかに続いているようだ。また「対詩」を書く時には必ず一人の読み手が待っているという至福もあるのではないだろうか。
しかしシンボルスカはいつでも多くの読み手に向って詩を書き、言葉に変換することは不可能とさえ思えることに、やわらかな、そして強い言葉を与えて「詩の言葉の力」を信じた稀有な詩人だと思います。ポーランドという風土はそうした言葉を育てるところでもあるのかもしれません。
さて、詩集の中間部に置かれた小池昌代の「動く境界」と四元康祐の「ハリネズミ」の二編がこの対詩集「詩と生活」というタイトルの意味にようやく到達していて、「ヴィスワヴァ・シンボルスカ」の一編の詩から共に自立した(あるいは離れてしまった。)かに見えます。さらに生活者としての男女の詩人の、それぞれの個性と差異、幼い者へのいのちの伝言の方法が浮き彫りとなってくる。その二編を並べてみましょう。
毛布をかけると 子供ははぐ
どんな寒い夜も
かけると はぎ かけなおせば はぐ
それでそこには
湧き水のような
やわらかな むきめ があるのだとわかる
世界は むかしから きりもなく
そうして 内側から むかれ続けてきた
(後略) (小池昌代・うごく境界)
(前略)
黙ってハリネズミを葉陰に置こうとすると
娘は同じことをなんども叫びながら私の背を拳で叩いた
こいつはいま、独りで一所懸命死のうとしているんだから、その
邪魔をするな、そう云ったのが自分ではない父の
そのまた見知らぬ父のように聞こえた
(後略) (四元康祐・ハリネズミ)
眠っている子供が繰り返し毛布をはぐ。子供の体内からは絶えず「湧き水のようなむきめ」が生れるからだという。これは子供のいのちが産まれた時からいだいている、絶えることのない成長への驚きであり、汗ばむいのちへの全肯定だと思えるのだ。これが生活者あるいは母としての詩人の視線だ。
しかし、父親であり、生活者である四元康祐の詩人の目はすでに娘に「死」を伝えようとしているかのようだ。庭の隅でみつけた瀕死のハリネズミを娘はなんとか助けたいと願うのに、「独りで一所懸命死のうとしているんだから」と父親は言う。その夜は冷たい雨が降って、翌日にはハリネズミは死んで、庭に穴を掘り埋葬することになったが、娘はその埋葬の瞬間にも「動いた。」と言うのだが、その後で娘はようやく「いのち」の断念をするのだった。
また四元康祐の詩「築地」では、生活者、父として、詩人としてこのようにも書いている。
命を殺めたり育んだりして金を得たことが私にはついになかった
正業になり得るだろうか たとえなったとしてもそんな詩も
タダで書かれた詩もおなじ詩の名で呼べるのかそれとも似て非――
「邪魔だよ」
「築地」とは、活きた魚が血まみれに解体される場所、育てられ、あるいは捕獲、採取されたさまざまな山海のいのちが売り買いされる場所、仮説も虚構もない場所をさまよいながら、一人の詩人はこんなつぶやきももらすのだった。さまよう詩人は「築地」で忙しく立ち働く男にふいに「邪魔だよ」と言われる。
詩は大切なものだ。しかしいのちと引き換えるほどに大切なものではない。詩を思うこともなく生涯をいきる生活者の方がはるかに多い世界で、わたくしたちは何故詩を書くのだろうか?そして詩を書く者が生活者ではなかったこともない。それがこの対詩集全体の底に流れてるテーマでしょう。
【付記】
さらにこれを書いたもう一つの理由は、わたくしの「相聞」や「連詩」への深い興味がこれを書かせているのだと思います。わたくしが一編の詩に読み手として向き合う時、その詩が大変魅力的であればあるほど、わたくしはいつの間にか、その一編に応える書き手となっていて、感想は無意識に排除されているということだったと思います。
ホラ。やっぱり感想は書けなかったではないか。
耳元で誰かが囁いている(^^)。。。
(二〇〇五年・思潮社刊)
Mar 17, 2006
言葉のこわさなど。。。
すでに社会人になっている愛娘から、最近になってわたしの記憶にはない思いがけないことを聞かされて、ちょっと驚いてしまった。娘は小学生の時に学校で「戦争」について学んだけれど、「ただただ、こわいだけだった。」と言う。どうやら小学校が招いた「戦争の語り部」の話を聞いてきたらしい。そのこわさから救われたくて、帰宅後の娘は母親のわたしに「もう、戦争は起きないのでしょ?」と質問したらしい。その時わたしは娘に「戦争がなくなることはない。」と答えたらしい。つまりわたしはその時の娘の幼い恐怖感を救ってやることができなかったのです。
それから何年娘はその恐さを抱いていたのだろうか?娘は「ただただ、わたしにだけはそんなこわいことは起こらないでください。」と願っていたという。張り倒してやりたいようなエゴイズムであるが、幼い娘にとっては、それが精一杯の忍耐であったのだろう。けれどもその質問にわたしは「もう戦争は起こりませんよ。安心しなさい。」などという嘘を言えるわけがなかったではないか。
ともかく、娘はその恐怖を超えて無事に大人になった。「戦争」というものの実態は、新聞もテレビもネットも書物もいやというほどに情報を提供してくれるので、今や娘の方が知識としては上回ったことだろう。わたしの「戦争」の知識の底流は父母や祖父母の話なのだから、比べようはないが。
戦争の記憶が遠ざかるとき、
戦争がまた
私たちに近づく。
そうでなければ良い。 (石垣りん「弔辞」より)
上記のようなことを書いていたが、わたしは今でも不用意に言葉を落としてしまって、誰かを傷つけていることはあるのだろう。どうしても拭いきれない不条理に陥ると、言ってはいけないことを口走るのかもしれない。昨夜から春嵐が続いている。
Mar 11, 2006
北原白秋 三木卓

大きなる手があらはれて昼深し上から卵つかみけるかも (雲母集より)
この評伝は「短歌研究」に四十一回の長期連載という経緯があり、二十五年間筑摩書房が三木卓氏の原稿完成を待ったという経緯もある。それほどに北原白秋のあの時代を背負った仕事は膨大なものであり、その生き方も熱く、多彩なものであったと、わたくしはあらためてそれに気付くのだった。そしてこの本のなかにおける三木卓の白秋解釈あるいは批判の言葉には時々キラリと光るものがあって、心が躍った。
この本を読んでいる時期に、わたしは幾人かの若い詩人に出会う機会があった。彼等は咽喉元から自然に発せられる音や、指先から流れ出る言葉によって詩作しているかのように見える。若い感性はそれを力とできるのだろう。その「若さ」がどこまで持ちこたえられるかと思う時、北原白秋の貪欲とさえ思える「言葉への執着」「愛着」というものが、時を超えてわたしに迫ってきたように思うのだった。若い彼等の作品が百年の時を超えてもなお、白秋の詩、短歌、童謡のように、人々がふいに口ずさむような一節を残せるのだろうか。(あ。わたくしの詩は、死とともに柩に納めてもらうつもりです。おかまいなく(^^)。。。)
三木卓が最終章で書いているように、「夭折する詩人は短楽章だけを作って終わるが、白秋は幾人もの詩人の仕事を多楽章にわたってしなければならなかった。」のだろう。その多岐にわたる仕事量の膨大さを支え続けたものはなんだったのだろう?
そのはじめにあったものは、白秋の潤沢な少年時代ではないだろうか?それが天性の白秋の才能をゆたかに実らせた土壌であったことは認めざるをえない。では「貧しさ」はどうか?という反論ももちろんあるだろうが、あえて極論を言えば、潤沢が許された者はそれを存分に享受すべきだ。それは三木卓の言葉を借りれば「作品は生身を代償にして成立する。どのような作家でもこの条件を逃れることはできない。」「最後まで彼を捉えて離さなかった心の飢えの深さ(あるいは自己消耗への強烈な欲望)の結果」という真摯な心の作業を白秋が生涯をかけて継続したということで、充分に相殺されると思うからだ。
・・・・・・と言っても白秋が純粋に文学に向き合ったということだけではない。彼はその時代(与謝野鉄幹、晶子の後を歩き、萩原朔太郎の先を生きた。)の見事なパフォーマーであったし、高名ともなれば政治的野心も働いたし、「戦争」への向き合い方には三木卓の厳しい批判もある。さらに自らの老いとの哀しい葛藤もあった。
さて、わたくしは一応女性でありますので、白秋の三人の女性(他にもいるのでしょうが。。。)にはおおいに興味がありました。まず一番有名(?)な女性問題は、人妻「俊子」との恋愛によって姦通罪で投獄されたことでしょう。出獄後にも共に暮したということがいかにも白秋らしい生き方だったと思うが、破局はやはり訪れた。
わが睾丸つよくつかまば死ぬべきか訊けば心がこけ笑ひする
罪びとは罪びとゆゑになほいとしかなしいぢらしあきらめきれず
監獄(ひとや)いでぬ走れ人力車(じんりき)よ走れ街にまんまろなお月さまがあがる
次に登場するのは「章子」である。ううむ「あきこ」はいい。「晶子」はわたくしにとって最高と思える女性であるし、「昭子」はわたくしである。なかなかよろしい(^^)。すみませぬ。お話がすべりましたが「章子」は白秋の文学的理解者として結婚。病弱であった。やがて彼女も白秋の元を去る。ここまでの白秋は「結婚生活」というものと「文学」との重なりのなかで生きたと思える。文学的理解者が必ずしも文学者のよき伴侶ではないことの顕著な例と言えるでしょう。
三人目の妻として「菊子」が登場する。二人の子供を授かり、どうやら安定した平凡な家庭生活を得たようだが、家族の絆はいつでも人間という不完全ないきものが作っているものである以上、あやうく成立していることは言うまでもないことだ。それを支えたのは菊子だろうとおもいます。
この著書は北原白秋と三木卓とが共に抱え続けている、物書きの茫漠とした宿痾のようなものの響き合いではないだろうか?それがこの著書全体をより高く昇華させたのではないかと思われます。三木の少年期にはすでに白秋はこの世にはいない。友人、弟子、家族というような「しがらみ」のない距離感が、三木のペンを自由に走らせて、二十五年をかけて書き上げた労作である。三木卓に「ありがとう。」と申し上げたいだけで、実はわたくしごときが、他愛のないことを書くことは恐れ多いのである。
(二〇〇五年・筑摩書房刊)
Mar 10, 2006
絵本詩集 ららばい

「絵本詩集 ららばい」という新しいページを作りました。トップページの「詩の部屋」からお入り下さい。挿絵は桐田真輔さんのホームページ「KIKIHOUSE」で描かれたものをお借りしています。清水鱗造さん、桐田さん、ありがとうございました。
あ。上の挿絵も桐田さんが描かれたものです。かさねがさね。。。
Mar 07, 2006
死者の書

監督 川本喜八郎(人形作家) 原作 折口信夫
した した した。。。
こう こう こう。。。
はた はた ゆら ゆら はたた。。。
この物語は音楽のようだ。。。
三月二日午後、岩波ホールにて、川本喜八郎監督による、人形アニメーション映画「死者の書」を観ることになって、何故か心をせかされる思いで、折口信夫の同名の原作を再読しました。これほどに映画を観る前に原作が気になったという経験はかつてなかったのだが。。。映画は、原作を少々省いた部分があったが、原作から想像された「大津皇子」の幻想の姿、「藤原南家郎女」の美しい現実の女性像、また全体の物語は原作に忠実であろうと作られたものであったと思う。
この「死者の書」の物語の舞台は奈良時代の平城京。最も新しい文化であった仏教を軸にして、語り部による当麻寺を麓に抱いた二上山の伝説、その時代の富と権力の争い、疫病など・・・さまざまな要素が盛り込まれた物語であって、わたくしには、とても簡単に書き尽くせないと、すでにペンを投げかけている。。。
大津皇子(天武天皇の皇子)は「磐余の池」にて非業の死を迫られたこと、その処刑の直前に、皇子に一目逢おうと駆けつけた「耳面刀自(みみものとじ)=藤原鎌足の女。不比等の妹。大友皇子の妃」の美しさのために、死者となってからも皇子の魂は鎮まることがなく、五十年後に彷徨い出ることになる。その魂に呼ばれたのが、「藤原南家郎女(ふじわらなんけいらつめ)=藤原武智麻呂(むちまろ・不比等の子)の子の豊成の娘」であった。この物語の主軸は、清らかな生者の郎女による、死者大津皇子の「魂鎮め」であるだろう。そして民俗学者・歌人・詩人である折口信夫のあらゆる美的要素が凝縮された「書」であることも見逃すことはできないことだろうとおもわれます。
この映画を観たこと、その原作を再読したこと、その季節はまさに「馬酔木」の花の咲き出す季節であったことも、ずっと忘れられない思い出になることだろう。語り部の歌の一部を引用しておきます。
ひさかたの 天二上
二上の陽面に、
生ひをゝり 繁(し)み咲く
馬酔木の にほへる子を
我が 捉り兼ねて
馬酔木の あしずりしつゝ
吾はもよ偲ぶ。 藤原処女
【付記】
ちょっと気持の負担の多い時期なので、書くことは先に延ばそうと考えましたが、湧き立っている今の気持を忘れないうちに、未消化ながら、とりあえず書いておくことにしました。
Mar 04, 2006
アメリカ・家族のいる風景

監督 ヴィム・ヴェンダース 原案・脚本・主演 サム・シェバード
二月二七日午後、「シネスイッチ銀座」にて、桐田さんと一緒にこの映画を観ました。観終わった後で哀しくならなかったのは救いであった。ハッピー・エンドでない映画(本も。)は辛いのだ。
「家族」とはなんだろう?この主人公のハワード・スペンスは、デビュー当時に、二人の恋人を捨てた西部劇俳優である。その二人にはそれぞれに息子と娘が産まれて、すでに若者になっている。ハワードには常に酒、ギャンブル、麻薬、女性問題とすさんだ生活が続いていたが、ある日突然にロケ先から姿を消して、三十年間会わなかった母親「ネバダ州エルコ在住」に会いに行き、その後にかつてデビュー映画の舞台となった街「モンタナ州ピュート」へ家族探しに行くことになる。
同じ頃に、娘のスカイはまだ見ぬ父を、映画や雑誌、ネットで追いながら、自分との繋がりをいつもつかもうとしていたが、母親の死という不幸な出来事があり、母の遺骨を連れて母の思い出の街「モンタナ州ピュート」を訪れていた。
息子アールとその母親ドリーンは共にその街で暮していたが、息子は父親を知らされていなかったので、「父の不在」という心の空白を埋めようがないまま、すさんだ生き方をしていた。突然、母親から本当の父親を知らされて、みずからの生き方が父親と同質の生き方だったことに気付き、彼はさらに混乱し、すさむことになる。
ハワードはこの街で二人の子供と出会うわけだが、娘スカイの「静謐」と息子アールの「狂乱」が対照的に描かれている。これはとりもなおさず二人の母親のハワードへの「愛の姿勢」も浮き彫りにされることになる。そして、娘スカイがこのちりじりの家族を繋いでゆく天使だったと思われる。
「家族」とはなんだろう?さまざまな愛の修復をしたり、あるいは連帯を強化したりしながら、家族の階段を一歩づつ登ってきた家族にだって「離散」や「崩壊」や「孤独」が待ち伏せしていることはあるえる。ハワードの家族のように「離散」や「崩壊」や癒しようもない「孤独」から、再出発を試みるという生き方もある。いずれにしても、それらは「こころの丹念な作業」の継続によるものであって、形骸だけでは成しえないことだ。ラストはハワードの子供たちが父親が残していった車(これはハワードの父のもの。)に乗って父親の戻っていった撮影現場へ向うシーンで終わる。このスカイブルーの車は三代に乗り継がれたことになる。ここから家族再生の長い旅がはじまるのだろう。。。
この映画はアメリカで製作されたものであるが、監督はドイツ人であるとのこと。これはアメリカの「家族意識」への一つの問いかけとも言えるのではないだろうか?また、この映画の舞台となったアメリカ西部の広大な原野を監督は「空虚な場所」と名付けたが、地上に今もある広大な原野というものは「貧しい土地」であるというのがわたしの考え方である。
【付記】
今日は我が愚息の誕生日。雛祭りを避けて、四日にこの世に産まれた男の子である。偶然とはいえ、この日にこの映画の感想を書いた。ではお祝いの花などを。。
Feb 26, 2006
花と古デジカメ
我がボロ・デジカメを買い換えるか否か、目下思案中です。明日は新品を買うつもりでいますが、この古デジカメの最後のテストとして花の写真を撮ってみました。おおお!結構いけるではないか!と自画自賛。ううむ。。新品を買うべきかどうか、悩む。。。
Feb 20, 2006
同人誌
個人詩誌「真昼の家」を休刊してから五年が経った。同人誌への参加というものから、なんとなく身を引いたのはもっと前の時期になるだろうか?とりあえず無所属(?)の間に、BBSを作っていただいたり、ホーム・ページを持たせていただいたり、さらにブログも持たせていただいたりと、わたしの詩作を含む活動の場はずっとネットの中だったが、どうしたことか紙版の同人誌「re Pure」に参加させて頂いた。
この、同人誌の母体となっているのは、「PSP」という詩の合評会(代表=竹内敏喜さん)なのですが、ここへのわたくしの参加そのものが「遅れてきた者」であり、同人誌への参加も創刊号では決心できず、二号からの参加という、これまた「遅れてきた者」であった。
前口上が長いが、ともかくネットから紙版への扉を久しぶりに開いた。ドアーがキーキー・ギシギシと音をたてているようだが、紙版の世界からは、ちょっと違う風が吹いてきたという感触が頬のあたりに感じる。ちょっと遅れましたがご報告です。
この詩誌の装丁と製本は水仁舎の北見さんです。画像のスキャンがうまくいかなくて残念ですが、タイトルは黒、「2」は深く輝く赤、小さなローマ字は参加者の名前ですが、これは金色です。表紙は白の厚手の和紙、素晴らしい和綴じの冊子です。
【付記】
水仁舎
↑から北見さんのブログに行けます。この詩誌の美しい画像が掲載されています。是非ともご覧下さいませ。また、ご本人の北見さんから訂正をたくさんいただきました。以下に訂正記事をコピーしておきます。北見さん、ごめんなさーい。
【表紙の紙は和紙ではありません。でもなかなか良い質感でしょ。 それから綴じは和綴じではなく中綴じの糸かがりです。】とのことでした。すみませぬ。
Feb 19, 2006
Feb 08, 2006
追悼の歌
「書の至宝」展で展示されたものを読み解きしながら、思い出したものがありました。読み解きはとても困難でしたが。。。亡父の従妹のおばさまが、父の死後にわたしに送って下さった短歌の短冊です。父が亡くなったのは平成九年(一九九七年)の八月でした。これも読み解きができなくて、おばさまにお電話をしてしまいました。おばさまは「しょうがないあっこちゃんねぇ。。」と嘆きながら、教えてくださいました。なつかしい思い出です。
ふるさとの(能)相馬の海に(仁)野に山に(爾) 美(み)たましずかにおわす(須)君かも(可裳)
ゆく夏の(能)足利の地に蝉し(志)ぐれ お(於)くつきふかく安かれと祈る
Feb 07, 2006
Feb 05, 2006
言葉のもどかしさなど。。。
四日、国立の一ツ橋大学に隣接する「佐野書院」にて、「ル・クレジオ」を迎えてのワークショップを聞きに行きました。題して「外部のヨーロッパ人 ル・クレジオを迎えて」というものです。詳しくは桐田さんの「吸殻山日記」をご覧下さい。(ずる。(^^;)。。。)
「ル・クレジオ」は一九四〇年ニースで生れていますが、彼の自称は「フランス系モーリシャス人」とのことです。幼児期に戦争があったこと、それによって国籍が数回変わったこと、さまざまな土地を見たこと。それが彼にマイノリティー的感覚を育てるもとになっているように思えました。その感覚に寄り添うように、さまざまな人々が「ル・クレジオ」との細い通路を探り出し、そこから語りかけるしかないのだが、それらはすべて「ル・クレジオ」の全体像に触れることはできない。
かくいうわたしは、まず「ル・クレジオ」の通訳の発言を待つことになる。その間にすでに理解の時間や解釈がおそらくずれているにちがいなかった。「アメリカ先住民世界」が「ル・クレジオ」に与えた影響はかなり大きいものであるらしいが、そしてそれはわたしも興味を持っていた世界だが、それをわたしからのか細い通路にしてしまうことは、なんとも短絡的で避けたい気持が働いた。
人間同士は心の形や姿や温度を見せることはできない。そこに「言葉」が働きかけるしかないのだが、それはなんともどかしい作業だろうか?「ル・クレジオ」の周辺をめぐりながら、わたしはただ「言葉のもどかしさ」を抱いて帰りの電車に揺られていたように思う。
「ぼくの真実に近づくために、ぼくは直感および言語という貧しい道具しか持ち合わせがない。だがある程度は、これらの道具でぼくにとっては十分なのだ。確実性におけるそれらの貧しさは、偶然性における豊かさである。」
立春とはいえ、快晴のとても寒い一日でした。一ツ橋大学構内にて。
Feb 03, 2006
書の至宝・日本と中国
二日午後、桐田さんと上野の東京国立博物館にて「書の至宝」を観てきました。展示総数が想像以上に多くて、観にいらっしゃる方々の人数も予想以上でした。閉館時間にせかされながら観ることになってしまいましたが、わたしの主なる目的だった「良寛」の屏風に書かれた書はしっかり観てまいりました。詩人正津勉の言葉を借りれば良寛の書は「脱力」だったと思います。のびやかで、やさしい書でした。
博物館を出ましたら、もう陽は落ちていましたが、うつくしい噴水を観ることができました。
噴水の頂の水落ちてこず 長谷川櫂
「噴水」は夏の季語ですが、何故かここの噴水を観るのは冬の季節ばかりのようです。まるで白いかき氷を噴き上げているようです。昨年の二月二四日には「踊るサチュロス」を観たことなど思い出しましたが、その日の帰りの時間にはぼたん雪が降りました。あらゆる人間の時間はゆるやかに、時には激しく流れ続けているようです。
その後は新宿にて、いつもの場所で、いつもの面々で。。。
Feb 01, 2006
朝日新聞「ののちゃん」
朝刊連載のいしいひさいちの漫画である。おそらく今話題沸騰の「ホリエモン」事件を揶揄したものではないだろうか?彼の漫画は時々、時代に対してするどいつっこみを入れるなぁ~と思います。自衛隊のイラク派遣の始まった時期にも、ののちゃんのおばあちゃんに「これは、どう見ても出征やでぇ。」などと言わせた漫画家である。
わたしはこの事件と同時進行的に下記の「獄窓から」を読んでいましたので、わたしの「刑務所」に関する時代感覚はごちゃまぜになってしまって、おおいに困った。。どだいあたしの弱いおつむではねぇ。
獄窓から 和田久太郎
大雪で国旗出すのを忘れたり (十三歳・丁稚見習い時代)
言ひ訳の為の饅頭三つかな (同上)
金魚摑み殺したる性慾の悩み (大正五年)
アナキスト和田久太郎は明治二六年(一八九三年)生まれ。昭和三年(一九二八年)秋田刑務所にて縊死。では和田久太郎の罪状とはなんだったのだろうか?
発端は、大正十二年(一九二三年)の関東大震災の折に起きた「亀戸事件」と「朝鮮人の大虐殺」、さらに甘粕大尉による「大杉栄等の暗殺事件」にある。この時の戒厳令司令官陸軍大将を務めていた福田雅太郎への暗殺未遂事件(大正十三年・一九二四年)によるものである。この暗殺計画の主なる目的は、同士である「大杉栄等暗殺事件」への復讐として、村木源次郎とともに実行されたが、「未遂」というよりは「頓馬(失礼!)」と言えるような結果だったと思う。
大杉栄等三人を暗殺したとされる甘粕大尉の刑期は二年であったが、和田久太郎の刑期は福田雅太郎に軽症を負わせたにすぎなかったが、無期懲役だった。(和田は「死刑」を望んだのだったが。)甘粕は「軍人」であり、和田は「民間人」、その時代の「法」というものが曖昧模糊としたものであり、裁判も当然ながら、その不平等な実情を見せるものだ。しかし和田久太郎は民衆がそれに気付き、その考えは熟してゆくものであることを信じていたように思えます。和田は再審請求をしなかったのです。
和田久太郎は大正十三年(一九二四年)九月から翌年の九月までは、市ヶ谷刑務所の未決監に入監するが、無期懲役と決まってからは秋田刑務所に移送されている。この和田久太郎が困難な状況に置かれていることは疑いようもないことだが、書かれた随筆、書簡、俳句、短歌、童謡、詩は実に明るいし、かろみさえあった。これは和田自身の天性のものなのか?さらに和田には多くの同士たちの温かい友情もあり、和田もまた外にいる人々への思いやりと明るさを最後まで失わなかったということは奇跡のようだ。。それはまた和田久太郎の民衆への信頼にも結びついていたようです。書かれているものの大半が、刑務所内における苦しみや寂しさでもないことにも驚かされます。
あくびより湧きいでにたる一滴の涙よ頬の春を輝け (序歌)
今日はまた網笠越しに見ゆるかな青空遠く昼の夢月 (大正十三年)
月も照らせこれも浮世の一世帯 (大正十三年)
永別の秋となり行く風雨かな (同)
もろもろの悩みも消ゆる雪の風 (昭和三年・辞世)
この本は、三回に渡って出版されています。一回目は、昭和二年(一九二七年)に市ヶ谷刑務所時代に書かれたものが「獄窓から」として労働運動社から出版されました。二回目は、昭和五年(一九三〇年)に、秋田刑務所で書かれたものを加えた形で、故・近藤憲二によって編纂され、改造社から出版されました。三回目のこの本は復刻版であり、それに秋山清の解説と、鈴木清順書き下ろしの「物語・村木源次郎」が新たに加えられています。
【付記】
それにしても、わたしは何故この本を読もうと思ったのか、今となっては理由がわかりませぬ。某大学図書館の閉架図書となっていた本を、その大学関係者から借りていただいてまで手にした本でした。おもしろいことに、この大学の閉架図書というものは半年間も借りられるのですね。期間延長も可能だとのことでした。もう三十年以上も前に出版された本です。わたしとしましては、大変に不慣れなことを書きました。こうした問題について詳しい方がいらっしゃると思いますが、誤りがありましたらどうぞご指摘くださいませ。
(一九七一年・幻燈社刊)
Jan 23, 2006
ニート 絲山秋子
これは「ニート」「ベル・エポック」「2+1」「へたれ」「愛なんていらねー」の五編からなる短編集である。一編づつ追いながら軽いメモを書いておきたいと思う。
【ニート】
どうやら生活の安定している作家である「わたし」が、かつての恋人であり、ニートの「キミ」の困窮生活を救うために、経済援助を申し出ることからこの物語ははじまる。それはおわりの時を決めかねる約束であるが、「わたしは約束を守る女だから、絶対と言ったら絶対なのだ。」と思っている。この二人の関係は恋人でもなければ友人でもないが、この「わたし」は愛の永続性をしずかに信じていたのではないのだろうか。。。
【ベル・エポック】
主人公の「典ちゃん」が、婚約者の突然の死によって故郷へ帰ることになった友人「みかちゃん」の引越し準備を手伝いながら、一日を共に過ごして、「みかちゃん」の思い出話を聞く物語である。いつかその友人の故郷へ訪ねるという約束をするが、見送ったあとで、主人公は友人と二度と会うことはないだろうと感じる。「みかちゃん」と「典ちゃん」の別々のかたちの深い喪失感が読み手の胸に重く残る。
【2+1】
「ニート」の続編である。2+1とは、「わたし」が女友達と二人で借りているマンションに、ニートの「キミ」を同居させた数である。「キミ」との共同生活はやがて同棲生活となり、女友達はある日黙ってメモを残してマンションを出てゆく。「もしもキミの子供を身ごもっていたとしたら即座に殺すだろう。子供なんてニート以下だ。」と「わたし」は思っている。やがて「キミ」は郷里に帰り「わたし」は一人の生活に戻った。切れ切れの愛だ。
【へたれ】
主人公の男性は東京のホテルマン。七歳で母親を亡くし、母親の従妹にあたる独り身の「笙子さん」に育てられる。父親の再婚の際にも、「笙子さん」との名古屋の生活を選んだ少年だった。結婚したが妻に出て行かれたという過去がある。大阪の歯科医「松岡さん」との偶然の出会いから「遠距離恋愛」が始まる。幾度目かの大阪行きの日に、彼は突然「笙子さん」の住む名古屋で下車してしまう。その名古屋までの列車のなかで彼は少年時代に飼っていた、たくさんの蛙を思い出し、「笙子さん」の書棚にあった草野心平の詩「ごびらっふ」を繰り返し思い出していたのだった。これは孤独な愛の復路ではないのか?
ああ虹が。
おれの孤独に虹がみえる。
おれの単簡な脳の組織は。
言わば即ち天である。
美しい虹だ。
ばらあら ばらあ。
【愛なんていらねー】
大学教授「成田ひろみ」は、元教え子であり刑務所帰りらしい「乾ケンジロウ」と再会して、彼女は乾との異常性愛に翻弄されることになる。人間は愛によってみずからをより浄化してゆく人間と、愛の裏に潜むエゴイズムや凶暴性を表出してゆく人間とがいるのではないか?愛とは、この二つの極へ向って働きかける力を内包しているのではないか?「乾ケンジロウ」は、屈折した精神の道筋を歩いてきたか、あるいは極度の苦難を潜りぬけてしまった人間だと思える。これが彼の愛のあり方なのだろう。
【付記】
この本を読みながら、しきりになつかしく思い出した詩は、黒田三郎の「賭け」だった。これを懐古などと言うなかれ。わたくしは絲山秋子の数冊の本のなかから彼女が描き出す現代の愛のあり方について、繰り返し考え直さなくてはならなかったということは否定しない。だが。愛に傷つくことを恐れてはならない。
僕は
僕の破滅を賭けた
僕の破滅を
この世がしんとしずまりかえっているなかで
僕は初心な賭博者のように
閉じていた眼をひらいたのである
(2005年・角川書店刊)
二十一日の初雪
雪の朝の目覚め際ではこわい夢をみないものらしい。いつもよりゆったりと眠っていた自分に目覚めてから気付いた。とても不思議な気分でした。窓の外は真っ白な世界が広がり、音もなく雪は一日中降り続いた。この土地ではめずらしい大雪でした。
肋骨はたましいの籠冬薔薇
山越えて深雪の地獄あるそうな 昭子
Jan 21, 2006
森のなかの1羽と3匹 大島弓子
大島弓子は大変有名な漫画家であるらしい。今年になって彼女の名前を初めて知りました。しかしこの本は漫画ではありません。童話のような、あるいは詩のような言葉と絵の絵本なのです。1羽は「カッコー」、3匹は「トンボ」「カエル」「セミ」ですが、どの生き物に対しても「いのち」をテーマにしてありました。これらの生き物が絵のうえでも言葉のうえでも擬人化された表現になっていますが、その擬人化のバランスがとてもよい。奇麗事に陥らず、さりとて生々しい残忍さにも走らず、みごとにこの生き物たちがこの絵本のなかでうつくしく息づいていました。
これが飛ぶということだ
誰に教えてもらわなくても
そのつどをクリアしてゆけば
一生は自然にやれるものなのだ (「セミ」より)
わたしもこんな絵本詩集を作ってみたいなぁ~(^^)。。。
(1996年・白泉社刊)
父の顔
「ガラスの使徒」を観た帰りに、山手線の電車のなかで、わたしは一瞬立ちすくんだ。亡くなった父とそっくりの顔立ちの男性がこちらを向いている。笑顔のように見えた。その人はまるで、あの世の父の笑顔だけを首の上に載せて、そこに立っているようだった。世の中には似た人は三人いるという説を信じてもいいかもしれない。その男性はからだの向きを変えて、父はもういなかった。断言するがわたしは「ファザー・コンプレックス」ではない。しかし父の精神の強靭さと、看護するわたしへの思いやりを最後まで通した男だったと、亡くなってからわかった。
Jan 20, 2006
ガラスの使徒
この映画の監督は金守珍。原作、脚本、主演は唐十郎。さらにわたしが期待をしたのは、中島みゆきが占い師役で出演するということだった。この期待をいだきながら、今冬としては比較的天候に恵まれた十七日に、恵比寿ガーデンプレイスにある「東京都写真美術館」で、桐田さんと待ち合わせることにしました。
世の中なにが起こるかわからない。わたしはいつでも約束時間二十分前には約束の場所に到着できるようにしているのですが、その日は事故のために電車の出発時間が十分遅れた。さらに乗り継ぐはずだった快速電車に間に合わず、各駅停車の電車に乗ることになってしまった。どうやら上映時間には間に合ったが、約束した待ち合わせ時間には遅れることになった。恵比寿駅東口からの「動く歩道」を走ったのは初めての経験であった。疲れた。人を待たせること、約束を守れないことはわたしはとてもとても嫌いなのだ。
・・・・・・と前置きが長いが、わたしはかなり映画を観る前からナーバスになっていた。この映画を観終った後では、さらにかなり哀しい気分になっていた。この映画に登場するさまざまな人間たちが、誰一人として救われないからなのだ。「ガラスの使徒」の「使徒」とは、イエスの福音を伝えるために選ばれた十二人の弟子たちのことである。転じて神聖な仕事に献身する人への敬称である。
原作&脚本&主演の唐十郎の一貫したテーマは「ガラスの使徒」である職人の池谷の一徹な生き方にあったのか、それをとりまく人間たちのさまざまな心の動乱にあったのか?監督の金守珍は原作者&脚本家を主役に起用するという試みをしているが、この意味はなんだったのだろうか?金守珍は、もとは「状況劇場」の役者だったらしい。ということは、この物語は、アングラ的な仕掛けがあちこちに配されているということだろう。舞台上の芝居がそのまま映像になったという感も免れない。この物語にはささやかながらの「成就」など一度もない。ただ「崩壊」ばかりが延々と続くのだ。もちろんハッピーエンドなどあろうはずもない。
小さな町工場で働くレンズ職人「池谷=唐十郎」の存在は、今の最先端の宇宙科学を陰で支えているのは、実は小さな町工場の熟練した職人たちであるという、昨今の事情をよく表している。 しかし工場は倒産の危機にあって、池谷と工場の専務の芹川は、整理屋の平手の執拗な脅しに追い詰められていた。その二人の前に芹川の幼馴染みだという少女の葉子が現れる。彼女の亡父も池谷と同じレンズ職人だったのだ。三人の「レンズ完成」への一途な情熱に、平手は束の間心を動かされるが、レンズはついに壊され、平手からやっと開放された三人が再生できるはずのないレンズを磨くシーンで、映画は終わる。奇跡はついに起きなかったのだ。
中島みゆきをわざわざ起用した「糸電話の占い師」が、この物語の大きな存在とはなっていないということは残念だった。彼女の不思議な魅力を映画全体に妖精のように存在させて欲しかった。
一つ気にかかることがある。「掌」である。レンズを磨く池谷の「掌」、レンズで光を集めて「掌」を焼く葉子、芹川の平手への怒りのナイフを「掌」で防いだ平手の愛人、平手の残酷な仕打ちによって「掌」を焼かれる芹川、「掌」が何度も表現される。そこだけが別の生き物のように。。。
ただし、この映画をまた観たいか?と問われれば、わたしは「イエス」とはいわないだろう。。。
Jan 14, 2006
ターシャの本
クリスマスに「暖炉の火のそばで」を自分で自分にプレゼントしたことは十二月の日記に書きましたが、このもう一冊の「ターシャの庭」は、娘が買ってくれました。良い子(ん?母だったかな?もう忘れました。。)にはお年玉が来ます(^^)。。この二冊の本は、まさに憧れ続けた生活であり、決して手に入ることのない生活です。食べるものは野菜や果実を育て、山羊を育てることからはじまり、着るものは糸をつむぐことからはじまる生活です。四季おりおりの樹木と花々にかこまれ、庭の池にはボートがあります。そしてそうして生きてきたターシャおばあさんのお顔のうつくしく、やさしいこと。。。
Jan 10, 2006
愛する大地 ル・クレジオ(豊崎光一訳)
この物語は、太陽が煮えたぎるような夏の庭で、主人公の少年「シャンスラード」が、虫の群を殺すシーンからはじまる。よく見かける子供の風景である。少年の清らかなからだや心には「憎悪」や「殺意」も潜在していて、その双方が生き生きと息づく時間でもあるのだろう。
この連想は奇異かと思われるかもしれない。町田康の小説「告白」に見られる少年期の重大なテーマは「喧嘩に勝つ」ということではなかったろうか?少年(少女も。)は生きてゆく場所を選んで生れてくるわけではない。生まれでたそこを生きてゆくために、少年は誰でも自らをさまざまな形で試さなければならないようだ。それが「虫殺し」であったり「喧嘩」であったり、あるいはまったく対極にある「優しさ」という場合もあるのではないだろうか?
シャンスラードが生きた土地は、海を片側に置く地形であり、民族の坩堝のように雑多な人間世界であり、それゆえに「生」と「死」はいつでも無造作に雑居していた。シャンスラードはその世界を肯定も否定もしない。その雑多な世界のなかにみずからの存在を見ていたようだった。
さらに、シャンスラードが大人になり、父親になり、彼は息子を通して、もう一度その世界を(あるいは宇宙も。)再確認しようとさえしていた。特別な出来事が起きたというわけではないが、世界はいつでもこのようにあるのだと、わたしはふいに気付いたような気がする。
「愛する大地」・・・・・・「愛する」ということは美しいものだけでなく、そのすべてを抱きとめるということではないだろうか?過去においても未来においても、そこにさまざまな生命や物質が存在する限り、いつでもそこは新しく、愛しいのだ。少年時代のように。。。
とりあえず、忘れないようにメモだけを書いておくことにする。
Jan 07, 2006
風邪をひいた日
五日夕方より発熱、六日早朝には解熱剤によって大汗とともに熱は下がった。自宅作業中の仕事は予定よりも遅れることになった。仕事先ではお正月返上で頑張っているのだろう、申し訳ないと思う。家事は熱のない合間に、だるい体を引きづりながら最低限はやる。仕事も家事も代理人はいない。七日の今日、たまった洗濯物を洗い、自分の汗で重くなった布団を干した。掃除もした。これから仕事である。
「病む女は家の闇だ。」と思ったのは少女期だった。わたしの母は虚弱体質ではなかったが、時には寝込むこともあった。そんな日には小学校から帰宅した時の家全体が暗かったという印象が今でもある。父の帰宅がひたすら待たれた。父は夕食を作り、わたしの話相手をしてくれた。
わたしが母親になった時に、高熱を出して寝ているわたしの布団に、夜になって幼い息子が黙って入ってきたことがある。いつもは一人で眠る子だったのだが、わたしの高熱で熱くなっている布団のなかで息子は汗をかきながら、じっと寝ているのだった。風邪をうつすかもしれない、汗をかいているという二つの心配から、息子の汗をふいてやり、着替えをさせてから一人で寝るように促したが、あの時の息子の汗を忘れない。
風邪をひいた日

